【一覧表】交通事故の後遺障害等級とは?症状や賠償金を解説
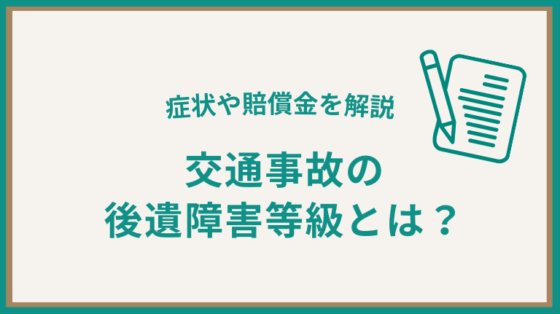
「医者に後遺障害が残るから申請してと言われたけど、自分の等級はどれくらいになるんだろう」
「自分の症状に当てはまる後遺障害等級を知りたい」
そのような疑問を抱いていませんか?
後遺障害等級は交通事故で負った怪我によって後遺症が残ってしまったことを認定機関に認めてもらう仕組みです。症状が重いものほど小さい数字に認定され、症状ごとに1~14級に分かれています。
後遺障害等級の認定を受けることで、以下のような補償が受けられます。
※その他の補償については、後遺障害等級に該当しなくても請求できるものもあります
このように交通事故による怪我の後遺症の補償を受けられるようになるのが後遺障害等級の認定なのですが、症状が残っていれば必ず認定が受けられるというわけではありません。
十分に準備をして申請をしないと、以下のようなことが発生するリスクがあります。
実際に、これまで交通事故案件を2万件以上解決してきたサリュでも、
「明らかに症状が残っているのに非該当になってしまった」
「認定された等級に対して不当に低い賠償金を提示された」
という依頼者の方々を、たくさん見てきました。
そのような事態を防ぐためにも、後遺障害等級の認定には、弁護士の力を頼ってください。
この記事では、交通事故で後遺障害が残った、残りそうであるというあなたがこの先知っておくべき、以下の内容を網羅的に説明しています。
| ・交通事故の後遺障害等級一覧 ・【等級別】後遺障害が残って請求できる賠償金 ・後遺障害は必ず正当な等級に認定されるわけではない!等級変更が認められた事例5つ ・適切な後遺障害認定を受けるためにやるべきこと3つ |
正当な認定を獲得できず、泣き寝入りするしかないような事態を防ぐためにも、この記事の内容を参考に納得できる等級の認定と賠償金の獲得に向けて行動してください。

この記事の監修者
弁護士 西内 勇介
弁護士法人サリュ
横浜事務所
神奈川県弁護士会
交通事故解決件数 500件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
京都大学法科大学院修了
【獲得した画期的判決】
死亡事故、高次脳機能障害や引き抜き損傷等の重度後遺障害の裁判経験
人身傷害保険や労災保険等の複数の保険が絡む交通事故の裁判経験
その他、多数
【弁護士西内の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】
事例339:無保険で資力に不安な相手方に対し裁判。200万円を回収した事例
事例368:主婦の休業損害を、すべての治療期間で認められた事例
事例373:過去の事故による受傷部が悪化、新たに後遺障害申請を行い、併合7級を獲得した事例
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1.交通事故の後遺障害等級一覧
まずは交通事故の後遺障害等級について理解を深めるため、認定のルールや認定される症状について解説します。
後遺障害等級の認定を得るためには、症状が残っているだけではなく、以下の条件を満たしている必要があります。
| (1)交通事故との因果関係が明確である (2)後遺障害等級の認定基準を満たしている |
交通事故が原因であることが明確で、仕事などへの影響があるという条件を満たした上で、決められた認定基準に当てはまるものが等級の認定を受けられます。
後遺障害等級で具体的に定められている、等級ごとの症状は以下の通りです。
【介護が必要な場合の後遺障害等級】
| 等級 | |
| 第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
参考:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「自動車損害賠償保障法施行令 別表第1」
【介護を要さない場合の後遺障害等級】
| 等級 | |
| 第14級 | 1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの |
| 第13級 | 1.一眼の視力が0.6以下になったもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.一手のこ指の用を廃したもの 7.一手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
| 第12級 | 1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手のこ指を失ったもの 10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの |
| 第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 第10級 | 1.一眼の視力が0.1以下になったもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8.一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの 2.一眼の視力が0.06以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9.一耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの 13.一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 15.一足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの |
| 第8級 | 1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの 4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8.一上肢に偽関節を残すもの 9.一下肢に偽関節を残すもの 10.一足の足指の全部を失ったもの |
| 第7級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの 7.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8.一足をリスフラン関節以上で失ったもの 9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失ったもの |
| 第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの |
| 第5級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.一上肢を手関節以上で失ったもの 5.一下肢を足関節以上で失ったもの 6.一上肢の用を全廃したもの 7.一下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの |
| 第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 第3級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの |
| 第2級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2.両眼の視力が0.02以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 第1級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両下肢の用を全廃したもの |
参考:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「自動車損害賠償保障法施行令 別表第2」
それぞれの等級について、詳しく解説します。
1-1.後遺障害等級14級
| 第14級 | 1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの |
後遺障害等級14級は、比較的軽度な症状について認定される等級です。
むちうちや骨折などで、痛みやしびれなどの症状が残った際には、14級9号に認定される可能性があるでしょう。
具体的には、以下のような症状で14級に認定された事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・右眼下部10円銅貨大以上瘢痕(14級10号)(横浜地判 平成24年3月29日判決) ・右頚部痛、両手の痺れ等(14級9号)(京都地判 平成25年2月5日判決) ・右示指及び左膝関節の神経症状(併合14級)(東京地判 平成28年11月1日判決) ・右耳小骨離断に伴う右難聴、耳鳴り(14級)(東京地判 平成25年1月16日判決) ・めまい、耳鳴り、嘔気、疼痛(14級10号)(山口地下関支判 平成17年11月29日判決) |
後遺障害等級14級については、以下の記事で詳しく解説しています。
後遺障害14級とは?認定基準や慰謝料など賠償金の目安を詳しく解説
1-2.後遺障害等級13級
| 第13級 | 1.一眼の視力が0.6以下になったもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.一手のこ指の用を廃したもの 7.一手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
後遺障害等級13級は、目や歯、指の欠損などの障害に対して認定される等級です。
この場合の視力とは、裸眼視力ではなく、眼鏡やコンタクトなどで矯正を加えた視力のことです。
具体的には、以下のような症状で13級に認定された事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・複視(13級)、右同名半盲(13級)(大阪高判 平成28年3月24日判決) ・正面視以外の複視(13級2号) ※パソコンを30分以上集中して見られない状態(さいたま地判 平成24年5月11日判決) |
1-3.後遺障害等級12級
| 第12級 | 1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手のこ指を失ったもの 10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの |
後遺障害等級12級は、痛みやしびれなどの神経症状、骨の変形障害、関節の機能障害などの障害に対して認定される等級です。
同じく痛みやしびれなどの神経症状で認定される14級に対して、12級の獲得のためにはレントゲンやMRI画像等の客観的な証拠で症状が説明できる必要があります。
具体的には、以下のような症状で12級に認定された事例が見られます。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・頚部痛及び腰痛(12級10号)(大阪地判 平成7年3月22日判決) ・難聴・耳鳴り(12級、自賠責非該当)(京都地判 平成29年4月21日判決) |
後遺障害等級12級については、以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。
後遺障害12級とは?認定基準や他の等級との違い、賠償金相場を解説
1-4.後遺障害等級11級
| 第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
後遺障害11級は、目や耳の障害のほか、脊柱の変形や指の欠損、内臓の機能障害などで認定を受ける可能性がある等級です。
交通事故では、脊椎(背骨や腰骨)の骨折の後遺症として、脊柱変形が見られるケースがあります。
具体的には、以下のような症状で認定された事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・嗅覚脱失、頭部外傷後の精神神経症状等(併合11級)(東京地判 平成18年3月14日判決) ・第一腰椎圧迫骨折後の脊柱変形(11級7号)(横浜地判 平成29年1月25日判決) |
1-5.後遺障害等級10級
| 第10級 | 1.一眼の視力が0.1以下になったもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8.一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害10級は、目や歯、聴力の障害や、指の障害、手足の関節の機能障害などで認定される可能性のある等級です。
10級に相当する「関節の機能の著しい障害」とは、関節の可動域(動かせる範囲)が事故の前の半分以下になることを指します。
具体的には、以下のような症状で10級に認定された事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・そしゃく機能障害(10級2号)(東京地判 平成18年12月27日判決) ・右手関節可動域制限(10級10号)(名古屋地判 平成17年4月13日判決) ・右肩関節機能障害(10級10号)(東京地判 平成25年7月29日判決) |
1-6.後遺障害等級9級
| 第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの 2.一眼の視力が0.06以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9.一耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの 13.一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 15.一足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの |
後遺障害9級は、認定される症状の幅が広いのが特徴です。
視力の低下や聴力障害、神経障害、内臓機能の障害、指の欠損など、該当する症状は多岐にわたります。
実際、過去には以下のような症状で9級に認定された事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・口蓋部に残存している長さ5cm以上の線状痕(9級16号)(さいたま地判 平成27年4月16日判決) ・右足第1〜5指の機能障害(9級15号)(名古屋高判 平成26年11月28日判決) ・高次脳機能障害(9級)(大阪公判 平成21年3月26日判決) |
1-7.後遺障害等級8級
| 第8級 | 1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの 4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8.一上肢に偽関節を残すもの 9.一下肢に偽関節を残すもの 10.一足の足指の全部を失ったもの |
後遺障害等級8級になると、日常生活や仕事などにおいて、大きな支障をきたします。仕事を続けるのが難しくなるようなケースもあるでしょう。
複数の手指の欠損や、手足の関節の重度の障害などで認定される可能性があります。
具体的には、以下のような症状で認定された事例があるでしょう。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・右腓骨神経麻痺による右足関節の機能障害(8級7号)(名古屋高判 平成26年11月28日判決) ・脊柱運動障害(8級2号)(神戸地判 令和3年11月17日判決) |
1-8.後遺障害等級7級
| 第7級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの 7.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8.一足をリスフラン関節以上で失ったもの 9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失ったもの |
後遺障害等級7級は、片方の失明や普通の会話ができないレベルの聴力低下、手足の指の複数本の欠損などの症状で認定される等級です。
労働能力喪失率(後遺障害の影響による労働力の低下を表す割合)の基準は56%と、労働の能力が半分以下に低下していると判断されます。
高次脳機能障害などの神経障害についても、7級に認定される可能性があるでしょう。
具体的には、以下のような症状で認定された事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・びまん性脳損傷等による神経・精神の障害(7級4号)(仙台地判 平成24年12月20日判決) ・記銘力障害、笑い発作(併合7級)(東京地判 平成17年7月25日判決) ・高次機能障害(7級4号)(東京地判 平成25年6月24日判決) ・腹圧性尿失禁(7級)(金沢地判 平成29年10月26日判決) |
1-9.後遺障害等級6級
| 第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの |
後遺障害等級6級は、「著しい障害」「著しい変形」など障害の中でもより症状が重篤なものに認定される等級です。
後遺障害6級程度の症状に至ると、身体障害者手帳の交付対象にも当てはまる可能性があります。障害に対する補償を十分に受けるためにも、賠償だけではなく福祉サービスの利用も検討されてください。
具体的には、以下のような症状で6級に認定された事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・脊柱奇形(6級5号)(大阪地判 平成14年9月27日判決) ・人工肛門造設・腸壁ヘルニア(6級相当)(大阪地判 平成3年3月24日判決) |
1-10.後遺障害等級5級
| 第5級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.一上肢を手関節以上で失ったもの 5.一下肢を足関節以上で失ったもの 6.一上肢の用を全廃したもの 7.一下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの |
後遺障害等級5級は、片目の失明と視力の大幅な低下や、神経系統の障害、手足の欠損や全廃など、非常に重い障害に対して認定される等級です。
5級に相当する神経系統の障害では、仕事への影響が大きく関係します。
これまでできていた業務ができなくなり、簡単な仕事しかできなくなったという場合などは、5級に相当する可能性があるでしょう。
具体的には、以下のような症状で5級に認定された事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・高次機能障害(5級2号) ※デザイン担当嘱託社員(男・固定時45歳)で、事故後復職。デザイン能力は低下しておらず会社も能力を高く評価。しかし、記憶力や持続力の低下、協調性の問題などの人格変化によりトラブルが発生して退職。(京都地判 平成17年12月15日判決) ・記憶や注意力、学習能力、対人関係の維持能力の障害(5級2号)(岡山地倉敷支判 平成14年6月28日判決) |
1-11.後遺障害等級4級
| 第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
後遺障害等級4級は、目の障害・咀嚼や言語の障害、聴覚障害、手足の障害などで認定される等級です。
4級の認定を受ける「手指の全部の用を廃したもの」とは、手指の第一関節から先を失ったり、事故の前と比べて関節の可動域が半分以下になったりと、手を使った動作が大幅に制限される症状を指します。
4級の労働能力喪失率の基準は92%にも至るとされ、健康なときと比べて9割以上労働能力低下したと判断され得ます。
事故前と比べると大きく収入が低下することに加え、介助が必要となる可能性もあります。
具体的には、以下のような症状で4級の認定を受けた事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・高次脳機能障害、嗅覚脱失、味覚減退等(併合4級)(東京地判 平成18年4月24日判決) ・脳挫傷後の精神神経症状等(併合4級)(神戸地判 平成18年11月17日判決) |
1-12.後遺障害等級3級
| 第3級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの |
後遺障害等級3級以上の等級では、労働能力喪失率の基準が100%とされ、身体の重要機能の喪失により、今後の生活に甚大な影響が及びます。
神経系統の障害としては、月に2回以上のてんかん発作や、高次脳機能障害などで認定を受けることがあります。
咀嚼、または言語の機能を廃したものは3級と認定されますが、どちらも廃した場合には1級となります。
具体的には、以下のような症状で3級に認定された事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・右半身麻痺、失語症、注意力障害等(3級3号)(東京地判 平成27年3月26日判決) |
1-13.後遺障害等級2級
【介護を要さない場合】
| 第2級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2.両眼の視力が0.02以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
【介護を要する場合】
| 第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
後遺障害等級2級は、介護を要するものとそうでないもので症状の基準が分かれています。
両手足を失う、介護が必要になるなど、生活に与える影響は甚大です。
介護を要する場合の1級との差は、介護を必要とするタイミングが「常時」か「随時」かという部分にあります。
常に介護がないと生活ができない場合には、1級に認定される可能性があるでしょう。
2級では、以下のような症状で認定を受けた事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・高次脳機能障害、右下肢短縮障害等(併合2級)(東京地判 平成20年1月24日判決) ・PTSDを認定せず、ヒステリー症状、混合性解離性(転換性)障害(2級3号)(さいたま地判 平成15年10月10日判決) |
1-14.後遺障害等級1級
【介護を要さない場合】
| 第1級 | 1.両眼が失明したもの2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両下肢の用を全廃したもの |
【介護を要する場合】
| 第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
後遺障害等級1級も、2級と同じく介護を要する場合とそれ以外で症状の基準が分かれています。
1級は、後遺障害等級の中でも最も症状が重いものに対する等級で、両目の失明や両手足の欠損、全廃など、これまでと同じ生活をするのが非常に難しくなる状態です。
植物状態や全身まひで身体が動かせない状態なども、1級の症状に当たります。
具体的には、以下のような症状で1級の認定を受けた事例があります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| ・外傷性てんかん、運動機能障害、高次脳機能障害等(1級3号(東京地判 平成16年12月21日判決) ・脳挫傷による植物状態(1級3号)(東京地判 平成10年3月19日判決) ・四肢麻痺、膀胱直腸障害、知的レベル3歳程度等(1級3号)(大阪地判 平成16年9月10日判決) |
2.交通事故の後遺障害等級は複数の後遺障害を「併合◯級」と等級を上げて認定されることがある
前章では後遺障害等級ごとの症状を説明しましたが、交通事故では1か所だけを怪我するわけではなく、複数個所に後遺障害が残るケースもよくあります。
そのようなケースでは、「併合」というルールを使って最終的な等級が判断されます。
| 後遺障害認定を受けた数 | 併合ルール | 例 |
| 5級以上の後遺障害が2つ以上ある | 重い等級を3つ繰り上げる | 5級と4級に認定 →4級を3つ繰り上げて併合1級 |
| 8級以上の後遺障害が2つ以上ある | 重い等級を2つ繰り上げる | 8級と10級に認定 →8級を2つ繰り上げて併合6級 |
| 13級以上の後遺障害が2つ以上ある | 重い等級を1つ繰り上げる | 13級と14級に認定 →13級を1つ繰り上げて併合12級 |
| 14級の後遺障害が2つ以上ある | 14級のまま | 14級に複数認定 →併合14級 |
※同一部位に残った後遺障害を同一の系列として取り扱うなど、一部例外があります
※怪我の状況や症状などによって、個別に判断されるケースもあります
具体的には、以下のような認定の事例があります。
| 認定された症状 | 結果 | |
| ケース1 | ・腰の痛みと左下肢のしびれ(12級13号) ・首の痛み(14級9号) | 併合12級 |
| ケース2 | ・左手関節機能障害(12級6号) ・顔面部の右眉毛を横切る長さ5cm以上の縦線状痕の著しい外貌醜状(12級14号) | 併合11級 |
| ケース3 | ・高次脳機能障害(7級) ・嗅覚脱失(12級相当) | 併合6級 |
| ケース4 | ・高次脳機能障害 ・脊髄損傷後の各症状等 | 併合2級 |
このように、後遺障害等級は決まった症状をベースに認定されますが、必ずしもその通りの結果になるわけではありません。
症状の状態などによって、個別に判断されることもあるため、相手の保険会社などに「このケースでは必ず●級になります」などと言われても真に受けないようにしましょう。
3.【等級別】後遺障害が残って請求できる賠償金
ここまで、後遺障害等級の各症状や認定のルールについて説明してきました。
ご自身の症状に応じた等級の目安がわかったところで、認定を受けることで請求できる賠償金について解説していきます。
後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求できるようになります。
それぞれ、詳しく解説します。
3-1.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故による怪我で後遺障害が残った場合に請求できる、被害者の精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害慰謝料には、3つの計算基準があります。
後遺障害慰謝料は等級ごとに金額の相場が決まっています。
裁判などの判例をもとにした弁護士基準と、最低限である自賠責基準のそれぞれの等級ごとの金額は以下の通りです。
| 等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
| 第14級 | 110万円 | 32万円 |
| 第13級 | 180万円 | 57万円 |
| 第12級 | 290万円 | 94万円 |
| 第11級 | 420万円 | 136万円 |
| 第10級 | 550万円 | 190万円 |
| 第9級 | 690万円 | 249万円 |
| 第8級 | 830万円 | 331万円 |
| 第7級 | 1000万円 | 419万円 |
| 第6級 | 1180万円 | 512万円 |
| 第5級 | 1400万円 | 618万円 |
| 第4級 | 1670万円 | 737万円 |
| 第3級 | 1990万円 | 861万円 |
| 第2級 | 2370万円 | 【介護を要する場合】1203万円 【介護を要さない場合】998万円 |
| 第1級 | 2800万円 | 【介護を要する場合】1650万円 【介護を要さない場合】1150万円 |
3-2.逸失利益
逸失利益は、後遺症による影響で得られなくなってしまった収入に対する補償です。
後遺障害の等級だけではなく、被害者の年齢や収入などによっても異なります。
| 【逸失利益の計算式】 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数=後遺障害逸失利益 ・基礎収入…事故の前年の1年間の収入 ・労働能力喪失率…9級の場合35% ・ライプニッツ係数…年齢ごとに決まっている係数 【35歳/前年度の年収が450万円の場合】 450万円×35%×20.389=3211万2675円 労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数はこちら |
逸失利益が認められるのは会社員だけではなく、主婦やアルバイト、個人事業主も請求が可能な場合があります。
また、認定を受けた段階で減収がなくても認められるケースもあります。
実際の過去の認定事例としては、以下のようなものがあります。
| 過去の認定事例(裁判例) |
| 被害者(男・固定時45歳)の右下肢1センチ短縮、約30度の外旋変形(12級8号)につき、立位での荷重バランスが悪く1時間以上起立不能で、時間給のアルバイトの職にしかつくことができず事故前より収入が大幅に減収したとして、22年間20%の労働能力喪失を認めた (横浜地判平13.10.19 自保ジ1430・15) |
| 過去の認定事例(裁判例) |
| 造園業手伝い(男・固定時52歳)の右膝半月板損傷による運動・労作後の関節水症、四頭筋萎縮、右膝外側関節裂隙の圧縮(12級12号)につき、12級を超える上位等級に該当するとは直ちに言い難いものの、これまで肉体的作業に従事してきたことや収入減少の見込み等を考慮し、10年間25%の労働能力喪失を認めた (東京地判平15.9.10 自保ジ1547・6) |
逸失利益については下記の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせて参考にしてください。
【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説
4.後遺障害は必ず正当な等級に認定されるわけではない!等級変更が認められた事例5つ
交通事故の怪我で後遺障害が残ってしまい、ここまでで解説したような症状が残っていたとしても、必ず適正な認定を受けることができるわけではありません。
なぜなら、後遺障害の認定には医療的な証拠を集め、認定機関に対して症状を客観的に証明する必要があるからです。
この申請は難しく、症状が残っているにも関わらず、「非該当」や「症状に対して軽い等級の認定」になるケースも少なくありません。
そこでここからは、サリュがサポートすることで納得のできない認定を覆し、適正な後遺障害等級を獲得した事例を5つ紹介します。
| 事故のケース | 怪我の状況 | 最初の 申請結果 | 異議申立て後の結果 | |
| ケース1 | 自動車を運転中に赤信号を無視してきた相手の車と衝突 | 首や左肩の打撲、捻挫の怪我で約半年治療を続ける | 非該当 | 14級9号 |
| ケース2 | バイクを運転中に交差点で自動車と衝突 | 右橈骨遠位端骨折の診断を受け、金属で右腕を固定する手術を受け、約1年間治療を続ける | 非該当 | 12級13号 |
| ケース3 | 自動車を運転中に、飛び出してきた車両に衝突される | 頸椎捻挫などの怪我を負い、通院治療を続ける | 14級9号 | 12級13号 |
| ケース4 | 自転車で走行中、車に追突され転倒 | 第11胸椎の圧迫骨折の怪我を負い、約7か月治療を続ける | 11級7号 | 8級相当 |
| ケース5 | バイクで走行中、侵入してきた自動車と衝突し転倒 | 意識のないまま救急搬送され、頭蓋骨折、脳挫傷、鎖骨骨折等の診断。高次脳機能障害を発症し、一人では日常生活も送れない状況に | 5級 | 3級 |
4-1.後遺障害「非該当」から14級の認定を勝ち取った事例
| 事故のケース | 怪我の状況 | 最初の申請結果 | 異議申立て後の結果 |
| 自動車を運転中に赤信号を無視してきた相手の車と衝突 | 首や左肩の打撲、捻挫の怪我で約半年治療を続ける | 非該当 | 14級9号 |
最初に紹介するのは、「非該当」とされ、賠償金もわずか35万円ほどしか提示されていなかった事例です。
被害者の方は、交通事故で首や背中に痛みやしびれが残り、日常生活にも影響が出ていました。
ところが、保険会社が提出した事前認定の結果は「後遺障害に当たらない」というもので、示談案も著しく低額でした。
そこでサリュが協力し、追加検査や専門医の診断をもとに異議申し立てを行ったところ、認定機関に症状が認められ、後遺障害14級9号を獲得しました。
また、示談金も大幅にアップし、被害者の方も「ようやく症状を理解してもらえた」と納得できる形で解決に至りました。
4-2.後遺障害「非該当」から12級の認定を勝ち取った事例
| 事故のケース | 怪我の状況 | 最初の申請結果 | 異議申立て後の結果 |
| バイクを運転中に交差点で自動車と衝突 | 右橈骨遠位端骨折の診断を受け、金属で右腕を固定する手術を受け、約1年間治療を続ける | 非該当 | 12級13号 |
次に紹介するのは、手関節(手首)の骨折による後遺症が「非該当」と判断されていた事例です。
被害者の方は約1年の治療後も痛みが残り、日常生活や仕事に支障が出ているにもかかわらず、最初の申請の結果は非該当でした。
そこで、サリュが全面的に協力してカルテなどの医療的証拠を改めて確認しなおし、認定機関への異議申立てを行った結果、右手関節の痛みについて12級の認定を獲得しました。
4-3.後遺障害14級から12級の認定を勝ち取った事例
| 事故のケース | 怪我の状況 | 最初の申請結果 | 異議申立て後の結果 |
| 自動車を運転中に、飛び出してきた車両に衝突される | 頸椎捻挫などの怪我を負い、通院治療を続ける | 14級9号 | 12級13号 |
続いて紹介するのは、頸椎捻挫などの怪我で残った痛みが「14級」の認定を受けたものの、症状の強さに対して納得できなかった事例です。
被害者の方が感じる、腕や頚部の痛みは非常に強く、身体を動かす仕事に就いていた被害者にとっては仕事に与える影響も大きいものでした。
サリュでは、改めてレントゲンやMRI画像などの医療証拠を見直し、顧問医師の意見を参考にしながら、異議申立ての準備を進めました。
そして、被害者請求という形で異議申立てを行った結果、被害者の方が感じている痛みを医学的に証明し、12級13号の認定を獲得しました。
4-4.後遺障害11級から8級相当の認定を勝ち取った事例
| 事故のケース | 怪我の状況 | 最初の申請結果 | 異議申立て後の結果 |
| 自転車で走行中、車に追突され転倒 | 第11胸椎の圧迫骨折の怪我を負い、約7か月治療を続ける | 11級7号 | 8級相当 |
続いて紹介するのは、背中の強い痛みが続いたにも関わらず11級の認定を受け、納得のできなかった被害者がサリュにご相談くださった事例です。
被害者の方は症状固定後にも強い痛みが続き、もともと問題なくできていた散歩もできなくなるほどでした、
ご自身の等級が正当なものなのかが不明だった被害者の方の症状を詳しく伺い、サリュは11級では不当であると判断して異議申立てを行いました。
その結果、サリュの主張が認められて第8級相当として判断され、8級相当で計算した賠償金で示談が成立しました。
4-5.後遺障害5級から3級の認定を勝ち取った事例
| 事故のケース | 怪我の状況 | 最初の申請結果 | 異議申立て後の結果 |
| バイクで走行中、侵入してきた自動車と衝突し転倒 | 意識のないまま救急搬送され、頭蓋骨折、脳挫傷、鎖骨骨折等の診断。高次脳機能障害を発症し、一人では日常生活も送れない状況に | 5級 | 3級 |
最後の事例では、被害者の方は交通事故による影響で高次脳機能障害や動眼神経麻痺などの重い後遺症が残り、一人では日常生活を送ることすら難しくなってしまった事例です。
そんな状態の被害者の方を心配したご家族がサリュに相談にこられました。
サリュでは、高次脳機能障害の症状を説明し、どのように後遺障害診断書を書いてもらえばいいのかなどのアドバイスを行いましたが、1度目の申請は5級という結果でした。
高次脳機能障害で5級になるか、3級になるかは、4大能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続・持久力、社会行動能力)がどれだけ失われたかによって決まります。
申請では「簡易な労務であれば自立して行える」という判断を受けたため、5級になってしまったのです。
そこでサリュでは、改めて周囲の方の意見を集めて意見書を作成し、異議申立てを行いました。
その結果、このケースの高次脳機能障害は3級であると認定を受けることができました。
5.適切な後遺障害認定を受けるためにやるべきこと3つ
ここまで読んでいただいた方は、「正当な等級の認定を受けるのは難しい」ということを実感いただけたと思いますが、そこで気になるのは、「じゃあどうすればいいの?」という部分ではないでしょうか。
ここからは、納得できる結果の獲得に向けてあなたができることを具体的に3つ説明します。
| 1.申請時に医療的な証拠を十分用意する 2.後遺障害診断書を適切に作成してもらう 3.納得できないときは異議申立てする |
5-1.申請時に医療的な証拠を十分用意する
最初に重要なのが、申請時に医療的な証拠を十分用意することです。
後遺障害の認定は、客観的な医療証拠によって決定づけられる側面が大きいため、裏付けが不十分だと「非該当」とされてしまう可能性があります。
| ・レントゲンやMRIなどの画像検査の結果 ・医師の診断書や意見書 ・通院記録や投薬状況の記録 ・その他各種検査結果 など |
このような証拠を用意し、症状を客観的に証明できるようにしましょう。
申請時に納得してもらうだけの医療的な証拠を集めることが、最初のポイントです。
5-2.後遺障害診断書を適切に作成してもらう
次に、後遺障害診断書を適切に作成してもらうことがポイントとなります。
後遺障害の認定は、最終的に後遺障害診断書の内容をもとに判断されます。そのため、書き方や記載内容が適切でなければ、正当な評価を受けられない可能性が高まるでしょう。
【後遺障害診断書の提出前にできること】
| 医師に自覚症状を正確に伝える | 「違和感がある」などの漠然とした表現は避け、「首に痛みがあってデスクワークができない」など、具体的に伝える |
| 診断書に記載漏れや間違いがないか確認する | 伝えていた自覚症状や検査結果などが書かれていないと、症状を認めてもらえない可能性がある |
| 必要に応じて弁護士などに確認してもらう | 認定に必要な情報や書き方に問題がないか心配なときは、専門家に相談する |
後遺障害診断書を書くことになれていない医師の場合、十分な知識がなく記載している可能性もあります。
大切な証拠となる後遺障害診断書に不備がないよう、丁寧に確認することが重要です。
5-3.納得できないときは異議申立てする
万が一認定結果に納得できなかったときは、異議申立て(再申請)ができるということも知っておいてください。
後遺障害の認定結果は、一度出たらそれが絶対というわけではありません。
新しい証拠を用意し、申請をし直すことで、結果が変わるケースもあります。
ただし、申請に向けて有効な証拠を準備できないと、納得できる結果にならない可能性が高いでしょう。
医療証拠を集めなおしたり、医師に意見書を追加で書いてもらったり、前回以上の準備が必要になります。
再申請に向けてどうすればいいのかわからない時には、弁護士に相談すると手続きをサポートしてもらえます。
このように、一度の申請結果で諦めず、納得できる結果に向けて異議申立てをするのが最後のポイントです。
6.適正な後遺障害等級の認定には治療中から弁護士のアドバイスを受けよう
最後に、これまで2万件以上の交通事故を解決してきたサリュからお伝えしたいのは、
「後遺障害が残ったら弁護士に相談してほしい」ということです。
サリュは、つらい症状が残っているにも関わらず非該当になってしまった方や、ご自身でも原因に気が付かない後遺障害の症状に悩まされている方など、後遺障害で苦しんでいる方をたくさん見てきました。
後遺障害等級は、等級がひとつ変わるだけでも賠償金の金額が大きく変わります。
例えば、「骨折の後遺症で強い痛みが残った」という場合、認定される等級が変わると後遺障害慰謝料の金額だけで以下のような差が出ます。
| 12級 | 14級 | 非該当 |
| 290万円 | 110万円 | 0円 |
※弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場です
痛みが残っていて仕事にも生活にも影響がある中で、十分な補償が得られないと納得できないでしょう。
交通事故の後も続く生活への不利益を少しでも補償するためには、適切な認定と、適正な賠償金の獲得が必須です。
弁護士に相談すれば、申請時の準備のサポートや不備の指摘など、申請に向けて全面的に支えてもらうことができます。
不慣れな対応で疲弊するのを防ぐためにも、まずは弁護士に相談してください。
7.後遺障害等級の認定サポートはサリュにお任せください
ここまで読んできた中で、
「自分の場合はどうなるのだろう」「納得できる結果になるか心配」
そんな不安な気持ちを感じられている方は、ぜひ一度サリュにご相談ください。
私たちは、交通事故でお困りの方の力になりたいという思いを軸に、被害者の方が納得できる結果の獲得に向けて全面的なサポートを提供しています。
| 1.顧問医師によるサポートが受けられる 2.交通事故フルサポートを提供している 3.交通事故被害者に特化した解決実績が2万件以上ある |
7-1.顧問医師によるサポートが受けられる
サリュでは、法律の専門家である弁護士だけではなく、医療の専門家である顧問医師と連携したサポートを行っています。
後遺障害等級の認定には、医療的な知識が不可欠です。
顧問医師が在籍していることで、以下のようなサポートが可能になります。
| ・後遺障害診断書の作成時に医師の目線でアドバイスできる ・診断書やカルテの内容を精査し、医学的な根拠を強める ・診断書などの表現を、法的な観点と医学的な観点の両面でチェックできる |
このように、違う視点を持つ専門家が依頼者の方を両面からサポートできるのが、サリュの強みです。
7-2.交通事故フルサポートを提供している
後遺障害の認定だけではなく、治療中からフルサポートをしているのもサリュの特徴です。
弁護士事務所の中には、「症状固定後からのサポート」としているところもありますが、サリュでは事故直後や治療中からの相談も承っています。
後遺障害等級の獲得に向け、治療中から検査や通院のアドバイスを提供できるのも、サリュにご依頼いただきたい理由の1つです。
7-3.交通事故被害者に特化した解決実績が2万件以上ある
サリュでは、交通事故被害者に特化した2万件以上の解決実績があります。
これらの経験から築いた豊富なノウハウで、依頼者の方一人ひとりに合わせたサポートを提供させていただけます。
後遺障害の等級変更や逸失利益などの賠償金の交渉では、過去の判例の知識がないと被害者に不利な条件を飲まざるを得ない状況になることがあります。
そのようなケースでも、サリュは過去のノウハウや知見を活かし、被害者の方が納得できる解決に向けて交渉できるのです。
自分の症状に合った後遺障害の等級を獲得したい、納得できる賠償金を請求したいという思いがある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。
8.まとめ
この記事では、交通事故の後遺障害等級について網羅的な情報を解説しました。
▼後遺障害等級は事故による怪我によって残った後遺症により労働能力が失われたことを認定機関に認めてもらう仕組みで、症状が重いものほど小さい数字に認定され、症状ごとに1~14級に分かれている
▼後遺障害等級の認定には併合などのルールがあり、個別の事情にあわせて判断される
▼後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償を請求できる
▼適切な後遺障害等級の認定を受けるためにやるべきことは以下の3つ
| 1.申請時に医療的な証拠を十分用意する 2.後遺障害診断書を適切に作成してもらう 3.納得できないときは異議申立てする |
これらの内容を参考に、納得できる等級獲得に向けて行動してください。
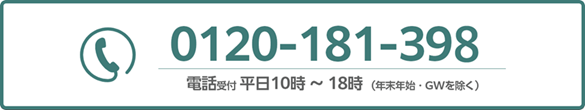

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
