後遺障害1級とは?認定される症状や賠償金について事例付きで解説
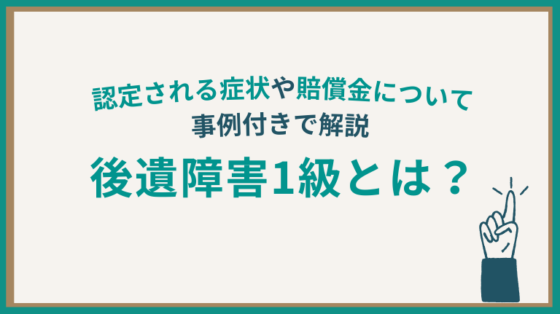
「交通事故に遭った家族に重い障害が残り、後遺障害1級に該当しそうと言われた」
「認定を受けたらどうなるのかよくわからない」
このような疑問や悩みを抱えて検索されていませんか?
後遺障害1級は、以下のような症状が残った場合に認定される可能性のある等級です。
【自動車損害賠償保障法施行令別表第1】(要介護のケース)
| 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 1級2号 | 腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
【自動車損害賠償保障法施行令別表第2】
| 1級1号 | 両眼が失明したもの |
| 1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
| 1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失つたもの |
| 1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
後遺障害1級の認定を受けることで、後遺障害に対する補償を受けられます。
後遺障害1級は、後遺障害の中でも最も重い後遺障害等級です。
このような障害が残った場合、今後の労働が難しくなったり、介護や看護が継続的に必要になったりと、将来的にも長く影響が残るため、加害者から正当な賠償を受けることが重要です。
しかし、賠償金の総額が数千万円から数億円と高額になる事故では、相手の保険会社が少しでも金額を抑えようと、不当に低い金額で計算して提示してくる可能性があります。
重い障害が残ったにも関わらず、そのような結果を迎えることがないよう、この記事では後遺障害1級の認定基準のほか、賠償金の相場や過去の獲得事例などをすべて解説していきます。
記事の内容を参考に、後遺障害等級の認定後の交渉で納得できる結果を勝ち取ってください。

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1.後遺障害1級が認定される症状
後遺障害1級は、介護が常に必要な場合とそうでない場合の2パターンに分かれます。
介護が常に必要な場合に2つの症状、そうでない場合に6つの症状で認定される可能性があります。
それぞれの症状について、詳しく解説します。
1-1.【要介護】の症状
後遺障害1級に認定される中で、常に介護が必要なものについては別表第1で以下の2つの症状が規定されています。
【自動車損害賠償保障法施行令別表第1】
| 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 1級2号 | 腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
常に介護が必要となる2つの症状について、それぞれ解説します。
| ※同じく介護が必要な場合に認定される可能性がある2級とは、介護の必要な程度によって異なります。 ・常に介護が必要な場合(自分で行動が一切できない)→1級 ・随時介護が必要な場合(食事や排泄などの一部の介護が必要となる)→2級 |
1-1-1.1級1号│神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
神経や脳に重篤な障害が残り、日常生活のあらゆる動作に介護が必要な状態になった場合、介護が必要な1級1号に該当する可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・高次脳機能障害による精神障害 ・脳損傷による身体性機能障害 ・脊髄損傷による神経の機能障害 などにより常に介護が必要になっているか |
| 認定される例 | ・高次脳機能障害のため、食事や入浴などの際に常に介護が必要になる ・高次脳機能障害による高度の認知症があり、常に監視が必要になる ・手足に高度~中等度の麻痺があり、食事や入浴などの際に常に介護が必要になる |
※高度~中等度の麻痺:障害のある腕や足の運動性・支持性がほとんど失われ、基本動作(歩く、立つ、物を持ち上げるなど)ができない、もしくはかなり制限がある状態
介護が必要な1級1号の方は、後遺障害の影響で常に介護が必要な状態であり、食事や入浴、排泄などは助けを受けなければ自力では行えません。
また、認知症などの影響で精神に影響が表れ、安全のために常に監視が必要となる場合も対象となります。
1-1-2.1級2号│胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
主に呼吸器に重度の障害が残り、生命維持のための医療的ケアや日常生活における介助を常時必要とする状態になった場合、介護が必要な1級2号に該当する可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・主に呼吸器に障害が残り、自力での食事や排泄、移動などが困難で、常に介護を必要とする |
| 認定のポイント | 血液検査や肺機能検査で以下のような条件に当てはまっているうえで、常に介護が必要な場合 ・動脈血酸素分圧(PaO2)が50Torr以下 ・動脈血酸素分圧が50Torr超〜60Torr以下で、かつ動脈血炭酸ガス分圧(PaCO2)が37Torr未満または43Torr超 ・スパイロメトリー(肺機能検査)で高度な呼吸困難が見られる |
これらは、重度の呼吸不全で認められる症状です。
このような状況では、自力での呼吸が難しく、在宅酸素療法(酸素ボンベなど)が必要になり、介護や医療的な支援が常に必要になります。
1-2.【要介護でない】症状
後遺障害1級には「常に介護が必要な状態」だけでなく、身体機能が極めて重大に損なわれた状態も含まれます。
これらは、別表2で以下のように定められています。
【自動車損害賠償保障法施行令別表第2】
| 1級1号 | 両眼が失明したもの |
| 1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
| 1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| 1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
それぞれの症状について、詳しく解説します。
1-2-1.1級1号│両眼が失明したもの
両目の視力を完全に失い、視覚による情報を得ることができない場合、1級1号に該当する可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・眼球を摘出した ・光の明暗がまったくわからない、もしくはかろうじてわかる |
| 認定のポイント | 明暗がかろうじてわかるとは、以下のようなケースです ・暗室で光の点滅がわかる ・目の前で動かした手の動きがわかる |
両目を失明すると、歩行や移動には白杖やヘルパーが必要になります。
また、文字の判読もできなくなるため、音声ガイドや点字などが必要になるケースも多いでしょう。
視覚が失われることで転倒するなどの、二次被害にも気を付ける必要があります。
1-2-2.1級2号│咀嚼及び言語の機能を廃したもの
口やあご、のどなどの重大な障害により、食べ物を噛むことも話すこともできなくなった場合、1級2号に該当する可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・スープ状の流動食しか口にできず、固形物を一切咀嚼できない ・発音に必要な子音4種のうち、3種類以上が発音できない |
| 認定のポイント | 言語機能を廃するとは、以下のうち3種類以上が発音できない場合 ・口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ) ・歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ) ・口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん) ・喉頭音(は行) |
食事については、流動食や経管栄養(胃ろうなど)を使って栄養を摂取することになります。
また、自身でコミュニケーションを取るのが難しいため、精神的なストレスを大きく感じる可能性もあるでしょう。
| 咀嚼機能と言語機能のどちらか一方のみが失われている場合は、後遺障害3級となります。 |
1-2-3.1級3号│両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両腕を肘より上の部分で失った場合、1級3号に該当する可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・両腕が事故により肘関節より上で切断された ・切断手術により、両肘以上の部位が摘出された ・壊死や感染などにより、両上腕が医療的に切除された |
両腕を失ってしまうことで、手を使った日常動作(食事や着替えなど)を自分で行うのが難しくなります。
日常的に家族や介護者のサポートが必要になる可能性もあるでしょう。
1-2-4.1級4号│両上肢の用を全廃したもの
両腕が存在していても、完全に機能を失い、まったく使えない状態の場合は1級4号に該当する可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・両腕が完全に機能を失った |
| 認定のポイント | ・肩、ひじ、手首の関節と、両手指の関節のすべてが固まって動かせない ・神経の損傷で腕が麻痺して完全に動かせない |
左右の腕・手指がまったく動かせなくなるため、1級3号と同じく日常生活には大きな影響が生じます。
1-2-5.1級5号│両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両足をひざの関節よりも上の部分で切断した場合は1級5号に該当する可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・両足が事故によりひざ関節より上で切断された ・切断手術により、両ひざ以上の部位が摘出された ・壊死や感染などにより、ひざより先が医療的に切除された |
膝関節より先を失った場合、車椅子や義足を利用して移動をすることになります。
義足は利用に訓練が必要なため、慣れるまではスムーズな移動が難しく、周囲のサポートが必須になるでしょう。
1-2-6.1級6号│両下肢の用を全廃したもの
両足が存在していても、完全に機能を失っていて歩行や立位などが不可能な状態の場合は1級6号に該当する可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・両足が完全に機能を失った |
| 認定のポイント | ・股、ひざ、足首の関節と、両足指の関節のすべてが固まって動かせない ・神経の損傷で足が麻痺して完全に動かせない |
足の機能を失っているため、歩行や立ち上がることはできず、車椅子などでの移動が必須となります。
移動だけではなく、排泄や入浴などでも介助が必要になるでしょう。
| 上記に当てはまらなくても複数の症状で併合1級に認定されるケースもある |
| 後遺障害の認定では、1つの部位に対する障害だけでなく、複数の部位に重度の障害が残った場合に「併合」という考え方が用いられます。 併合のルールは以下のとおりです。 (1)5級以上の後遺障害が2つ以上残存→重い方の等級を3つ繰り上げる (2)8級以上の後遺障害が2つ以上残存→重い方の等級を2つ繰り上げる (3)13級以上の後遺障害が2つ以上残存→重い方の等級を1つ繰り上げる このようなルールがあるため、以下のように等級が繰り上がります。 【実際の事例】以下の後遺障害を受け、併合1級を認定 ・高次脳機能障害(3級3号) ・外貌の著しい醜状(7級12号) ・鎖骨の著しい変形(12級5号) ・嗅覚脱失(12級相当) (広島高判・令和3年9月10日) |
2.後遺障害1級に認定された被害者が受け取ることができる賠償金
後遺障害1級は最も重い後遺障害等級であり、生活にも大きな影響を残す後遺障害です。
症状の説明をする中でも触れましたが、治療後も車椅子などの装具や、生活の介助が引き続き必要になるケースが多いため、将来のためにも適正な賠償金を請求する必要があります。
ここでは、適正な賠償金獲得の参考にできるよう、被害者が受け取ることができる賠償金について詳しく解説します。
以下の項目ごとに、詳細や相場を確認していきましょう。
| 1.慰謝料│精神的苦痛に対する補償 2.逸失利益│将来の減収などに対する補償 3.将来の介護費4.その他の賠償金 |
2-1.慰謝料│精神的苦痛に対する補償
慰謝料とは、交通事故によって生じた精神的苦痛に対する補償です。
慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。
それぞれ解説します。
| 慰謝料の計算基準の違い |
| 交通事故の慰謝料の計算基準には、以下の3種類があります。 このように、自賠責基準で算出された慰謝料は、最低限の金額となってしまいます。 相手の保険会社は、この自賠責基準か、それより少し高い程度の任意保険基準で計算した慰謝料を提示するケースが多いでしょう。 しかし、被害者にとって正当だといえるのは、過去の裁判例などをもとに算定される弁護士基準です。 相手の保険会社から慰謝料などの提示があったときには、その金額を過信せず、必ず計算基準などの根拠を確認することが重要です。 |
2-1-1.入通院慰謝料│入院や通院による精神的苦痛への補償
入通院慰謝料は、交通事故のけがにより、入院や通院を余儀なくされたことへの精神的苦痛に対する補償です。
弁護士基準では、入院期間・通院期間を下記の表に当てはめて計算します。
※この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合、入通院期間1か月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。
(例:16か月入院した場合=340万円+(340万円-334万円)=346万円)
上記の表に当てはめると、以下のような金額が入通院慰謝料の相場となります。
| ・15か月入院した場合→340万円 ・12か月の入院後に6か月通院した場合→337万円 |
入通院慰謝料については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。
【怪我のケースで比較】交通事故の慰謝料の弁護士基準とその他の基準の差を徹底解説
2-1-2.後遺障害慰謝料│後遺障害による精神的苦痛への補償
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛の補償です。
特に1級の場合、生活全般にわたって支障が続くことから、その精神的苦痛の大きさは相当なものと認められます。
後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
| 弁護士基準 | 自賠責基準 |
| 2800万円 | 介護を要する場合:1650万円 介護を要しない場合:1150万円 |
後遺障害1級では賠償金が高額になる傾向にあるため、保険会社はできる限り金額を抑えようと、被害者に対して不当に低い計算基準で慰謝料を計算することがあります。
相手から慰謝料を提示された際は、上記の適正な相場(弁護士基準の相場)を知ったうえで対応してください。
後遺障害慰謝料については、以下の記事の内容も参考にしてください。
後遺障害の慰謝料とは?等級ごとの相場や算定基準をわかりやすく解説
2-2.逸失利益│将来の減収などに対する補償
逸失利益とは、後遺障害の影響で仕事ができなくなってしまったり仕事に支障が生じている場合に、本来であれば得られるはずだった収入を補償するものです。
後遺障害1級では労働能力喪失率は100%、つまり、今後の働く能力が完全に失われているとみなされます。
逸失利益の計算は、以下の式に当てはめて行います。
| 1年あたりの基礎収入*×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数* *1年あたりの基礎収入…被害者が事故に遭う前の年収などから算出 *ライプニッツ係数…交通事故の損害などを計算するための係数 |
たとえば、1年あたりの基礎収入400万円、30歳の男性が1級の認定を受けた場合の逸失利益は、以下のように計算されます。
| 400万円×労働能力喪失率100%×22.167=8866万8000円 |
※実際の計算式はケースによって異なります。
逸失利益を請求できるのは、正社員だけでなく、パートやアルバイト、自営業、家族の家事を行う主婦・主夫などであっても請求が可能です。
年齢や性別ごとの後遺障害逸失利益の目安については、以下の表を参考にしてください。
各目安金額は、平均収入などをもとにした一例です。実際の金額は事例によって異なるため、詳しい金額は弁護士などにご相談ください。
【男性】
| 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 | 65歳 |
| 1億4002万 | 1億2025万 | 1億0897万 | 8180万 | 3550万 |
【女性】
| 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 | 65歳 |
| 9941万 | 8837万 | 7377万 | 5092万 | 2769万 |
| ※上記早見表では、以下を前提にしています。 【基礎収入】25歳:男性5,908,100円・女性4,194,400円 35歳:男性5,897,800円・女性4,334,500円 45歳:男性6,837,700円・女性4,629,200円 55歳:男性7,242,100円・女性4,508,600円 65歳:男性4,162,800円・女性3,246,800円 (※令和6年の全学歴、年齢別、男女別の平均収入を前提) 【労働能力喪失率】100% 【ライプニッツ係数】労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数はこちら |
こちらの計算はあくまで例となります。
また、逸失利益についての詳しい内容は以下の記事で解説していますので、こちらも参考にしてください。
【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説
2-3.将来の介護費
後遺障害1級と認定された場合、将来にわたり介護が必要となるケースが多く、介護費用も賠償の重要な対象となります。
具体的には、以下のような項目が請求の対象となります。
| ・訪問介護やデイサービスなどの介護サービス利用料 ・家族が介護する場合の日額(一般的に1日8000円) ・車椅子や義手、義足などの福祉器具の購入費用、買い替え費用 ・おむつなどの衛生用品の消耗品の購入費用 ・バリアフリー化や手すりの設置などにかかった住宅改装費用 ・介護車両の購入や改装費用 |
特に「常に介護が必要」とされる別表第1の1級1号・2号に該当する場合、24時間体制の介助や専門的な医療的ケアが求められることもあり、その負担は非常に大きなものです。
どのようなものが請求の対象になるのか知っておき、もれなく請求を行ってください。
また、過去の裁判例では被害者の訴えに応じて、以下のような項目が認められた判例もあります。
| 遷延性意識障害(1級3号)の母の介護を行うため、長女がホームヘルパー2級の資格を取ろうとして受講した研修費用7万8000円 | 札幌地判・平成13年8月23日 |
| 高次脳機能障害等の女性の父親が、被害者の通院のための運転免許の取得、自動車の購入を行った費用325万円のうち、250万円 | 東京地判・平成15年8月28日 |
| 両目を失明した被害者(1級1号)の盲導犬費用544万円 | 東京地判・昭和61年5月15日 |
| 四肢不全麻痺等(1級3号)の被害者につき、 ・エレベーター付きのマンションへの転居費用(60万円) ・マンションの室内改造費(121万円) ・車椅子から車両へ乗り降りする設備費(75万円) |
大阪地判・平成13年6月28日 |
2-4.その他の賠償金
後遺障害1級に該当するほどの重大な事故による後遺症が残った場合、慰謝料や逸失利益、介護費以外にも多くの費用が発生します。
実際に、以下のような項目は賠償の対象となります。
| 物損の損害賠償 | 車の修理費、代車やレンタカー費用、レッカー代、事故車の保管料など |
| 治療費 | 事故で受けた傷の治療に要する費用(診察料、手術費、入院費、投薬費など)。必要かつ相当とみなされる範囲で請求可能。 |
| 通院交通費 | 治療のために通院する際に発生する交通費(公共交通機関や自家用車のガソリン代など)。妥当な手段・理由があれば全額または相当分が請求対象。 |
| 装具・器具購入費 | 治療やリハビリに必要な装具や器具(松葉杖、コルセット、車椅子など)を購入する費用。将来的に必要になると考えられるものも含まれる。医師の指示や診断で必要性が認められるものが対象となる。 |
| 付添費用 | 入院・通院時に家族や看護師などが付き添うことで発生する人件費や交通費。 |
| 休業損害 | 治療や療養のために仕事を休み、得られなかった収入分に対する損害。 給与所得者は休業損害証明書、自営業者は確定申告などで証明し算定する。 詳細は以下の記事で解説 交通事故の休業損害|職業ごとの算出方法・受け取り方法など網羅解説 |
これらの費用は、事故がなければ本来かかる必要のなかった出費であり、被害者の生活を取り戻すために欠かせないものです。適切に証明し、相手方に請求することが重要です。
また、このような補償について、保険会社は請求が可能であることを十分に説明しないことも多く、被害者側が自ら気づいて申告しなければ支払われないこともあるため、注意してください。
3.後遺障害1級の認定を受けた場合の賠償金獲得事例
ここまで後遺障害1級の認定の基準や賠償金の相場を解説してきましたが、実際にどのくらいの金額になるのか想像しづらい部分もあるのではないでしょうか。
ここでは、これまで2万件以上の交通事故を解決に導いてきたサリュの事例の中から、後遺障害1級の認定を受けられた被害者の方の実際の賠償金の獲得事例を4つご紹介します。
| 【ケース1】将来の介護費用や住宅改装費用を含めた2億4500万円を獲得した事例 【ケース2】脳梗塞が交通事故によるものだと証明し約7000万円を獲得した事例 【ケース3】自由診療での将来治療費を認めさせ約8800万円を獲得した事例 【ケース4】将来介護費を含め約1億9000万円を獲得した事例 |
3-1.【ケース1】将来の介護費用や住宅改装費用を含めた2億4500万円を獲得した事例
| 事故・怪我の状況 | 対向車線の乗用車と衝突し、衝突時の衝撃で車外へ放り出され頚髄損傷の傷害を負う。 |
| 認定を受けた症状 | 四肢体幹機能障害、感覚障害、膀胱直腸障害等の症状が残存し、別表第一の1級1号に認定 |
| 獲得金額 | 介護関係費用、住宅改築費用等を含む約2億4500万円 |
この事故では、被害者は頚髄損傷の怪我を負い、四肢体幹機能障害、感覚障害、膀胱直腸障害という重い障害が残りました。
交渉時に主な争点となったのは、介護関係費用や住宅改築費用(リフォームなどにかかる費用)がどこまで認められるかです。
サリュでは、被害者本人やご家族に丁寧に聞き取りを行い、今後必要となる金額を算定して相手方へ請求。サリュの交渉の結果、最終的に約2億4500万円という金額で示談が成立しました。
3-2.【ケース2】脳梗塞が交通事故によるものだと証明し約7000万円を獲得した事例
| 事故・怪我の状況 | 運転中に、よそ見をしていた対向右折車が衝突。 全身打撲、頭部打撲、肋骨骨折等の重傷を負い、救急搬送される。当初は脳挫傷(外傷によって脳が損傷すること)と診断を受けていたものの、脳梗塞に診断が変更 |
| 認定を受けた症状 | 脳梗塞により1級の認定 |
| 獲得金額 | 約7000万円 |
こちらのケースでは、被害者は当初「脳挫傷」という診断を受け、治療やリハビリを継続していました。
しかし、通院中から「脳挫傷」ではなく、「脳梗塞」に診断が変わっていたのです。
これにより、相手の保険会社は「交通事故の直前に脳梗塞になり、交通事故を引き起こしたのではないか」と考え始めました。
そこでサリュでは、医師面談を繰り返し、「当初は脳挫傷と判断したが、経過観察するうちに脳梗塞であることがわかった」という経過を証明。交通事故によって脳梗塞が引き起こされた珍しいケースであるという医学的意見書を作成し、後遺障害1級の認定を獲得しました。
これらの証拠をもとに、将来の介護費用についても自由診療をベースにした額で交渉。総額約7000万円という金額で示談が成立しました。
3-3.【ケース3】自由診療での将来治療費を認めさせ約8800万円を獲得した事例
| 事故・怪我の状況 | 軽トラックで走行中に加害車両と出合い頭に衝突。 右大腿骨解放骨折、左下腿骨開放性骨折、右下腿骨折、両側多発骨折、低酸素脳症、脳梗塞等の重傷を負う |
| 認定を受けた症状 | 遷延性意識障害が残り、後遺障害1級に認定 |
| 獲得金額 | 約8800万円 |
こちらのケースでは、被害者が軽トラックで走行中、加害車両と衝突して右大腿骨解放骨折、左下腿骨開放性骨折、右下腿骨折、両側多発骨折、低酸素脳症、脳梗塞などの大きな怪我を負いました。
被害者には遷延性意識障害が残り、後遺障害1級に認定されましたが、そんな被害者に対して保険会社が提示してきた示談金は約3300万円でした。
そこで、その金額が適正なのか不安に思ったご家族がサリュに相談。サリュが示談案を検討したところ、相手の提示する金額は将来の治療費を健康保険適用で計算した金額であり、本来受けられる賠償に対して低額になっている可能性があることが判明しました。
サリュでは自由診療を前提とした計算を行った金額で保険会社と交渉。過去の類似の裁判例などを提示し、粘り強い交渉を行ったことで、総額約8800万円の示談金を獲得しました。
3-4.【ケース4】将来介護費を含め約1億9000万円を獲得した事例
| 事故・怪我の状況 | 小学生である被害者が道路を横断中、加害車両が衝突。 外傷性くも膜下出血、広範囲脳挫傷、左上腕骨骨折、右下肢骨折等の重傷を負う |
| 認定を受けた症状 | 高次脳機能障害による嚥下障害、構音障害、排泄機能障害、四肢体幹失調等が残存し、後遺障害1級1号に認定 |
| 獲得金額 | 約1億9000万円 |
このケースは、小学生である被害者が道路を横断中、加害車両が衝突。外傷性くも膜下出血、広範囲脳挫傷、左上腕骨骨折、右下肢骨折等の重傷を負いました。
高次脳機能障害により重篤な後遺障害が残った被害者は後遺障害1級1号の認定を受け、相手方の保険会社からは8000万円強の賠償案が提示されました。
その金額が妥当なのか不安のあったご家族に相談いただき、サリュでは示談の内容を再検討。
その後、適正な金額を求めて訴訟を提起しました。
主な争点となったのは、被害者の将来介護費についてです。
訴訟では実際の介護状況や将来の介護の必要性を粘り強く主張立証した結果、裁判所からは約7800万円の将来介護費を認める和解案が提示されました。
また、その他の部分についても大幅に増額し、約1億9000万円で解決しました。
4.後遺障害1級に該当する症状が残った場合に受けられるその他の支援
後遺障害1級に認定されるような重度の障害が残った場合には、損害賠償だけでなく、公的制度による支援を受けられる可能性があります。これらの制度は、経済的な負担を軽減し、生活を維持するための重要な支えとなります。
ここでは、主に利用できる可能性のある4つの制度について解説します。
4-1.障害者手帳の交付
後遺障害1級に該当する方は、多くの場合、障害者手帳(身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳など)の交付対象となります。
具体的な等級は障害の内容や程度によって異なりますが、重度の障害であれば1級または2級に該当する可能性があるでしょう。
※後遺障害等級とは異なる身体障害者手帳の等級です。
| 申請先 | お住まいの市町村の障害者福祉担当窓口 |
| 必要なもの | 医師の診断書・意見書、障害を証明するものなど |
| 受けられる支援 | ・所得税や住民税の控除 ・公共交通機関の運賃割引 ・医療費助成 ・福祉用具の給付や貸与 ・住宅改修費の助成 など |
4-2.障害年金
重度の後遺障害が残った場合、障害年金(国民年金または厚生年金)を受給できる可能性があります。
障害年金は、障害の重度に応じて等級に分類し、その等級ごとに決まった金額が支払われます。
この障害年金の等級は、後遺障害の等級とは別に判断されるものです。
「後遺障害1級だから障害年金も1級」というわけではありませんので、注意してください。
【障害基礎年金】
| 障害の程度1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない |
| 障害の程度2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない |
障害年金の年金額は、加入している年金が「国民年金」か「厚生年金」かによって異なります。
ここでは、国民年金の場合の金額の例を紹介します。
【障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)】
1級
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 1,039,625円 + 子の加算額※ |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,036,625円 + 子の加算額※ |
2級
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 831,700円 + 子の加算額※ |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 829,300円 + 子の加算額※ |
※子の加算額
| 2人まで | 1人につき239,300円 |
| 3人目以降 | 1人につき79,800円 |
子の有無によって異なりますが、月額約7万円〜10万円程度の支給となります。
厚生年金に加入していた場合は、上記に追加して報酬比例分(収入に応じた金額)が追加されるイメージです。
4-3.労災保険(業務中や通勤途中の事故の場合)
事故が仕事中や通勤途中に発生したものであれば、労災保険の対象となります。
労災保険では、以下のような項目が請求可能となります。
| 療養補償給付 | 勤務中・通勤中の負傷または疾病で、療養を必要とする場合にもらえる給付 |
| 休業補償給付 | 勤務中・通勤中の負傷または疾病が原因で、働けなくなり、賃金を得ることができなかった場合(または減額された場合)にもらえる給付 |
| 障害補償給付 | 勤務中・通勤中の負傷または疾病が治癒した後に、一定の障害が残った場合にもらえる給付 |
| 傷病補償等年金 | 勤務中・通勤中の疾病が1年6カ月を経過しても治癒せず、その程度が「傷病等級」に該当する場合に支給 |
| 介護補償給付 | 障害補償年金または傷病補償年金受給者のうち、特定の状態に該当し、介護を受けている場合に支給される給付 |
労災保険と任意保険(自賠責保険)は併用可能です。
労災保険については以下の記事で詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。
4-4.その他
その他、重度の障害が残ってしまった場合には、以下のような福祉サービスや給付を受けられる可能性があります。
【各自治体の福祉サービス】
| 申請先 | お住まいの市町村の障害者福祉担当窓口など |
| 受けられる支援 | ・訪問介護や介護施設の利用料の給付 ・障害の重度に応じた手当 など |
※自治体によって受けられる支援の内容や金額は異なります
【ナスバによる介護料の支給】
| 申請先 | 独立行政法人自動車事故対策機構 ナスバ 各支部 |
ナスバとは独立行政法人自動車事故対策機構の略称で、自動車事故の防止や被害者の支援を行っている機関です。
ナスバでは、交通事故によって要介護になった場合、以下のような給付を受けられます。
| 最重度 特1種 | 月額85,310 円(下限額)~211,530 円(上限額) |
| 常時要介護 1種 | 月額72,990 円(下限額)~166,950 円(上限額) |
| 随時要介護 2種 | 月額36,500 円(下限額)~83,480 円(上限額) |
※労災保険の介護給付等との併給は不可
特に介護が必要なケースでは出費が続き、経済的な負担となることも考えられます。
利用できる制度がないか、地域の障害者福祉担当窓口などで確認してください。
5.後遺障害1級という重度の障害でも、保険会社は巧妙に賠償金額を抑えてくることがある
ここまで、後遺障害1級に認定される症状や賠償金の相場についてお伝えしてきました。
労働能力が完全に失われる非常に重い障害であり、将来的な補償も十分に必要なことがわかっていただけたのではないでしょうか。
しかし、このように重い障害が残ってしまったのにも関わらず、保険会社は適正な金額を提示してくるとは限りません。
むしろ、賠償金の総額が高額になる後遺障害1級のようなケースでは、意図的に金額を低く見積もろうとしてくることも多いのです。
保険会社は、以下のような手口で賠償金額を低く抑えようとします。
| ・将来の介護費用を十分に見積もらない ・逸失利益などを不当に低く計算する ・余命を少なく見積もって計算する |
実際に、過去の裁判例では被害者の後遺障害が重篤であることを理由に、余命を不当に低く見積もって賠償金を計算したことが争点となったものがあります。
| 被害者 | 小学生(男・8歳) |
| 後遺障害の内容 | 遷延性意識障害、四肢の運動麻痺など(1級3号) |
| 加害者側の言い分 | 「生存可能年数を相当範囲に限定すべき」→重い障害のため、平均余命よりも短く計算 |
| 裁判の結果 | 被告主張を斥けて、8歳男性の平均余命と認定し、18歳から67歳まで100%の労働能力喪失を認める |
(大阪地判・平成13年9月10日)
裁判の結果、加害者側の主張は排斥され、平均余命が認定されましたが、このように相手は可能な限り低い金額で済ませるためにさまざまな手法を使ってきます。
「保険会社が提示してくるということは適正な金額なのだろう」
そう思ってしまうかもしれませんが、その認識では不当な金額に気が付かないまま交渉を進められてしまうリスクがあることを知っておいてください。
6.後遺障害1級における適正な賠償金獲得に向けて弁護士が力になれる
後遺障害1級の適正な賠償金を獲得するために、まずは弁護士へ相談するようにしてください。
前章で述べたとおり、保険会社はあらゆる手段を用いて、介護費や逸失利益を過小評価し、本来支払うべき金額をできるだけ抑えようとしてきます。
相手方が専門知識を駆使して主張してくるなかで、被害者側が自力で対抗するのは非常に難しいのが実情です。
このときに被害者側の立場に立って、保険会社と対等に戦ってくれるのが弁護士です。
弁護士へ依頼すると、以下のような部分でサポートを受けられます。
| ・相手が提示する金額を精査し、不当に低い場合は根拠を持って反論する ・将来の介護費や逸失利益など、不当に低く見積もられやすい項目もきちんと算定する ・相手との交渉で必要な証拠を不足なく集める |
特に、ご家族の介護や生活支援をしながら、こうした法的対応まで行うのは時間的にも精神的にも大きな負担になります。
しかし、十分な準備や反論ができなければ、本来受け取れるはずの賠償金を不当に低く抑えられてしまうリスクがあります。
安心してご家族のサポートに専念するためにも、できるだけ早い段階で、信頼できる弁護士に相談することを強くおすすめします。
7.ご家族が「後遺障害1級の認定を受けるかも」そんな時はサリュにご相談ください
後遺障害1級に該当するような重大な事故に遭われた場合、ご家族は介護や看病に大きな労力が必要になります。
保険会社との交渉や後遺障害の認定などもご本人に代わって行うことになりますが、介護や看病の合間にそれらをこなすのは非常に大変でしょう。
そこで、少しでもご家族の負担を軽減するため、まずはサリュにご相談ください。
ご依頼いただいた場合、将来の心配なく事故解決を迎えられるよう、サリュが全力でサポートいたします。
後遺障害1級の認定を受けた、受けそうだという被害者のご家族がサリュを選んでいただきたい理由は、大きく以下の3つです。
| 1.被害に対して適正な賠償金を算定できる 2.相手の保険会社に負けない交渉力 3.事故解決まで被害者とご家族をフルサポート |
7-1.被害に対して適正な賠償金を算定できる
1つ目の理由は、被害に対して適正な賠償金を算定できるからです。
後遺障害1級に該当するような大きな事故の場合、賠償金の額が数千万円から億単位になることもあります。だからこそ、適正な金額を正確に算定できるかどうかが極めて重要です。
しかし、前章でもお伝えしたとおり、相手の保険会社はできるだけ支払いを抑えるために、不当に低い金額を提示してくることがあります。
賠償金の計算に必要な項目を一部しか含めていなかったり、介護費や逸失利益などを過小評価したりすることも珍しくありません。
実際にサリュが手がけた事例でも、保険会社の提示した賠償金から本来支払われるべき費目が漏れていたために、大幅に金額が低く見積もられていたケースがありました。
そのようなケースでは、改めて賠償金を算定しなおし、法的根拠をもって適正な金額まで増額してきました。
このように、専門的な判断により被害に見合う正当な補償を算定できるのが、サリュの強みです。
7-2.相手の保険会社に負けない交渉力
2つ目の理由は、相手の保険会社に負けない交渉力があるからです。
重い障害が残った場合、保険会社との交渉は、単なる事務的なやりとりでは済みません。金額や補償範囲など、複雑で専門的な論点をひとつずつクリアにしていく必要があります。
しかし、相手の保険会社はこうした交渉のプロです。被害者やご家族に知識がないことを逆手にとり、自社に有利な条件で交渉を進めてくることも少なくありません。
弁護士が介入しなければ不当な条件を飲まされていた事例も、サリュでは多数見てきました。
サリュの創業者である谷は元損保顧問弁護士であり、その知見から保険会社との交渉ノウハウも豊富に持っています。
その知見を活かして相手の保険会社と粘り強く交渉できるのもサリュの大きな強みです。
7-3.事故解決まで被害者とご家族をフルサポート
最後の理由は、被害者とご家族をフルサポートする体制が整っていることです。
後遺障害1級の認定が見込まれるような事故では、ご本人はもちろん、ご家族の負担も非常に大きくなります。毎日の介護や病院の付き添い、保険会社とのやりとりまで、抱える負担はとても大きなものです。
だからこそ、交通事故の被害者に寄り添い、解決まで伴走できる弁護士事務所を選ぶことが重要です。
サリュは交通事故の被害者専門の弁護士法人として、制度や手続きの支援はもちろん、医療機関との連携、家族へのフォローなど、被害者とご家族にとって本当に必要なサポートを徹底しています。
法律相談だけでなく事故解決までのすべてをサポートできる体制が整っていることが、私たちの強みです。
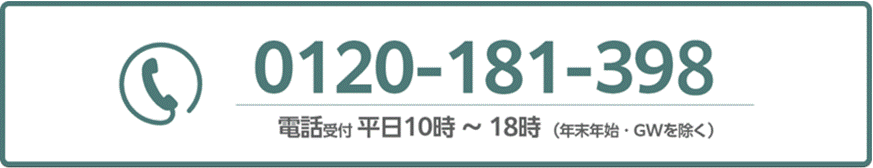
メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。
8.まとめ
この記事では、後遺障害1級について解説しました。
内容のまとめは以下のとおりです。
▼後遺障害1級は、以下のような症状が残った場合に認定される可能性のある等級
【要介護】の場合
| 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 1級2号 | 腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
【要介護でない】場合
| 1級1号 | 両眼が失明したもの |
| 1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
| 1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失つたもの |
| 1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
▼後遺障害1級に認定された場合に受け取ることができる賠償金は以下のとおり
▼加害者からの賠償の他、障害者手帳の交付や障害年金、労災保険などの給付を受けられる可能性がある
▼適正な賠償の獲得のためには、弁護士への相談・依頼が重要
これらの内容を参考にして、適正な後遺障害の認定と賠償金獲得に向けて行動してください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
