巻き込み事故で搬送│残る後遺症や今後の対応を解説
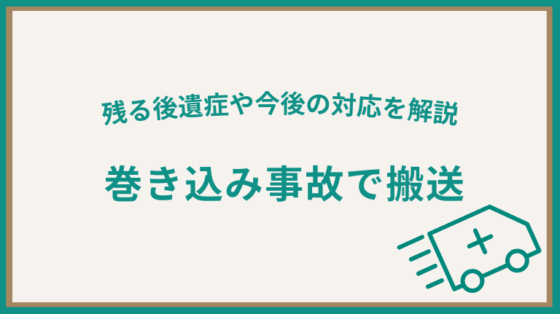
「大切な家族が巻き込み事故にあったと連絡があったけど、これからどうすればいいんだろう」
突然「家族が巻き込み事故にあった」と聞いたら、衝撃を受けてパニックになってしまうのではないでしょうか。
巻き込み事故とは、車が左折するときに直進していたバイクや自転車が巻き込まれてしまう交通事故のことです。
打撲や骨折などの軽い怪我で済めば、数日~数か月程度の通院で済みます。
しかし、双方スピードが出ているような巻き込み事故では、下記のような怪我を負う可能性もあります。
| ・複雑骨折 ・複数個所の骨折 ・頭部の怪我(脳挫傷、頭がい骨骨折など) ・内臓損傷 |
このような怪我をした場合、重度の障害が残ることや最悪の場合には命を失うことも考えられるでしょう。
大切なのは、巻き込み事故で家族が大きな怪我をした場合、すぐに弁護士に相談することです。
私たちサリュではこれまで、交通事故により被害者が亡くなったり、重度の後遺症が残ってしまったりする事例を数多く見てきました。
そのような事故では、交渉は加害者側の保険会社主導で進み、相手の言い分のみをもとに事実認定されがちです。
「加害者に都合のいい意見が通って、悪くないはずの家族に過失があることにされた」
「重度の障害が残って介護が必要なのに、相手から十分な補償がもらえない」
そのような事態を防ぐためには、弁護士のサポートが必要です。
この記事を読み、今すぐが難しくても、病院や保険会社とのやりとりが落ち着いたタイミングで弁護士に相談してください。
まずは、この記事では「今すぐ」やるべきことを解説します。
「もっと自分にできることがあったかもしれない」
「あのとき、あの情報を知っていれば…」
そんな後悔をしないためにも、記事を参考に悔いのない行動をとってください。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢
弁護士法人サリュ
大阪弁護士会
交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得
目次
1.大切なご家族が巻き込み事故にあったらあなたがやること4つ
大切なご家族が巻き込み事故に遭ってしまったら、混乱して何をすればいいのかわからなくなってしまうでしょう。
まずあなたがやることは、上記リストのとおりです。
それぞれ、詳しく知りたい方に向けて解説します。
1-1.病院に連絡し、怪我の状態を確認する
まず優先して行うことは、病院に連絡し、被害に遭われた方の怪我の状態を確認することです。
可能であれば、できるだけ早く病院を訪れるようにしましょう。
【病院へ行く際の持ち物】
| ・身分証明書…家族であることを証明するのに使う可能性がある ・ノートやメモ帳、筆記用具…医師や看護師などの話をメモするのに使う ・被害者本人の保険証やお薬手帳…身分証明や過去の既往症・服薬歴などを説明するのに使う ※準備しておくと役に立つ可能性が高いですが、急いでいる場合は無理に揃える必要はありません |
病院についたら、担当の医師や看護師から怪我の程度や治療方針などについて説明を受けます。
後で他のご家族に説明をしたり、保険会社に伝えたりするのに必要になるため、可能であればノートなどを持ち込み、メモをとっておくようにしましょう。
交通事故などでの緊急時には、病院の状況によっては手術室の空きがなかったり、担当医が不在であったりして、病院の対応が遅れる可能性があります。
そのような事情も踏まえ、病院へ行ってから帰るまでは時間がかかる(泊まり込みになる可能性もある)ことを想定しておいてください。
1-2.職場や他の家族に連絡する
病院である程度状況を確認したら、必要な相手へ連絡しましょう。
| 被害者本人の職場 | 被害者本人の職場へ連絡し、事故や怪我の状況と仕事を休む必要があることを伝える。この先のやりとりのため、被害者の治療中に連絡のつきやすい連絡先を伝えておく。 |
| あなたの職場 | 付添いなどであなた自身にも休みが必要になる場合、あなたの職場にも連絡する。介護休暇などが使える可能性があるので、余裕があれば確認する。 【介護休暇】家族の介護が必要な場合に取得できる休暇 参考:厚生労働省「介護休暇について」 |
| 家族 | あなたに代表として連絡が来ている場合、他の家族にも連絡して状況を伝える(病院によっては同時にお見舞いに来られる人数に制限があることがあるので注意)。 家族の他に、パートナーや親しい友人など知らせておくべき相手がいればその方にも連絡する。 |
病院からしばらく帰れない可能性があるため、お子さんがいる場合などは面倒を見てくれる方に頼むなど、ご自身の生活についても対応が必要です。
1-3.被害者の代わりに相手の保険会社とやりとりする
被害者に意識がなかったり、自身で連絡が取れる状況ではなかったりする場合、被害者の代わりに相手の保険会社とやりとりをします。
交通事故後、当日中~3日程度で保険会社から連絡がくるのが一般的です。
連絡が来たら、以下の情報を伝えましょう。
| ・被害者本人との続柄(親子、配偶者など) ・被害者の怪我の状況、治療状況 ・入院している病院の情報 |
保険会社からその後の対応について案内されるので、必要書類の受け取りなどは案内に従って行ってください。
1-4.事故の証拠を可能な限り集める
必要な連絡を一通り終えたら、事故の証拠を可能な限り集めておきましょう。
このあと詳しく説明しますが、巻き込み事故で被害者の意識や記憶がない場合、被害者が実況見分などに立ち会えず、加害者に有利な証言のみが残ってしまう可能性があるからです。
| ・病院で聞いた怪我の状況や手術の内容(時系列順でメモをとっておくと後からわかりやすい) ・搬送されてきたときの状態 ・事故のあった当日の天気、時間、明るさなど |
これらの情報は、できる限り残しておいてください。
また、もしも可能な場合、以下のような情報も集めておけるとよいでしょう。
| ・事故現場や事故車両などの写真 ・事故の目撃者や通報者の証言、連絡先 |
事故直後からここまで行動するのは難しいかもしれませんが、できる部分だけでも記録しておくと、後で役に立ちます。
2.巻き込み事故にあった方に残る可能性のある後遺症や死亡リスク
車や大型車両との接触による巻き込み事故では、被害者が命に関わる重傷を負う可能性もあります。
特に、救急車で搬送されて緊急手術が必要になるようなケースでは、そのリスクも高まってしまうでしょう。
また、命の危機は脱しても、身体に重度の障害が残ってしまうこともあります。
そんな巻き込み事故による死亡リスクと後遺症について、詳しく解説します。
2-1.死亡リスク
令和6年の統計では、交通事故に遭った方が亡くなるケースは1%未満です。
しかし、頭部や胸部に強い衝撃を受けた場合、死亡リスクが高いと言われています。
| 頭部の怪我の例 | 胸部の怪我の例 |
| ・頭がい骨の骨折 ・脳挫傷による出血(脳内出血、くも膜下出血など) ・脳震盪 など |
・肺挫傷(肺の組織の損傷) ・肋骨の骨折 ・心臓の損傷 ・大動脈の損傷 など |
交通事故で亡くなった人の中で、頭部を怪我した人が37.4%、胸部損傷の方が27.1%というデータがあり、他の部位の損傷と比較して命に関わる可能性が高い怪我です。
参考:警察庁 道路の交通に関する統計
これらの怪我を負っている場合や、複数個所の怪我がある場合などは、死亡リスクがあることを知っておいてください。
2-2.後遺症
重度の怪我を負っていた場合、命の危機を脱してもさまざまな後遺症が残る可能性があります。
交通事故で考えられる後遺症には、以下のようなものがあります。
| 高次脳機能障害 | 記憶力や注意力、判断力、感情のコントロールなどが上手くできなくなる状態 |
| 遷延性意識障害 | 脳に損傷が残り、意識が戻らない状態。寝たきりや植物状態。 |
| 身体の麻痺 | 脳や脊髄の損傷の影響で、身体が動かせなくなる状態。半身不随や全身まひなどになる可能性もある。 |
| 内臓機能の障害 | 呼吸器や消化器などに障害が残った状態。呼吸や排泄、食事などが自力でできなくなる可能性がある。 |
残った後遺症が重度の場合、長期間にわたる介護や介助が必要になる可能性があります。
このような場合には、後遺障害等級の認定(後遺症により日常生活などに影響が残っていることを認定機関に認めてもらうこと)を受けることで、後遺症に対する慰謝料や将来の収入補償、介護にかかる費用を加害者に請求できるようになります。
3.巻き込み事故で受け取れる可能性のある慰謝料などの賠償金
大切な人が巻き込み事故に遭ってしまった状況で、お金のことを考えるのは難しいかもしれません。
ですが、長期の入院や手術、介助が必要な怪我を負ってしまった場合、先のことを考えると、受け取ることができるお金について知っておくことが大切です。
今すぐに理解するのは難しいと思うので、このような内容について請求できるということだけ押さえておいてください。
以下に、特に役に立つ記事についてもリンクをまとめるので、こちらも余裕があるときに確認してみてください。
| ・仕事などを休んだ時に受けられる休業損害について 交通事故の休業損害|職業ごとの算出方法・受け取り方法など網羅解説 ・入院や通院に対する慰謝料について 【怪我のケースで比較】交通事故の慰謝料の弁護士基準とその他の基準の差を徹底解説 ・後遺障害等級の認定(怪我による後遺症が仕事や生活に影響があると認定を受けること)で請求できる慰謝料について 交通事故の後遺障害慰謝料の相場や計算方法・賢いもらい方とは? ・逸失利益(後遺障害によって減った収入などへの補償)について 【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説 ・被害者が事故で亡くなってしまった場合の慰謝料について 自賠責の死亡事故賠償金は一律3000万円ではない!実際の相場解説 |
【怪我の補償】
| 治療費 | 事故で受けた怪我の治療に要する費用(診察料、手術費、入院費、薬剤費など)。必要かつ相当とみなされる範囲で請求可能。 |
| 通院交通費 | 治療のために通院する際に発生する交通費(公共交通機関や自家用車のガソリン代など)。 妥当な手段・理由があれば全額または相当分が補償対象。 |
| 装具・器具購入費 | 治療やリハビリに必要な装具や器具(松葉杖、コルセット、車椅子など)の費用。医師の指示や診断で必要性が認められるものが対象となる。 |
| 付添費用 | 入院・通院時に家族が付き添った際のその家族の休業補償や交通費。付き添いに医師の指示があれば補償される。 |
| 将来介護費 | 重度の後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になった場合の介護費。医療証拠や専門家の意見をもとに必要性を立証できれば補償される。 |
| 休業損害 | 治療や療養のために仕事を休んだことで得られなかった収入分の損害。給与所得者は休業損害証明書、自営業者は確定申告書などで証明する。 詳細は以下の記事で解説 交通事故の休業損害|職業ごとの算出方法・受け取り方法など網羅解説 |
| 入通院慰謝料 | 入院・通院に伴う精神的苦痛の補償。治療期間や通院実績などを考慮して算定される。 詳細は以下の記事で解説 【怪我のケースで比較】交通事故の慰謝料の弁護士基準とその他の基準の差を徹底解説 |
【後遺障害が残った場合の補償】
| 後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛の補償。後遺障害等級に応じて補償額が決まる。 詳細は以下の記事で解説 交通事故の後遺障害慰謝料の相場や計算方法・賢いもらい方とは? |
| 逸失利益 | 後遺障害の影響で労働能力が低下・喪失したことで将来得られなくなる収入分の損害。年齢や後遺障害等級、収入実績などを基に算定する。 詳細は以下の記事で解説 【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説 |
【被害者が亡くなった場合の補償】
| 死亡慰謝料 | 被害者が死亡したことに伴う精神的苦痛の補償(被害者本人の苦痛と遺族の苦痛)。被害者の家庭内での立場などで金額が決まる。 詳細は以下の記事で解説 自賠責の死亡事故賠償金は一律3000万円ではない!実際の相場解説 |
4.巻き込み事故にあって後に問題になるのが「過失割合」
交通事故には「過失割合」という考え方があります。これは、事故の原因について、当事者それぞれにどれだけ責任があるのかを割合で示したものです。
巻き込み事故では、この過失割合が後ほどトラブルになる可能性が高いです。
過失割合が変わると受け取れる賠償金の金額も変わってしまいます。
【損害額1000万円の場合】
| 過失割合(相手:あなた) | 受け取れる賠償額 |
| 10:0 | 100%→1000万円 |
| 9:1 | 90%→900万円 |
| 5:5 | 50%→500万円 |
このように、支払う金額が大きく変わってしまうことから、加害者側(保険会社)はできる限り加害者の過失を小さく提案してくる傾向にあります。
特に、被害者が事故の直後に意識がなかった場合、事故当時の証言をすることができず、加害者側の一方的な証言が通ってしまう可能性があるので注意が必要です。
例えば、本来は被害者に過失がない事故であっても、
「被害者がスピード違反をして突っ込んできた」
などと証言された場合、それがそのまま認められてしまうかもしれません。
過失割合に関する知識がないと、相手の不当な主張に気が付かず、被害者にとって不利な過失割合を受け入れてしまう可能性があります。
そのような事態を防ぐためにも、過失割合に関する正しい知識を身に付けておきましょう。
5.巻き込み事故の過失割合は自動車:バイク「8:2」
前項でお伝えしたとおり、巻き込み事故では過失割合が重要な争点となりがちです。
まず、巻き込み事故の基本的な過失割合ですが、典型的なケースの過失割合は次のとおりです。
| 自動車とバイクの基本過失割合は8:2 | 自動車と自転車の基本過失割合は90:10 | 自動車と歩行者の基本の過失割合は100:0 |
| ・前方左折車が後方から直進してきたバイクと衝突した場合 ・車が十分左に寄っていないことや後方確認不足があることで車の過失が大きくなる |
・前方左折車あるいは前方左折バイクが後方から直進してきた自転車と衝突した場合 ・自転車は車やバイクよりも交通弱者と扱われるため、自動車やバイクの過失がより大きくなる |
・横断歩道を青信号で歩行中に青信号に従って右左折してきた車と衝突した場合 ・歩行者は信号を守って横断しており、過失はない |
基本の過失割合はこのようになっていますが、事故の状況によって修正要素(過失が変更する事情)があり得ます。
例えばバイクと車の事故の場合、以下のような修正要素があります。
それぞれ、当てはまる項目があった場合には過失が追加されます。
| バイクの過失が加算される修正要素 | |
| バイクの著しい前方不注視 | +10 |
| バイクの15km以上の速度違反 | +10 |
| バイクの30km以上の速度違反 | +20 |
| バイクのその他の著しい過失※ | +10 |
| バイクのその他の重過失※ | +20 |
| 車に加算される修正要素 | |
| 自動車の大回り左折・進入路鋭角 | +10 |
| 自動車の合図遅れ | +5 |
| 自動車の合図なし | +10 |
| 自動車の直近左折 | +10 |
| 自動車の徐行なし | +10 |
| 自動車のその他の著しい過失※ | +10 |
| 自動車の重過失※ | +20 |
| ※著しい過失(運転者に著しい落ち度があった) ・脇見運転などの著しい前方不注意 ・ハンドル・ブレーキの操作が著しく不適切であった ・携帯電話の使用や画面を見ながらの運転 ・ナビの操作や画面を見ながらの運転 ・酒気帯び運転 ・バイクのノーヘルメットでの運転 ※重過失(故意と同等の過失があった) ・飲酒運転 ・居眠り運転 ・無免許運転 ・薬物などを使用しての運転 |
このような修正要素があるため、相手はスピード違反やながら運転などの過失を意図的に隠したり、逆に被害者の過失を捏造したりすることで、不当な過失割合になってしまう危険性があるのです。
過失割合については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。
交通事故の過失割合とは?基本の割合や決め方、不満なときの対処法
6.巻き込み事故は加害者の意見が通りやすい│弁護士に依頼して相手の不当な訴えを覆した事例
前章で解説した過失割合だけではなく、巻き込み事故では加害者側が不当な主張を押し付けてくる事例が多々あります。
そのようなケースでは、被害者が知識を持って戦わないと十分な補償が得られなくなってしまいます。
ここでは、加害者側の不当な主張に対し、被害者が弁護士に依頼することで納得のいく結果になった事例を3つ紹介します。
| 事故のケース | 怪我の内容 | 後遺障害等級 | 獲得した賠償金 | |
| 事例1 | 歩いて交差点を左折しようしていたところ、右側から右折進行してきた原付自転車と衝突 | 右脛骨遠位端骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫 | 右足関節の可動域制限で10級11号 | 約2000万円 |
| 事例2 | バイクで走行中、ブレーキをかける暇もなく、隣の車線を走行していた乗用車が左折するのに巻き込まれる | 右股関節脱臼骨折 | 股関節の可動域制限で10級11号 | ─ |
| 事例3 | 自転車で横断歩道を渡っている時に、右折してきた乗用車にはねられる | 翌日に死亡 | ─ | 保険会社の提示額から1100万円増額 |
6-1.実際の悪質な事例(1)後遺障害が残ったにも関わらず不当に低い賠償金
| 事故のケース | 怪我の内容 | 後遺障害等級 | 獲得した賠償金 |
| 歩いて交差点を左折しようしていたところ、右側から右折進行してきた原付自転車と衝突 | 右脛骨遠位端骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫 | 右足関節の可動域制限で10級11号 | 約2000万円 |
最初に紹介するのは、巻き込み事故で深刻な後遺障害が残ったにもかかわらず、相手の保険会社から提示された賠償金がわずか114万円だったという不当な事例です。
こちらの事例では、被害者が手術や長期通院を要する重傷を負ったにもかかわらず、保険会社は
「治療費は打ち切り」「逸失利益はほとんど認めない」
といった態度をとり、低額な示談案を押し付けようとしていました。
被害者は将来の生活に対する不安から、サリュに依頼されました。
サリュでは、後遺障害の程度や仕事・生活への支障を医学的に詳細に立証し、訴訟も視野に入れて粘り強く交渉。
その結果、当初の提示額114万円を大きく上回る約2000万円の賠償金を獲得し、被害者の方も納得のいく解決ができました。
6-2.実際の悪質な事例(2)加害者が過失割合を認めない
| 事故のケース | 怪我の内容 | 後遺障害等級 |
| バイクで走行中、ブレーキをかける暇もなく、隣の車線を走行していた乗用車が左折するのに巻き込まれる | 右股関節脱臼骨折 | 股関節の可動域制限で10級11号 |
次に紹介するのは、本来加害者の過失が大きい事故にもかかわらず、加害者が被害者に責任を押し付けようとした事例です。
こちらの事例では、被害者の方が肩を強く負傷し、長期的に痛みや可動域制限が続いていました。しかし加害者側は「被害者にも大きな過失がある」と主張し、保険会社もそれを鵜呑みにして示談金を低額に抑えようとしていました。
被害者は「自分が悪いはずがない」と感じ、サリュに助けを求められました。
サリュでは、事故の状況や医療機関の診断書・画像を精査し、被害者の過失がないことを主張すると同時に、肩関節の後遺障害を異議申立てで争いました。
その結果、12級の認定を得て休業損害も大幅に増額。最終的には示談金が当初提示から大きく増額され、被害者の方も納得のいく解決に至りました。
6-3.実際の悪質な事例(3)遺族に知識がないからと低額な数字を提示
| 事故のケース | 怪我の内容 | 獲得した賠償金 |
| 自転車で横断歩道を渡っている時に、右折してきた乗用車にはねられる | 翌日に死亡 | 保険会社の提示額から1100万円増額 |
最後に紹介するのは、死亡事故にもかかわらず、遺族の方に専門的な知識がないことをいいことに、相手の保険会社が低額な示談金を提示してきた事例です。
こちらの事例では、遺族の方は大切な家族を突然亡くされたショックのなか、保険会社から「この金額が妥当です」と言われ、提示額を受け入れそうになっていました。
しかし「本当にこのままでいいのか」という疑問がぬぐえず、サリュにご相談いただきました。
サリュでは、裁判例を分析したうえで適正な算定基準で慰謝料や逸失利益を計算し、保険会社との交渉を進めました。
その結果、当初提示の数倍もの金額まで増額ができ示談に至りました。遺族の方も「故人への思いが報われた」と納得のいく解決ができました。
7.大切な人が巻き込み事故にあったら即座に「弁護士を頼って」
ここまで巻き込み事故についての知識を解説してきましたが、大切なのは、
「事故に遭った場合にはできるだけ早く弁護士に相談してほしい」ということです。
巻き込み事故では被害者は後遺障害が残るような重篤な被害を負いやすいです。
しかし、その被害の大きさに対して、加害者有利に話が進みやすく、十分な補償が行われない可能性があります。
そのような納得できない結果を迎えないように、あなたの力になれるのが弁護士です。
特に、死亡事故や、被害者の方に意識がない事故、事故直後の記憶がない事故だと、加害者の一方的な主張で調書が作成され、その情報をもとに過失が決定してしまう可能性があります。
弁護士に依頼すれば、事故当時の状況を丹念に確認し、加害者の証言に正当性があるかを1から確認してもらえます。証拠の確保にも尽力してくれるでしょう。
プロの力を借りることで、事故に対する正当な補償を受けることが可能になります。
8.巻き込み事故で無念な思いをしたくなければ「被害者専門の弁護士」サリュを頼ってください
「突然の巻き込み事故に家族が巻き込まれて、これからどうすればいいのかわからない」
「本当に事故に遭ってすぐで弁護士に連絡してもいいものなのか判断できない」
そんなお気持ちをお持ちの方は、まずはお気軽にサリュにお問い合わせください。
サリュでは、トータルサポートを行っているので、被害者の方が入院中や通院中であってもご相談可能です。
また、ご事情によってはご家族の方が代理でお問い合わせいただくかたちでもご相談可能性ですから、
「何から相談していいのかわからない」というような状況でも、まずはご相談ください。
サリュは、交通事故の被害者に特化して2万件以上を解決してきた、被害者専門の弁護士事務所です。
これまで培ってきた豊富な経験とノウハウで、あなたとご家族を徹底的にサポートいたします。
事故の直後は考える余裕がないかもしれませんが、しばらくすると加害者側の保険会社との戦いが始まります。
加害者有利に交渉を進めようとする保険会社に対して、事故に遭って大きな負担を抱える被害者やご家族が立ち向かうのは本当に大変なことです。
そんなとき、サリュがあなたを支えます。
初回の相談は無料で行っておりますので、
「まだ正式に依頼するかどうかはわからない」という方も、ぜひ気負わずにご相談ください。
電話でお問い合わせをされる方は、下記をクリックしてください。
メールでお問い合わせをされる方は、下記をクリックしてください。
9.まとめ
この記事では、大切なご家族が巻き込み事故の被害者になってしまったという人に向けて、知っておくべき情報やこれからするべきことなどをまとめて紹介しました。
内容のまとめは、以下のとおりです。
▼家族や大切な人が巻き込み事故に遭ったと連絡が遭ったらまずやることは以下の4つ
| 1.病院に連絡し、怪我の状態を確認する 2.職場や他の家族に連絡する 3.被害者の代わりに相手の保険会社とやりとりする 4.事故の証拠を可能な限り集める |
▼巻き込み事故では頭部や胸部に強い衝撃を受けた場合、死亡リスクが高い傾向にあり、命の危機を乗り越えても重度の後遺症が残る可能性がある。
▼巻き込み事故でトラブルになりやすいのは過失割合
▼巻き込み事故で大きな怪我をした場合は、弁護士の力を借りることが重要
「家族のために自分はどうすればいいのだろう」と焦ってしまったとき、この記事の内容を参考にして落ち着いてひとつずつ対処してください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
