もらい事故とは?対処法や請求できるお金、注意点を解説
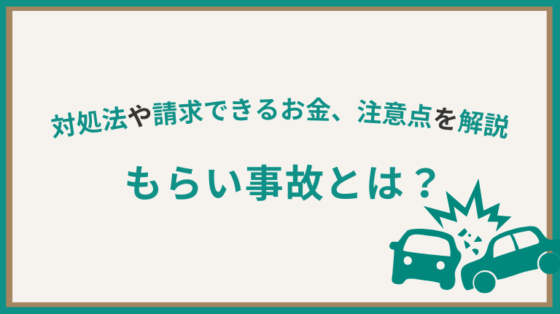
「突然もらい事故に巻き込まれて、どうすればいいのかわからない」
急な交通事故に遭ってしまったあなたは、これから自分がどう行動すればいいのかわからず、困っているのではないでしょうか。
もらい事故とは、被害者に過失のない交通事故のことを指します。
下記のようなケースでは、もらい事故になることが多いでしょう。
| ・停車中に後ろから衝突された ・対向車がセンターラインを越えてきて正面衝突された ・交差点を青信号で進んでいるときに、赤信号で進入してきた車に衝突された |
もらい事故では被害者側の保険会社は介入できないため、示談交渉などを加害者側(相手)の保険会社と、被害者(あなた)が直接行っていくことになります。
この時、相手側の保険会社は、被害者にとって不利な条件を提示するケースがほとんどです。
・車の損傷が大したことがないから、3か月で治療費を打ち切ると言われた
・後遺症の症状が残っているのに、認められないと言われた
このように、被害者がとても納得できないような条件を提示してきて、知識がない被害者が泣き寝入りをしてしまうこともあります。
この記事では、もらい事故の被害者が不当な条件で事故解決をさせられてしまうことがないよう、もらい事故の被害者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
この記事の内容を参考に、納得できる事故解決に向けて行動してください。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢
弁護士法人サリュ
大阪弁護士会
交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得
目次
1.もらい事故は被害者にまったく過失がない交通事故のこと
「もらい事故」とは、被害者側に全く過失がなく、過失割合が100:0で相手方が一方的に悪い交通事故を指します。
たとえば、以下のような事故はもらい事故となるでしょう。
| ・停車中に後ろから衝突された ・対向車がセンターラインを越えてきて正面衝突された ・交差点を青信号で進んでいるときに、赤信号で進入してきた車に衝突された |
このような事故の場合、被害者は免許の点数への影響はありません。
違反点数が加算されたり、ゴールド免許がはく奪されたりするようなことはないため、安心してください。
しかし、もらい事故の場合、示談交渉は基本的に、被害者本人が直接相手方の保険会社と行う必要があるため、注意が必要です。
相手方の保険会社は自社の有利に交渉を進める可能性があるため、対処法を理解しておきましょう。
2.もらい事故が発生したらどうすればいい?今後の流れ
もらい事故に遭ってしまった場合、どのように対応すればいいのかわからず、困ってしまうこともあるでしょう。
ここでは、もらい事故の被害者がこの後どうすればいいのか、今後の流れを解説します。
| 1. 自分と相手の保険会社または保険の取扱代理店に連絡する 2. 病院(整形外科)を受診する 3. (車に損傷があれば)自動車の修理を行う 4. 示談交渉を行う 5. 賠償金の支払いを受け取る |
2-1.自分と相手の保険会社または保険の取扱代理店に連絡する
事故発生後は、まずは被害者・加害者ともに加入先の保険会社または代理店へ報告しましょう。
もらい事故の場合、被害者側保険会社は示談交渉に直接関与できないことが多いものの、自分の保険を使う可能性や弁護士費用特約利用の可否確認などで、連絡は必要です。
例えば、弁護士費用特約が付帯されていれば、自己負担なく弁護士に依頼できるケースもあります。
また、基本的に、相手の保険会社からは事故当日~数日以内に電話などで連絡があるはずです。
そこで今後の流れなどの説明を受けることになるので、相手からの連絡を待ちましょう。
2-2.病院(整形外科)を受診する
交通事故に遭った後は、外傷の有無にかかわらず、病院(整形外科)で診察を受けてください。
むち打ち症などの首の痛みや、手のシビレといった症状は、外形は分からないことが多く、病院に行く必要があるのか、ためらう方もいらっしゃいます。
しかし、受診が遅れると、我慢できる程度の痛みだった、たいした痛みではないと見られてしまうことがあります。
そのため、外傷がなかったとしても、痛みやしびれがあえば、必ず受診をしてください。
| 賠償金請求の際にも事故直後からの通院は重要 |
| 怪我や後遺症が残った場合に相手に賠償金を請求する際にも、事故直後から通院をしていることは重要です。 事故の直後から治療の記録を残すことで、交通事故による怪我であることが客観的に証明でき、怪我の重度についても記録が残るからです。 適正な補償を獲得するためにも、事故に遭ったらまずは病院へ行きましょう。 |
2-3.(車に損傷があれば)自動車の修理を行う
車に損傷がある場合は、見積もりを取って修理を行います。
修理費用は相手方に請求できますが、その根拠となる修理見積もりが必要です。
ディーラーや整備工場で見積もりを取得し、損害額を確定させ、相手の保険会社に連絡しましょう。
修理中に代車やレンタカーを利用した場合、その費用も相手に請求できるため、領収書などを必ず保管しておいてください。
もし、車が全損してしまった方は、以下の記事もご参考ください。

2-4.示談交渉を行う
治療が終わったら、示談交渉へと進みます。
もらい事故では、被害者本人と相手方の保険会社が直接交渉することになります。
相手方の保険会社は、自社の損失を減らそうと、相場よりも低い慰謝料などの示談金を提示してくることがあり、被害者に不利な展開になりがちです。
| 路肩で作業中に乗用車に跳ね飛ばされ、足を骨折。後遺障害等級12級に認定されたケース |
| 【保険会社の提示する条件】 慰謝料や休業損害、逸失利益などが最低限の基準で計算され、怪我の影響で賞与が減額したことも考慮されていない金額 【弁護士の交渉の結果】 正当な金額となるよう交渉を続け、提示金額の2.3倍の金額で示談が成立 事例の詳細を見る |

| 停車中に衝突され、頚椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷の怪我を負ったケース |
| 【保険会社の提示する条件】 「むちうちの通院期間は通常3か月程度である」として、通院期間中にも関わらず治療費の打ち切り 【弁護士の交渉の結果】 自費にて治療を続け、後遺障害等級14級の認定を獲得。その後の交渉で治療費も全額支払われる 事例の詳細を見る |

このように、弁護士への依頼がなければ不当な条件のまま解決させられてしまう事例は多数存在します。
納得できない条件を提示され、交渉がうまく進まない場合には、弁護士への依頼を検討してください。
2-5.賠償金の支払いを受け取る
示談が成立すれば、合意した金額が支払われます。
適切な示談ができれば、治療費や修理費などをカバーできます。
ここまでくれば、もらい事故への対応は終了です。
3.もらい事故で被害者が請求できる項目(慰謝料などの賠償金)
もらい事故の被害者は、物損・人身いずれの場合でも、修理費や治療費、慰謝料などの賠償金を相手側に請求できます。
しかし、どちらの事故かによって請求できる項目には差があります。
それぞれの事故で請求できる項目について、詳しく解説します。
3-1.物損事故の場合
【物損事故で請求できる項目】
| ・車の修理費、買い替え費用 ・代車やレンタカーの使用料 ・休車損害(車を使えなかったことで生じた損害への補償) ・レッカー代 など |
物損事故の場合、主な請求対象は「車の修理費」などの、車の修理にかかる費用です。
過失がない被害者は、全損ではないかぎり、修正費を全額相手に請求可能です。。
実際の修理費用が証拠となり、その分が賠償されます。
見積書や修理工場からの領収書などをしっかり保管しましょう。
3-2.人身事故の場合
人身事故では、物損事故で請求できる項目に加え、以下のような内容を請求できます。
【人身事故で請求できる項目】
| 項目 | 内容 |
| 入通院慰謝料 | 入院・通院が必要なけがを負わされた場合の精神的苦痛に対する慰謝料 →もらい事故の慰謝料相場は0.86万円〜2800万円!獲得事例8つ紹介 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害※が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料 →交通事故の後遺障害慰謝料の相場や計算方法・賢いもらい方とは? |
| 死亡慰謝料 | 被害者を失った遺族の精神的苦痛に対する慰謝料 →自賠責の死亡事故賠償金は一律3000万円ではない!実際の相場解説 |
| 治療費 | 治療費(通院費、入院費、薬代など)の実費全額 |
| 通院交通費 | 治療が終了した時までの交通費の実費相当額 |
| 入院雑費 | 入院時にかかる雑費。1日1000~1500円程度で計算 |
| 休業損害 | 交通事故による怪我で仕事などを休んだ場合の損害を補償する。年収や実際に休んだ日数などをもとに計算 →交通事故の休業損害|職業ごとの算出方法・受け取り方法など網羅解説 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害※を負わなければ被害者が本来得られたであろう利益に対する補償。計算基準によって異なる →【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説 |
※後遺障害:交通事故による怪我で後遺症が残り、労働能力が低下(喪失)したことが認められたもの
たとえば、むちうちで通院した場合、以下のような項目を請求できます。
【むちうちで3か月通院した場合】
| ・3か月の通院に対する入通院慰謝料 ・治療費(通院費、検査費)の実費 ・通院にかかった交通費の実費 ・仕事を休んだ分の休業損害 |
同じ人身事故であっても、怪我の重度や入通院期間、後遺障害の有無などによって請求できる項目は異なります。
| 入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の相場は計算基準によって大きく異なる |
| 交通事故の入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の計算基準には、以下の3つの基準があります。 この中でも、弁護士基準は裁判基準とも呼ばれ、過去の判例をもとに、被害者にとって適正と言える計算基準となります。 しかし、相手の保険会社が提示してくる慰謝料は、基本的に最低限の補償である自賠責基準か、それに近い金額程度であることがほとんどです。 被害者にとって適正な慰謝料を獲得するには、弁護士への依頼が必須となります。 |
4.もらい事故で被害者が使える任意保険は2つ
もらい事故の場合、被害者(あなた)の加入する「人身傷害保険」や「車両保険」が使えることがあります。
もらい事故の場合、基本的に加害者側の保険会社に請求するとお伝えしましたが、もらい事故でも、被害者自身が加入している任意保険を一部使うことができるのです。
補償範囲を理解しておくことで、自己負担を減らし、スムーズに補償を受けられます。
自分の保険を上手に活用すれば、経済的リスクを軽減できるでしょう。
4-1.人身傷害保険
もらい事故の被害者が使える1つ目の任意保険は、「人身傷害保険」です。
人身傷害保険は、被害者が自分で加入している任意保険による補償制度です。
怪我の治療費をはじめ、怪我が原因で働けない期間の収入や、精神的損害に対する補償をします。
| 人身損害保険の補償範囲=治療費や休業損害など実際の損害額 |
自分の保険で治療費や慰謝料を先行して受け取れるので、相手方との交渉が長引いても困りにくいです。
例えば、相手が無保険だった場合でも、人身傷害保険で必要な補償を確保できるでしょう。
相手側の対応に不安がある場合には、自分の保険を使ってカバーすることを検討してください。
4-2.車両保険
もらい事故の被害者が使える2つ目の任意保険は、「車両保険」です。
車両保険は自動車の損傷を補償する保険です。
| 車両保険の補償範囲=適正修理費相当額もしくは車両時価額(時価相当額) ※基本的に使用すると保険等級が下がり、翌年の保険料が上がることに注意 |
もらい事故で実際に修理にかかった費用が加害者に請求できる費用を上回ってしまった場合でも、自分の車両保険で修理費をカバーできます。
また、「車両保険無過失事故特約」をつけている場合、等級が下がらず利用できることがあります。
保険を利用する際には、結果的に損することがないか、加入している特約がないかなど、十分に確認しておくことが必要です。
5.もらい事故では被害者は自力で相手方の保険会社と交渉することになる
もらい事故では、加害者側の保険会社と、被害者本人が交渉する必要があります。
損害保険会社は、基本的に自社の利益を重視し、被害者への補償を最低限にしか行わない傾向にあります。
そのことを知らずに交渉を進めると、本来受け取れるはずの賠償金の相場よりも、不当に低い金額のまま示談を成立させられてしまう可能性があるのです。
実際に以下の事例では、治療費の打ち切りや不当に低い示談金を提示し、被害者が泣き寝入りをせざるを得ない状況へ追い込まれかけていました。
| 追突事故で外傷性頚部症候群の怪我を負った事例 |
| 【相手方の保険会社の対応】 ・事故から半年で、治療中にも関わらず治療費打ち切りの連絡 ・相場よりも低い金額の賠償金の提示 【弁護士の交渉の結果】 ・治療を継続し、後遺障害申請の結果後遺障害等級14級の獲得 ・提示された金額の3倍以上の金額で示談成立 事例の詳細を見る |

「大きい保険会社が言うことだから、間違っていないだろう」
被害者であるあなたは、そんな風に思ってしまうかもしれませんが、それは違います。
相手は被害者のことではなく、自社の利益を優先しているということを知っておきましょう。
もらい事故では自分の保険会社が介入できない以上、そのことを十分知った上で対応していくことが必要です。
6.もらい事故で怪我をしたらまずは弁護士に相談するのがおすすめ
もらい事故で怪我をした場合には、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
なぜ弁護士への依頼が必要なのか、理由は以下の3つです。
| ・相手の保険会社との示談交渉に対等に立ち向かえる ・最終的にもらえる賠償金が高くなる可能性がある ・怪我や後遺障害の妥当な認定を受けるサポートをしてくれる |
6-1.相手の保険会社との示談交渉に対等に立ち向かえる
1つ目の理由は、相手の保険会社との示談交渉に対等に立ち向かえるからです。
先ほどからお伝えしている通り、もらい事故では被害者側の保険会社は交渉に介入することができず、被害者本人が相手の保険会社とやりとりをする必要があります。
交通事故の対応に慣れた保険会社と、初めて事故に遭った被害者が対等にやりとりをするのは、非常に難しいでしょう。
そんなときに力になれるのが、交通事故の対応に慣れた弁護士です。
経験豊富な弁護士に依頼することで、相手の保険会社とも対等に交渉を行ってくれ、被害者が不当な条件を受け入れることを防いでくれます。
6-2.最終的にもらえる賠償金が高くなる可能性がある
2つ目の理由は、最終的にもらえる賠償金が高くなる可能性があるからです。
先ほども少し説明しましたが、交通事故の慰謝料には、「弁護士基準」「任意保険基準」「自賠責基準」という3つの計算基準があります。
この中で最も高額な弁護士基準の慰謝料を請求するためには、弁護士への依頼が必要になります。
また、交通事故で請求できる賠償金は、慰謝料だけではありません。
知識が豊富な弁護士であれば、事故のケースごとに請求できる賠償金を漏れなく精査し、すべて請求することが可能でしょう。
被害者にとって適正な賠償金の獲得のためにも、弁護士への依頼は重要です。計算基準について詳しくは下記の記事もご参考ください。
【怪我のケースで比較】交通事故の慰謝料の弁護士基準とその他の基準の差を徹底解説

6-3.怪我や後遺障害の妥当な認定を受けるサポートをしてくれる
最後の理由は、怪我や後遺障害の妥当な認定を受けるサポートをしてくれるからです。
治療中から弁護士に依頼していれば、
「どんな検査を受けておくべきか」
「後遺症が残りそうな場合、後遺障害の認定に向けてどのような対応をすればいいか」
などのアドバイスを受けることができます。
また、複雑な後遺障害等級の認定に向けて、書類の準備などもサポートしてくれるでしょう。
実際に自分のケースで依頼するべきなのかを判断するためにも、まずは弁護士に相談してみてください。
| 物損事故の場合、弁護士は力になれないケースが多い |
| 物損事故の場合、弁護士に依頼しても力になれないケースが多くなってしまいます。 なぜなら、物損事故では修理費用などの実費を請求することが多く、弁護士に依頼してもしなくても、獲得できる賠償金にあまり差がでない可能性が高いからです。 そのため、弁護士費用が増額分よりもかかってしまう費用倒れが起こるリスクがあるのです。 ただし、物損事故では弁護士に依頼できないというわけではないので、不安がある場合には一度相談してみてください。 |
7.もらい事故の対応ならサリュが力になります
「もらい事故だけど、大きい怪我をしたわけじゃないから弁護士に頼むほどじゃないかも」
そんな風に弁護士への依頼をためらっている方は、ぜひ、サリュにご相談ください。
サリュは、交通事故の被害者の救済に特化し、これまで20,000件以上の交通事故を解決に導いてきた弁護士事務所です。
サリュでは、突然交通事故に遭ってしまい、困っている被害者の方がこれ以上つらい思いをすることがないよう、豊富な知見でサポートを行っています。
【サリュの強み】
| ・元損保弁護士の知見で、相手の保険会社と対等な交渉力 ・示談交渉中だけでなく、もらい事故の治療中からサポートを提供 ・顧問ドクターのサポートで、後遺障害等級の認定にもコミット ・交通事故被害者の方が安心して活用できる無料相談を実施 |
「他の弁護士事務所では治療後に来てくださいと言われた」
「もらい事故なら力になれないと言われた」
そんな方も、まずは一度、サリュにご相談ください。サリュでは、原則相談料や着手金の負担がございません。
メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。
8.もらい事故でよくあるQ&A
最後に、もらい事故に関してよくある質問をQ&A形式でまとめました。
弁護士費用や慰謝料相場、車の修理費用など、被害者が抱く疑問を解消します。
Q、弁護士費用を払えないのですが、弁護士への依頼は諦めたほうがいいですか?
A.諦めなくても大丈夫です。
弁護士費用に不安がある場合、まずはご自身や家族が弁護士費用特約に加入していないか確認してみてください。
弁護士費用特約は、自動車保険などに付帯している特約で、基本的に自己負担なしで弁護士に依頼できる仕組みです。
また、費用面に不安がある場合、無料相談でそのことを聞けば、費用倒れのリスクなどなしで依頼できるかどうかを確認することもできます。
サリュでは、無料の相談を行っている他、着手金なしの完全後払いでの依頼をお受けすることも可能ですので、弁護士費用特約に加入していなくても安心してください。
Q、慰謝料の相場はどのぐらいですか?
A.慰謝料の相場は事故状況や怪我の程度で大きく変わります。
軽いむちうち程度なら数十万円程度、重い怪我で、後遺障害が残った場合には、数百万円以上になることもあります。
実際のもらい事故の慰謝料の獲得事例については、以下の記事で紹介しているので、こちらも参考にしてください。
もらい事故の慰謝料相場は0.86万円〜2800万円!獲得事例8つ紹介

自分のケースでどのくらいになりそうか具体的に知りたい方は、弁護士などの専門家に相談してください。
Q、車の修理費用は全額請求できますか?
A.過失がないもらい事故の場合、基本的に修理費は全額請求可能です。
ただし、車の時価額や修理見積もり金額を超える賠償は困難な場合があります。
車両は今の価格ではなく、購入時の価格をベースに計算され、年式や走行距離によって査定額は下がってしまう傾向にあるからです。
例えば、時価総額が50万円の車に100万円の修理費は認められにくいです。
詳しくは、以下の記事でも解説しているので、こちらも参考にしてください。

9.まとめ
この記事では、もらい事故に遭った被害者が知っておくべき知識を網羅的に解説してきました。
記事の内容のまとめは、以下の通りです。
▼もらい事故の被害者が行うべき今後の流れは以下の通り
| 1. 自分と相手の保険会社または保険の取扱代理店に連絡する 2. 病院(整形外科)を受診する 3. (車に損傷があれば)自動車の修理を行う 4. 示談交渉を行う 5. 賠償金の支払いを受け取る |
▼物損事故の場合請求できる項目は以下の通り
| ・車の修理費、買い替え費用 ・代車やレンタカーの使用料 ・休車損害(車を使えなかったことで生じた損害への補償) ・レッカー代 など |
▼人身事故の場合は上記に加え、以下の項目も請求できる
| ・入通院慰謝料 ・後遺障害慰謝料 ・死亡慰謝料 ・治療費 ・通院交通費 ・入院雑費 ・休業損害 ・後遺障害逸失利益 |
▼もらい事故では被害者が加入する人身傷害保険、車両保険も使える
この記事の内容を参考に、もらい事故に対応してください。
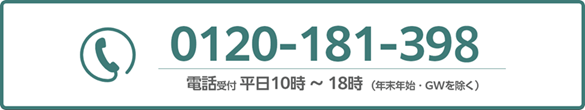

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
