「通勤途中に事故に遭った…」労災の使い方や今後の流れを解説
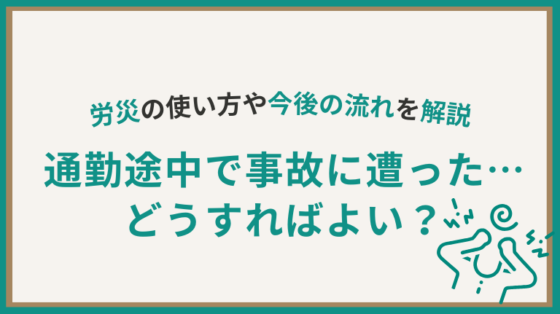
「通勤途中に交通事故に遭ってしまって、どうすればいいのかわからない」
仕事に向かう途中で交通事故に巻き込まれてしまったあなたは、この先どうすればいいのかわからず、困っているのではないでしょうか。
通勤途中に交通事故に遭ったら、事故直後の対応が落ち着き次第会社へ報告しましょう。
通勤中の事故は、通勤災害として労災保険の対象になる可能性があります。
労災保険を使えば、治療費の給付や休業補償が受けられるため、交通事故で怪我をしたことで生じた損害をカバーできるでしょう。
しかし、会社によっては
「うちでは労災保険の手続きはできない」
「申請すると会社にデメリットがあったら困るから、自分の保険を使ってほしい」
などと言われ、労災保険の手続きをスムーズに行ってくれない場合もあります。
そこでこの記事では、被害者であるあなたがきちんと補償を受けられるよう、通勤途中の交通事故の対応方法や、受けられる補償について網羅的に解説します。
この記事の内容を参考に、さっそく行動してください。

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢
弁護士法人サリュ
大阪弁護士会
交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウであなたのために、力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1.通勤途中に交通事故に遭ったら労災になる!まずは会社に連絡しよう

通勤途中に交通事故に遭ったら、まずは会社に連絡してください。
最初に以下の内容を伝えておくと、この先の手続きなどがスムーズになります。
| ・事故の対応で遅刻(欠勤)することの報告 ・交通事故や怪我の状態 ・会社指定の労災指定病院の有無の確認 |
通勤中に交通事故に遭った場合、仕事中と同様に「労災保険」の対象(通勤災害)となる可能性があります。
この場合、自分だけで対処しようとせず、まずは会社へ連絡し、適切な手続きを踏むことが重要です。
【通勤災害の対象になる範囲】
| 対象になる事由 | 労働者が通勤(帰宅)中に事故に遭い、傷病や障害、死亡した |
| 対象になる人 | 労災保険に加入している人(正社員・アルバイト・派遣などの雇用形態を問わず、労働者は基本的に加入している) |
通勤途中に事故に遭ったら、まずは落ち着いて会社へ電話やメールで報告しましょう。
2.通勤途中に事故にあった後の流れ

通勤途中に事故に遭った場合、まず会社・警察に連絡し、相手の情報を確保し、病院で診察を受ける必要があります。
この先の流れについて、具体的に解説します。
| 1. 会社へ報告し労災利用の意思を伝える(総務部や人事部などの担当部署へ) 2. 警察への事情説明・実況見分に協力する 3. 相手の連絡先を手に入れる(加害者の名前、住所、電話番号、加入している保険会社) 4. 当日、もしくはできる限り早く病院で診察を受ける |
事故の直後は、まずは警察への事情説明や実況見分などに全面協力しましょう。
公的な事故記録が残ることで、後の保険請求や労災手続きに有利な証拠になるため、必ず協力しておきましょう。
また、 大した怪我ではないと思っても、必ず病院で診察を受けてください。
事故の直後は怪我をしたという自覚症状が薄いかもしれませんが、事故の衝撃で、骨折などの怪我をしている可能性は少なくありません。
交通事故に遭ったら必ず病院へ行くべき理由は、以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。
交通事故後は即病院へ行くべき3つの理由と受診しないリスクを解説
3.通勤途中の交通事故で補償を受けられる保険は2種類ある
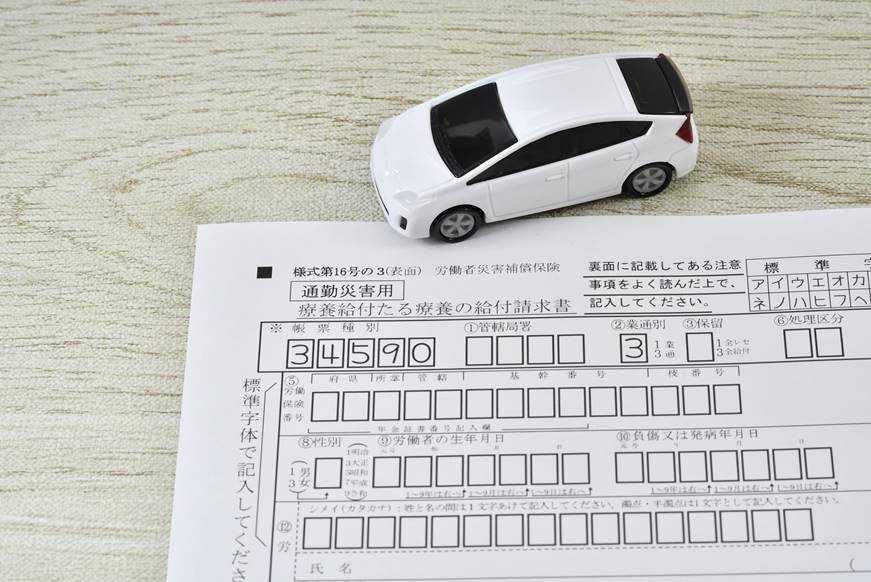
通勤途中の交通事故に遭った場合、「労災保険」と「自動車保険(自賠責保険・任意保険)」の2つから補償を受けることができます。
後遺障害や死亡による損害を除く傷害部分に限りますが、それぞれ、どのような補償を受けられるのか、詳しく解説します。
| 労災保険(通勤災害) | 「加害者側の自賠責保険」 | |
| 内容 | 仕事中に発生した怪我や病気の補償をするための制度。 自分に過失があっても治療費などを全額補償してもらえる | 加害者が過失(不注意)によって事故を起こしてしまった場合に、被害者の損失を補償するための制度 |
| 補償範囲 | ・治療費 ・松葉杖などの療養費用 ・休業補償 | ・治療費 ・松葉杖などの療養費用 ・入院中の雑費 ・診断書作成費用 ・休業損害 ・文書費 ・慰謝料 ※太字は労災保険と重複する項目 |
| 上限額 | 設定なし | 合計120万円 |
3-1.労災保険(通勤災害)
| 労災保険(通勤災害) | |
| 内容 | 仕事中や通勤中に発生した怪我や病気の補償をするための制度 自分に過失があっても治療費などを全額補償してもらえる |
| 補償範囲 | ・治療費 ・松葉杖などの療養費用 ・休業補償 |
| 上限額 | 設定なし |
労災保険は、仕事中や通勤中にケガや病気になった場合に、生活に困らないように補償してくれる保険制度のことです。
通勤中の事故は、通勤災害として労災保険の適用対象となります。
【補償される金額】
| 治療費 | 原則として傷病が治るまでの治療費全額 (基本的に労災病院や労災指定病院等へ通院する場合) |
| 療養費用の範囲 | 治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものなどの実費 |
| 休業補償 | 療養のために休業してから4日目以降から休業補償給付+特別支給金 ※詳細は以下で解説 |
通勤災害の休業補償の金額は、以下の計算式で計算します。
基本的に、事故に遭う3か月前からの賃金を日額として平均化し、その8割が給付されることになります。
【計算式】
| 休業補償給付=給付基礎日額※の60%×休業日数(休業4日目以降) 休業特別支給金=給付基礎日額※の20%×休業日数(休業4日目以降) 【例】給付基礎日額が10000円の場合 休業補償給付:10000円の60%=6000円 休業特別支給金:10000円の20%=2000円 合計8000円給付される(1日あたり) |
※給付基礎日額:事故直前3ヵ月間に支払われた賃金総額(ボーナスは除く)を、その期間の日数で割った1日あたりの給付額
ただし、会社への行き・帰り道であっても、合理的な理由がなく逸脱したと判断された場合は、通勤途中と認められない可能性があります。
実際に、どのようなケースで通勤災害が認められるかは、以下の表を参考にしてください。
| 労災が 適用されるケース | ・会社に行く途中にコンビニなどに立ち寄った ・家から出向先に直行していた ・仕事に必要な忘れ物を取りに戻った ・会社に届け出を出していないマイカー通勤中だった (就業規則違反でも労災認定は受けられる) |
| 労災が 適用されないケース | ・旅行先など、住居ではない場所から出勤していた ・仕事とは無関係の私物の忘れ物を取りに戻った |
普段使っている通勤ルートで事故に遭った場合や、マイカー通勤が会社に黙認されている場合でも、労災が適用される事例があります。
具体的に、厚生労働省が定める通勤災害の逸脱、中断の例外の定義は以下になるので、こちらをもとに確認してください。
| 厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為 |
| (1)日用品の購入その他これに準ずる行為 (2)職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 (3)選挙権の行使その他これに準ずる行為 (4)病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 引用:通勤災害について | 東京労働局 |
3-2.加害者側の自動車保険
| 加害者側の自動車保険(自賠責) | |
| 内容 | 加害者が過失(不注意)によって事故を起こしてしまった場合に、被害者の損失を補償するための制度 |
| 補償範囲 | ・治療費 ・松葉杖などの療養費用 ・入院中の雑費 ・診断書作成費用 ・休業損害 ・文書費 ・慰謝料 ※太字は労災保険と重複する項目 |
| 上限額 | 合計120万円 |
交通事故では、加害者が加入している自動車保険からも補償が受けられます。
自賠責保険は、労災保険と比べて補償範囲が広いため、入院中の雑費や文書費などの、労災保険では補償を受けられない部分を補ってくれます。
ただし、自賠責保険の支払い金は、補償内容すべてを合わせて120万円が上限となるため、注意が必要です。
加害者が加入している保険には自賠責保険(加入義務があるもの)に加えて、任意保険があることがあります。
自賠責保険の120万円の上限額を超えた部分については、任意保険でカバーしてもらうことも可能です。
3-3.二重取りにならなければ併用も可能
労災保険と自動車保険は、併用することが可能です。
| ・治療費は労災保険から補償を受け、入院中の雑費や慰謝料は自賠責保険に請求する |
というような使い方ができるため、組み合わせて請求することができます。
ただし、同一損害の二重取りはできません。
| ・労災保険で治療費の補償を受けながら、自賠責保険に治療費を請求する |
というようなことは、できないようになっています。
詳しい手続きや併用する方法などは以下の記事で解説しているので、併せてご参照ください。
4.通勤途中に事故にあったときの注意点

通勤途中に事故にあった場合、注意するべき点がいくつかあります。
被害者であるあなたが損害を被るようなことがないよう、これらの点に気を付けながら対応を進めてください。
| 1.会社に労災保険の使用を拒否されても交渉を続ける 2.どんなに手間でも 事故後は必ず病院を受診する 3. 通勤中の事故で会社を休む場合は、有給休暇か休業補償を選ぶ 4.保険会社とやり取りする前に早い段階で弁護士に相談する |
4-1.会社に労災保険の使用を拒否されても交渉を続ける
まず注意してほしいのが、会社に労災保険の使用を拒否されても、交渉を続けることです。
労働者は雇用形態を問わず労災保険に加入しており、労災利用は法律で保障された権利です。
しかし、会社によっては「労災を使うことでデメリットがあるのではないか」と考え、申請を拒否する場合があります。
通勤中とはいえ会社と無関係の相手と起こした交通事故の場合、会社に責任はなく、申請をすることで会社にデメリットが生じるようなことはありません。
そもそも、会社には業務災害によって休業した場合、企業は労働基準監督署に死傷病報告書を提出する手続きを行う義務があります。
手続きを行わなかった場合、会社は労災隠しを行ったとして、罰則の対象になる可能性もあるのです。
「うちは労災の手続きはやっていない」などと言われても、隠したほうがリスクになる可能性が高いことをしっかり説明し、引き下がらないでください。
| どうしても会社が対応してくれない場合は自分で手続きすることも可能 |
| 労災の手続きは基本的に会社が行うものですが、どうしても会社で対応してもらえない場合には、労働者本人(あなた)が手続きをすることも可能です。 以下の厚生労働省のページから必要な書式をダウンロードし、労働基準監督署長あてに提出することで必要な調査が行われ、保険金が給付されます。 参考:労災保険給付関係主要様式│厚生労働省 ※治療費については、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を受診した労災保険指定医療機関に提出してください。 労災保険指定医療機関ではない場合、一旦費用を立て替え、直接、労働基準監督署長に提出してください。 |
4-2.どんなに手間でも 事故後は必ず病院を受診する
次に、事故後は必ず病院を受診することも重要です。
症状が軽い、自覚症状がないと思っていても、必ず1度は病院を受診し、検査などを受けておきましょう。
交通事故直後はアドレナリンで痛みを感じにくく、翌日以降に痛みが出てくることはよくあります。
ここで病院へ行かず、症状が後から出てきても、初診の記録がないと労災や保険請求に不利になるかもしれません。
必ず、事故後すぐに医師の診察を受け、診断書を取得しておきましょう。
4-3.通勤中の事故で会社を休む場合は、有給休暇か休業補償を選ぶ
通勤中の事故で休業する場合は、休んでいる間の給与を有給休暇か休業補償のどちらかでカバーすることになります。
基本的に、2つを同時に使うことはできません。
それぞれの特徴は以下の通りです。
| 有給休暇 | 休業補償 | |
| 金額 | 会社の就業規則で決まった金額 | 給付基礎日額の80% |
| 条件 | ・有給休暇が残っている | ・労災の認定を受けている |
| メリット | ・欠勤扱いにならない | ・有給休暇の残日数を気にしなくてよい |
| デメリット | ・付与された日数が限られている | ・基本的に休業1日目から3日目までの休業保険を請求することができない ・通勤災害による休業は欠勤扱いとなる |
通勤災害で休業補償を使った場合、休んでいる期間は欠勤の扱いとなります。
欠勤数が翌年に付与される有給の日数やその期間の評価に関わる可能性があるため、長期間の休業が必要になりそうな場合は、有給を組み合わせるなどの工夫が必要です。
4-4.保険会社とやり取りする前に早い段階で弁護士に相談する
今後の交渉に向けて、弁護士へ相談しておくことも大切です。
この先、交通事故の示談金の獲得に向けて、相手の保険会社と交渉していくことになります。
その時に力になってくれるのが、交通事故の対応に慣れた弁護士です。
弁護士は、適切な賠償金の相場や保険会社との交渉術に精通しており、被害者に不利な提示を避けやすくなります。
納得のいく補償を得るため、早めに専門家の力を借りることを検討してください。
| 会社や加害者側とのやりとりにお困りごとがあるときはサリュにご相談ください |

「どれだけ伝えても会社が労災手続きをしてくれない」
「加害者が自分の任意保険を使いたくないと言ってくる」
通勤中に交通事故に遭い、そのようなお悩みを抱えている方は、ぜひサリュにご相談ください。
サリュは、これまで20,000件以上の交通事故解決実績のある、被害者専門の弁護士事務所です。
交通事故に対する確かな経験と知識で、あなたを全面的にサポートいたします。
通勤中の交通事故の対応でお困りごとがある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。
メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。
5.通勤途中の交通事故に関するよくある質問

通勤途中の事故に関して、雇用形態や対処法など、被害者が疑問に思いやすい点について整理します。
以下のQ&Aで基本的な疑問をクリアにし、状況に応じて専門家への相談も視野に入れてください。
Q. 派遣やパート、アルバイト、公務員の場合でも労災は使えますか?
A.使えます。
労災保険は正社員に限らず、雇用関係のあるすべての労働者に適用されるためです。
実際、アルバイトでも通勤事故で労災認定されたケースは多数あります。
雇用形態を理由に労災が拒否されることはありません。
Q. 事故でしばらく休むことになったときはどうしたらいいですか?
A.休業補償を労災保険から受ける手続きを進めましょう。
休業補償の受給条件や具体的な金額については、以下の記事で解説しているので、詳しくはこちらを参考にしてください。
交通事故でも休業補償はもらえる|4つの受給条件と休業損害との違い
Q. 怪我がない場合はどうなりますか?
A.怪我がない場合は通勤災害とはなりません。
通勤災害は、労働者の通勤による負傷などを補償するものです。
そのため、怪我がない物損事故の場合は、労災の対象とはなりません。
Q. マイカー通勤だった場合はどうなるの?
A.マイカー通勤中の事故は、基本的には労災対象になります。
もしマイカー通勤の手続きを会社に行っていないという場合でも、合理的な通勤経路と認められる場合、通勤災害として労災適用が可能です。
ただし、会社の就業規則に違反している場合、その部分のペナルティを受ける可能性があるので、注意してください。
6.まとめ
この記事では、通勤途中で交通事故に遭ってしまった方が、労災保険を使うための方法や、保険での補償の内容などを解説してきました。
内容のまとめは以下の通りです。
▼通勤途中に交通事故に遭ったら、以下の内容を会社に報告する
| ・事故の対応で遅刻(欠勤)することの報告 ・交通事故や怪我の状態 ・会社指定の労災指定病院の有無の確認 |
▼事故のあとは、以下の手順で対応を進める
| 1. 会社へ報告し労災利用の意思を伝える(総務部や人事部などの担当部署へ) 2. 警察への事情説明・実況見分に協力する 3. 相手の連絡先を手に入れる(加害者の名前、住所、電話番号、加入している保険会社) 4. 当日、もしくはできる限り早く、病院で診察を受ける |
▼通勤途中の交通事故で使える保険は以下の通り(後遺障害や死亡による損害を除く傷害部分に限ります)
| 労災保険(通勤災害) | 加害者側の自動車保険(自賠責) | |
| 内容 | 仕事中に発生した怪我や病気の補償をするための制度。 自分に過失があっても治療費などを全額補償してもらえる | 加害者が過失(不注意)によって事故を起こしてしまった場合に、被害者の損失を補償するための制度 |
| 補償範囲 | ・治療費 ・松葉杖などの療養費用 ・休業補償 | ・治療費 ・松葉杖などの療養費用 ・入院中の雑費 ・診断書作成費用 ・休業損害 ・文書費 ・慰謝料 ※太字は労災保険と重複する項目 |
| 上限額 | 設定なし | 合計120万円 |
▼通勤途中に事故にあったときの注意点は以下の4つ
| 1.会社に労災保険の使用を拒否されても交渉を続ける 2.どんなに手間でも 事故後は必ず病院を受診する 3. 通勤中の事故で会社を休む場合は、有給休暇か休業補償を選ぶ 4.保険会社とやり取りする前に早い段階で弁護士に相談する |
この記事の内容を参考に、通勤途中の交通事故に対応してください。

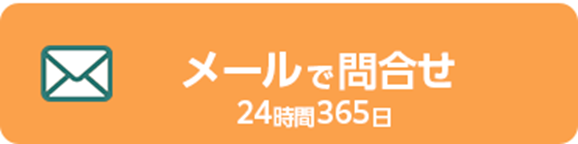

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
