手首骨折の後遺症|症状や後遺障害等級、認定手順を紹介
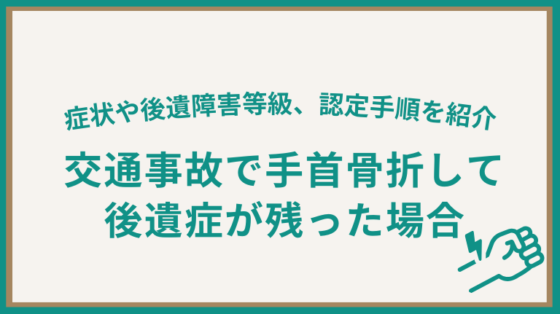
「手首骨折では、どんな後遺症が残るリスクがあるんだろう」
「手首のリハビリ中に痛みを感じることがあるけど、これって後遺症なの?」
手首骨折の治療中のあなたは、このようなお悩みを抱えていませんか。
手首骨折の後遺症としては、痛みやしびれ、動きが制限されるという症状が残る可能性があります。
もし手首骨折で後遺症が残ってしまった場合には、症状によっては、後遺障害等級の認定を受けられることがあります。
後遺障害等級の認定とは、交通事故などによる怪我の後遺症が残り、生活や仕事に影響を及ぼしていることに対して認定を受けることです。
後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害に対する慰謝料や、後遺症の影響で得られなくなるであろう将来の収入に対する補償(逸失利益)などを含めた賠償金が請求できる場合があります。
しかし、手首骨折の後遺症で、後遺障害等級の認定を受けるのは、簡単ではありません。
また、せっかく等級を受けられても、症状に対して適正な等級を獲得しないと、正当な補償を受けているとはいえないでしょう。
この記事では、手首骨折の後遺症が残ってしまいそうな人が不安に思う、以下の内容をわかりやすく解説しています。
| この記事でわかること |
| ・手首骨折ではどんな後遺症が残る可能性があるのかわかる ・後遺症が残った場合のその後の対応方法がわかる ・後遺障害等級の認定に向けてやるべきことがステップでわかる ・適正な等級で認定を受けるためのポイントがわかる |
手首骨折の後遺症が残ってしまったとしても、この記事の内容を参考に、落ち着いて行動してください。
正しい対応で、適正な補償の獲得に向けて行動しましょう。

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1.手首骨折で残る可能性のある後遺症の症状
最初に少し触れた通り、手首骨折では、痛みやしびれ、動かしづらさなどの後遺症が残ることがあります。
どんな症状が残りやすく、生活にどのような影響が出るのか、以下にまとめました。
| 症状 | 後遺症の 残りやすさ | 日常生活への 影響 | 内容 |
| 痛み、しびれ | ★★★ | ★★★ | 手首周辺に痛みやしびれが残る。 重い物を持った時や、スポーツなどで負担がかかると強い痛みを感じる。 |
| 動かしづらい | ★★☆ | ★★★ | 手が動かしづらく、着替えや入浴などの日常動作がしづらくなる。 パソコンなどの仕事に影響が出ることもある。 |
| 力がうまく入らない ※リハビリなどで完治できる 可能性がある | ★☆☆ | ★★☆ | ものがうまく掴めなかったり、手に疲れを感じやすくなったりする。 |
※あくまで一例です。
それぞれの症状について、詳しく説明します。
1-1.痛み、しびれ
一番よく見られる手首骨折の後遺症は、痛みやしびれの症状です。
本来、骨折では骨がくっつくと痛みが引きますが、骨折した際に周囲の神経や血管などを損傷することで、このような症状が残ることがあります。
普段は痛みがなくても、重いものを持った時など、手首に強い負担がかかることで痛みやしびれが現れるケースが多いでしょう。
後遺症の症状が重い場合には、安静時にも痛みやしびれが続き、日常生活に支障をきたすこともあります。
【痛み・しびれの後遺症による日常生活への影響】
| ・痛みのせいで手がうまく動かせない ・手首に痛みやしびれがあり、ずっと気になる ・パソコン作業など、手を使う作業を長く続けられない |
1-2.動かしづらさ、指などのこわばり
次によく見られるのが、動かしづらさや、指などのこわばりの症状です。
これは、骨折の影響で関節の可動域が狭くなったり、関節周辺の筋肉が硬化したりすることで起こると考えられています。
これらの症状が出ると、着替えや入浴など、怪我をするまでは普通に行っていた日常動作が難しくなります。
また、パソコンや筆記用具の扱いに影響が出るため、症状の重さによっては、これまで通りの仕事ができなくなってしまうということもあるでしょう。
【動かしづらさ・指などのこわばりの後遺症による日常生活への影響】
| ・ボタンをはずす、薬を取り出すなどの細かい作業ができない ・パソコン作業やピアノなどの楽器の演奏、スポーツなどがうまくできない |
| 手首骨折では、筋力低下で「うまく力が入らない」症状が残ることも |
| 骨折の治療中に、患部をギプスなどで長時間固定していると、動かさなかった分筋力が低下し、筋肉が弱ってしまうことがあります。 その影響で、一時的に手首や手の力がうまく入らなくなってしまう症状が出る方もいるでしょう。 これにより、 ・ものがうまく掴めない ・手を思うように動かせない ・(筋力低下により)疲れやすくなる というような影響が出ることがあります。 しかし、筋力の低下は基本的に一時的なもので、リハビリなどを続ければ回復に向かうことが多いとされています。 |
2.交通事故で手首骨折をして後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けられる可能性がある
前章では手首骨折で残る可能性がある後遺症の症状をお伝えしました。
「自分もこんな症状が残りそう」
「医師に説明されたものに当てはまる」
そう感じた方も多いのではないでしょうか。
交通事故で手首骨折の怪我を負い、後遺症が残ってしまった場合、その症状の内容や重さに応じて、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
| 後遺障害等級の認定とは |
| 後遺障害等級の認定は、交通事故による怪我で後遺症が残ってしまった際に、症状の程度やその後の生活への影響をもとに、適切な賠償額を判断するために行われる判断です。 認定は、保険会社ではなく、損害保険料率算出機構という公的機関が行います。 等級は1級~14級の14段階あり、数字が小さいほうが障害の重度が重いと判断され、賠償金も高くなる傾向にあります。 交通事故による怪我の被害者は、この認定を受けることで、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの賠償金を請求できるようになります。 ※後遺障害慰謝料…交通事故によるケガで後遺障害が残ったことに対して支払われる金銭のこと。後遺障害を負ったことによる精神的な負担などについての補償のこと。 ※逸失利益…死亡事故の被害や後遺障害を負うことによって本来健常なままであれば得られたであろう収益などの利益のこと。 |
後遺障害等級の認定と聞くと、
「大怪我をして、介護が必要な人しか受けられないんじゃないの?」
「手首骨折くらいじゃ、関係なさそう」
そんな印象を受けるかもしれませんが、そんなことはありません。
実際に、手首骨折の後遺症でも、後遺障害等級の認定を受け、慰謝料などを含めた賠償金を獲得した事例は存在しています。
【事例1】
| 事故の状況 | バイクと自動車の事故で衝突・転倒。 右橈骨遠位端骨折の診断を受ける |
| 後遺障害等級 | 右手関節の痛みについて「12級13号」認定 |
| 賠償金額 | 約540万円(自賠責保険金224万円を含む) |
事例の詳細を見る(手関節の骨折で「非該当」だったが、異議申立てを行い「12級」認定!)
【事例2】
| 事故の状況 | 交通事故により、右橈骨遠位端粉砕脱臼関節内骨折、 右尺骨茎状突起骨折という、右手首の関節が砕けたような怪我 |
| 後遺障害等級 | 右手首には可動域が通常の2分の1以下に制限される症状が残り、 「10級10号」認定 |
| 賠償金額 | 約3500万円 |
事例の詳細を見る(事前提示賠償額2000万円から、交渉で3500万円まで増額解決した事例)
このように、適正な後遺障害等級の認定を受けることで、慰謝料などを含めた賠償金を獲得できた事例は多数あります。
反対に、「後遺症が残っている」と感じていても、認定を受けずにいると、本来ならば得られたかもしれない慰謝料などを含めた賠償金を請求することができないのです。
3.手首骨折で認められる可能性のある後遺障害の等級
後遺障害等級には全部で14段階あり、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等、それぞれの等級に対応した補償の金額が異なるとお伝えしました。
「具体的に、手首骨折では何級くらいに認定されるの?」
という疑問があるかと思いますが、手首骨折では、症状によって7級、8級、10級、12級、14級の等級に認定されるケースが多いです。
(怪我の状態や、手首骨折以外の症状によって異なるケースもあります)
それぞれ、どんな症状が何級に認定されるのか、詳しく解説します。
3-1.【神経症状】手首に痛みやしびれが残る│14級・12級
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
手首に痛みやしびれが残る後遺症は「神経症状」として判断され、14級、もしくは12級に該当する可能性があります。
14級と12級の違いは、検査結果やレントゲン写真などの医学的な所見の有無が大きく関わっています。
十分な医学的所見があり、症状が証明できるものは12級に認定される場合があります。
画像所見などはないものの、治療の経緯などを見て症状が残っていると証明できるものは14級と判断されるケースが多いでしょう。
3-2.【可動域の制限】手がもとのように動かせない│12級・10級・8級
| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
手がもとのように動かせない後遺症は、「可動域の制限」として判断され、12級、10級、8級のいずれかに該当する可能性があります。
等級の違いは、手首の可動域が障害のない関節と比べて、どこまで動くかで変わります。
ケースによっても異なりますが、概ね、下記のような基準で等級が決まると言われています。
| 12級6号 | 手首の可動域が障害のない関節の3/4以下 |
| 10級10号 | 手首の可動域が障害のない関節の1/2以下 |
| 8級6号 | 手首がまったく動かない~障害のない関節の1/10以下 |
3-3.【変形障害】骨がもとの形にくっつかない、偽関節ができる│12級・8級・7級
| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
| 8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
| 7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
骨がもとの形にくっつかない、偽関節ができるなどの後遺症は、「変形障害」として判断され、12級、8級、7級のいずれかに該当する可能性があります。
骨がうまくくっつかず、不完全な状態で癒合してしまった場合には、「変形」「癒合不全」として12級に認定される可能性があります。
また、骨がうまくくっつかず、付着できなかった骨同士の間が関節のように動いてしまうことを、偽関節といいます。
この偽関節ができた場合には、
・日常生活で硬性補装具が必要な場合は7級
・硬性補装具がなくても生活ができる、一時的にしか使わないという場合には8級
に認定されるケースが多いでしょう。
4.手首骨折の後遺症は後遺障害等級によって賠償金が大きく左右される
前章では、手首骨折の後遺症で認定される可能性がある後遺障害の等級をお伝えしました。
実は、認定された等級が違うと、請求できる慰謝料や逸失利益などを含めた賠償金に大きな差が出ます。
なぜなら、請求できる慰謝料や逸失利益などを含めた賠償金は、何級に認定されたかをもとに計算するからです。
例えば、手首骨折をして、痛みやしびれの後遺症が残ったケースについて見てみましょう。
| 【等級目安】 ・検査結果など十分な医学的所見が残っていた:12級 ・証拠が不十分だった:14級 ※あくまで一例です。実際は個別の状況により、認定の有無や等級は異なります。 |
| 後遺障害慰謝料 | 逸失利益 | |
| 12級 | 290万円 | 2,590万円 |
| 14級 | 110万円 | 925万円 |
| 差額 | 180万円 | 1,665万円 |
※後遺障害慰謝料の相場は弁護士基準
※逸失利益は【基礎年収500万円、現在30歳で67歳まで働く】と仮定し、12級14%、14級5%で計算した場合
このように、認定される等級が違うだけで、補償される金額に大きな差が出ることになります。
適正な補償を請求するためには、症状に合った正しい認定を受けることが重要です。
| 労働能力喪失率で逸失利益の金額が変わる |
| 逸失利益とは、後遺障害を負うことによって、本来健常なままであれば得られたであろう収益などの利益のことです。 【計算式】基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間 この中でも、受けた等級によって、労働能力喪失率が変わります。 例えば、基礎年収500万円、現在30歳で67歳まで働くと仮定した場合、以下のような差が出ます。 ・12級(労働能力喪失率14%):2,590万円 ・14級(労働能力喪失率5%):925万円 →差額 1,665万円 基礎収入が同じでも、等級が異なることで、補償額は大きく変わってしまうのです。 逸失利益の詳しい計算方法については、下記の記事で説明しています。 【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説 |
5.【4ステップでわかる】後遺障害等級の認定を受ける手順
ここまでの内容を読んで、自分の後遺症が残りそうだから、後遺障害等級の認定を受けたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
この章では、後遺障害等級の認定を受けるまでの手順を、4ステップで簡潔に解説します。
| 【STEP1】医師に症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらう 【STEP2】手続きに必要な書類を準備する 【STEP3】保険会社に必要書類を提出し、審査を待つ 【STEP4】結果が通知される |
順番に確認し、確実に行動できるようにしましょう。
5-1.【STEP1】医師に症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらう
まずは、医師に症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらいます。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状が改善しない」と医師が判断した状況のことです。
症状固定の時期を過ぎても残っている症状については、後遺障害等級の認定を進めていくことになります。
後遺障害診断書は、後遺障害が残っていることを医師に証明してもらう書類です。
| ・後遺症の症状の詳細 ・症状の程度 ・治療の過程 ・日常生活への影響 |
このような内容について、医師に記載してもらいます。
後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定時に、非常に大きい役割を果たす書類です。
この書類の内容に不備があると、正当な等級で認定されない可能性が高まります。
そのような事態を避けるためにも、通院中から医師とのコミュニケーションをかかさず取り、症状や日常生活への影響を漏れなく伝えて記載してもらうようにしましょう。
5-2.【STEP2】手続きに必要な書類を準備する
次に、手続きに必要な書類を準備します。
後遺障害等級の申請には、後遺障害診断書以外にもさまざまな書類が必要になります。
手続きに必ず使う書類は、以下の通りです。
【必要書類】
| ・後遺障害診断書(医師に記載してもらい、病院でもらう) ・交通事故証明書(警察に申請して交付してもらう) ・事故発生状況報告書(保険会社のテンプレートなどに自身で記載する) ・保険金支払請求書(保険会社のテンプレートなどに自身で記載する) ・(被害者請求の場合)印鑑証明書(役所やコンビニで交付してもらう)※事前の印鑑登録が必要 |
また、以下のような書類も必要になる(あった方がいい)場合があります。
【事例によって提出することが有益となる書類】
| ・レントゲンなどの検査結果を証明する書類(担当医に問い合わせ、病院で交付してもらう) ・物損資料や実況見分調書などの刑事記録 |
5-3.【STEP3】保険会社に必要書類を提出し、審査を待つ
必要書類を揃えたら、保険会社に提出し、審査を待ちます。
後遺障害等級の認定は、保険会社を経由して、損害保険料率算出機構という公的機関が行います。
(事前認定の場合は任意保険会社に、被害者請求の場合は直接自賠責保険会社に書類を提出します)
審査は、主に書類審査で行われます。
提出した書類の内容をもとに審査されるため、不備のない書類の提出を心がけましょう。
審査には、目安として約数週間〜数か月かかることが多いです。
内容によっては、追加の資料を求められるようなケースもあるため、保険会社から連絡があった場合には迅速に対応しましょう。
5-4.【STEP4】結果が通知される
審査が完了すると、保険会社を通じて結果が通知されます。
結果の通知には、認定された等級やその理由が記載されており、認定が見送られた場合には非該当と通知されます(正確には、「自動車損害賠償責任保険お支払不能のご通知」という文書が送付されます)。
| 認定結果に不満がある場合、異議申し立てができる |
| 後遺障害等級認定の結果に納得できない場合、異議申し立てが可能です。 異議申し立てには新たな医学的証拠(再検査の結果や新しい診断書など)を添えて再申請を行い、症状の重大さや生活への影響を再度証明します。 自分で行って非該当や納得のいかない等級だった、という場合には、有効な書類を集められていない可能性があります。 弁護士に相談して、どんな書類を準備するべきか、どんな書き方をするべきかなど、アドバイスをもらったほうがいいでしょう。 |
6.手首骨折で後遺障害等級の認定を獲得するのは難しい!
手首骨折の後遺症では後遺障害等級の認定を受けられる可能性があることをお伝えしてきましたが、実は、手首骨折で等級の認定を獲得するのは、難しいのが現状です。
まず、後遺障害の認定される割合は、全体で見ても約5%と、狭き門となっています。
さらに、手首骨折の後遺症として残りやすい「神経症状」や「可動域制限」は外見では判断しづらく、十分な客観的証拠となる書類の提出が重要となります。
この証拠が不足していることが原因で、等級が非該当になってしまうケースが多いのです。
とはいえ、先ほど実際に等級の認定を受け、慰謝料などを含めた賠償金を獲得した事例をお見せしたように、手首骨折の後遺症で認定を受けている方もいます。
十分な証拠となる書類を準備し、適切に手続きを行うことで、手首骨折の後遺症でも正当な等級の認定を受けられる可能性があるでしょう。
7.適正な等級と慰謝料などの賠償金を獲得するためには弁護士のサポートが必要
手首骨折の後遺症で適正な後遺障害等級の認定を受け、納得できる慰謝料などを含めた賠償金を獲得できる可能性を上げたいなら、弁護士のサポートがあなたの助けになるかもしれません。
それには、2つの理由があります。
| ・後遺障害等級の認定のアドバイスをしてくれるから ・獲得できる慰謝料などを含めた賠償金が増額する可能性があるから |
それぞれどういうことなのか、詳しく解説します。
7-1.後遺障害等級の認定のアドバイスをしてくれるから
ひとつ目の理由は、後遺障害等級の認定のアドバイスをしてくれるからです。
前項でも述べた通り、手首骨折で後遺障害等級の認定を受けるのは難しいとされています。
なぜなら、手首骨折の怪我が原因で後遺障害が残っているということを、書類で客観的に証明するのが難しいからです。
そこで頼りになるのが、後遺障害認定のサポート実績が豊富な弁護士です。
これまでの認定サポートの経験から、以下のような内容を確認し、アドバイスしてくれます。
| ・必要書類に不備はないか ・後遺障害診断書の内容は適切に書かれているか ・他に受けておくべき検査などはないか |
担当医は、治療については専門家かもしれませんが、後遺障害の認定については不慣れな場合がほとんどです。
そのため、医師の指示に従っているだけでは、認定について書類が不十分になったり、書類の書き方に不備があったりする可能性があります。
その時に、法的な視点や過去の認定の傾向などから適切なアドバイスをしてくれるというのが、弁護士が力になれるひとつ目の理由です。
7-2.獲得できる慰謝料などを含めた賠償金が増額する可能性があるから
ふたつ目の理由は、獲得できる慰謝料などを含めた賠償金が増額する可能性があるからです。
弁護士に依頼することでなぜ獲得できる慰謝料などを含めた賠償金が増額するのかというと、以下のような理由があります。
| ・【理由1】弁護士基準という高額な計算基準で慰謝料を請求できる ・【理由2】請求できる項目を漏れなく確認してくれる |
7-2-1.【理由1】弁護士基準という高額な計算基準で慰謝料を請求できる
賠償金が増額する理由その1は、弁護士基準という高額な計算基準で慰謝料を請求できるからです。
交通事故の慰謝料の計算基準には、以下の3種類があります。
この中でも、相手の保険会社が提示してくるのは、最低限かそれに近い、低い基準の金額です。
ですが、弁護士に依頼することで、過去の裁判例をもとに、被害者にとって適正だと言われている「弁護士基準」で計算した慰謝料を請求することができるのです。
具体的な金額の差は、以下の通りです。
| 14級 | 10級 | 8級 | |
| 弁護士基準 | 110万円 | 550万円 | 830万円 |
| 自賠責基準 | 32万円 | 190万円 | 331万円 |
| 差額 | 78万円 | 360万円 | 499万円 |
このように、慰謝料の計算基準が変わるだけで、最終的に受け取れる賠償金の総額に大きな差が出るのです。
7-2-2.【理由2】請求できる項目を漏れなく確認してくれる
賠償金が増額するもう一つの理由は、請求できる項目を漏れなく確認してくれるからです。
交通事故の賠償金では、慰謝料や逸失利益の他にも、請求できるお金がたくさんあります。
【交通事故の賠償金の内訳】
| ・治療費 ・入院費用 ・通院交通費 ・入通院慰謝料 ・後遺障害慰謝料 ・逸失利益 ・休業損害 ・将来の医療費(後遺障害が残る場合) ・義肢、装具費用(装具が必要な場合) |
これらの項目の中には、弁護士に依頼しないままだと請求できることに気が付かなかったり、相手の保険会社に「このケースでは請求できません」と言われて信じてしまったりして、請求が漏れてしまうものがあります。
それを防いで、漏れなく受け取れる賠償金を請求するためにも、弁護士への依頼は効果的です。
| 手首骨折の後遺症が残りそう…対応に不安がある方は、サリュにご相談ください! 「後遺障害等級の認定って難しそう」「相手が提示している示談金、相場より低い気がする」 そんな悩みを抱えている方は、ぜひ、サリュへご相談ください。 サリュは、これまで約20000件以上の交通事故事例の解決実績がある 被害者救済に特化した弁護士事務所です。 手首骨折の対応経験も豊富で、後遺障害等級の認定や異議申し立てでも数多くの解決事例があり 確かな知見であなたをサポートいたします。 自分と似た解決事例を探す 電話やメールにて無料相談も承っておりますので 後遺障害等級の認定や示談金交渉に不安がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。 電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。 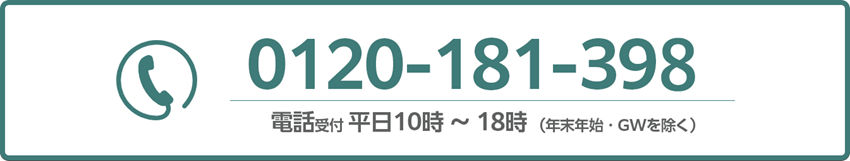 メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。 |
8.まとめ
この記事では、手首骨折の後遺症について解説しました。
内容のまとめは、以下の通りです。
▼手首骨折では、以下のような後遺症が残る可能性がある
| 症状 | 後遺症の 残りやすさ | 日常生活への 影響 | 内容 |
| 痛み、しびれ | ★★★ | ★★★ | 手首周辺に痛みやしびれが残る。 重い物を持った時や、スポーツなどで負担がかかると強い痛みを感じる。 |
| 動かしづらい | ★★☆ | ★★★ | 手が動かしづらく、着替えや入浴などの日常動作がしづらくなる。 パソコンなどの仕事に影響が出ることも。 |
| 力がうまく入らない ※リハビリなどで 完治できる可能性がある | ★☆☆ | ★★☆ | ものがうまく掴めなかったり、手に疲れを感じやすくなったりする。 |
※あくまで一例です。
▼交通事故で手首骨折をして後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けられる可能性がある
▼後遺障害認定を受けるまでの手順は下記の4ステップ
| 【STEP1】医師に症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらう 【STEP2】手続きに必要な書類を準備する 【STEP3】保険会社に必要書類を提出し、審査を待つ【STEP4】結果が通知される |
▼手首骨折で後遺障害等級の認定を獲得するのは難しいため、弁護士のサポートが必要
この記事の内容を、手首骨折の後遺症が残った際の行動の参考にしてください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
