交通事故の休業損害|職業ごとの算出方法・受け取り方法など網羅解説
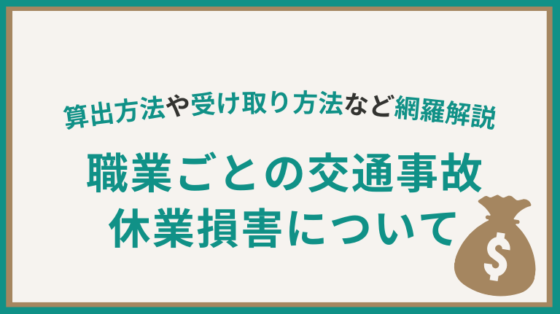
交通事故によるケガで仕事を休んだ場合にもらえるのが「休業損害」です。しかしながら、休業損害の詳しい計算方法やもらい方を熟知している方は少ないのではないでしょうか。
休業損害は、一般的には、加害者が加入している任意保険または自賠責保険から支払われます。金額の計算も保険会社がしてくれるため、「もらって終わり」になりがちな点に注意が必要です。
よくある誤解として、
・保険会社が計算した休業損害の金額が低いケースがあること
・金額が足りない場合には、別途請求できること
があります。
交通事故の休業損害について適切な金額をもらうためには、「休業損害とはどのようなものか」を正確に理解しておくことがとても大切です。
そこで今回の記事では、以下の内容を詳しく解説します。
<休業損害を請求できるのは誰?>
| ・事故に遭う前に仕事で収入を得ていた人(会社員や個人事業主、パート・アルバイトなど) ・専業主婦(主夫)などの家事従事者も請求できる |
➡詳しくは「2. 休業損害を請求できる人(給与所得者+自営業者+主婦など)」で解説。
<休業損害の適切な金額はどうやって計算するの?>
| ・「休業日数×1日あたりの基礎収入」がベース ・加害者側の保険会社が算定する場合、保険会社が独自に用意した基準を用いるため、弁護士基準と比べて大幅に低額になる可能性があるので注意 |
<休業損害の適切な金額の具体的な計算方法は?>
| (1)給与所得者(会社員・アルバイトなど)の場合 (2)自営業者・個人事業主の場合 (3)家事従事者(主婦・主夫など)の場合 (4)無職・失業者の場合 (5)学生の場合 (6)会社役員の場合 |
<休業損害の日数の考え方は?>
| ・初診日から完治または症状固定日までの間に、交通事故によるケガが理由で実際に仕事を休んだ日をカウント ・休業日数として認められるか否かは、ケガの状態や職種、治療経過などから総合的に判断される |
この記事では、記事を読んでいる方が「適切な休業損害の金額を手にできる」ことを目標に詳しく解説しています。
損しないためには、保険会社の言葉だけを鵜呑みにするのではなく、自分でも適切な金額になっているかをしっかり確認することが大切です。ぜひこの記事を参考になさってみてください。
| 休業補償(休業補償給付)と混同しやすいので注意しましょう 「休業損害」と似ている言葉で「休業補償(休業補償給付)」があります。休業補償の方は、労災保険から支払われる給付金であり、全く違うものなので、混同しないよう注意しましょう。 もしも知りたいのが「休業補償」のほうだった場合は、別記事「交通事故でも労災が使えるケースは?保険併用との順序も解説 」の記事をご覧ください。 |

この記事の監修者
弁護士 馬屋原 達矢
弁護士法人サリュ
大阪弁護士会
交通事故解決件数 900件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【著書・論文】
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【獲得した画期的判決】
【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得
【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得
【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得
【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1. 交通事故の被害者が受け取れる「休業損害」とは

休業損害とは、交通事故によるケガが原因で休業するなどして収入が減った場合に、その損害を補償するものです。事故に遭っていなければ得られたはずの収入を補償してもらうイメージです。
休業損害は加害者側に請求することができ、多くの場合は、加害者が加入している保険会社から支払われるのが一般的です。
【休業損害の概要まとめ】
| 休業損害を 請求できる人 | ・事故に遭う前に仕事で収入を得ていた人 (会社員や個人事業主、パート・アルバイトなど) ・専業主婦(主夫)などの家事従事者も請求できる ➡詳しくは「2. 休業損害を請求できる人(給与所得者+自営業者+主婦など)」で解説 |
| 休業損害の金額 | ・「休業日数×1日あたりの基礎収入」がベース ・基礎収入の出し方は、職業によって異なる ➡詳しくは「4.【職業別】休業損害の計算例(詳しい事例あり)」で解説 |
| 休業損害の日数 | ・治療のために実際に仕事を休んだ日(入院・通院・自宅療養など) ➡詳しくは「5. 休業損害の日数の考え方」で解説 |
| 休業損害の もらい方 | ・加害者側の任意保険会社から証明書の雛形をもらい、勤務先に証明書を記入してもらうのが一般的 ➡「6. 交通事故の休業損害を受け取る流れ3ステップ」で解説 |
休業損害については、「誰がもらえるのか」「金額がいくらになるか」「日数はどこまで認められるのか」など、重要なポイントがたくさんあります。
2章以降でそれぞれ詳しく解説していくので、しっかり確認して、十分な損害補償額を得られるようにしましょう。
2. 休業損害を請求できる人(給与所得者+自営業者+主婦など)

休業損害を請求できるのは、事故に遭う前に仕事で収入を得ていた人です。会社員や個人事業主、パート・アルバイトなどが該当します。
事故に遭っていなければ得られたはずの収入を補償するものなので、事故前に働いていなかった無職の方は、基本的には対象外となります。
ただし、専業主婦(主夫)などの家事従事者も休業損害を請求することができます。この場合の家事従事者とは、自分以外の同居者のために継続的に家事を専業で行っている人 です。
家事従事者の休業損害については、別記事「主婦などの家事従事者の休業損害【交通事故】相場や計算方法を解説」のもぜひ参考になさってください。
3. 休業損害の適切な金額の計算方法

休業損害として請求できる金額は、「休業日数×1日あたりの基礎収入」がベースとなります。
ただし、加害者側の任意保険会社が算定する場合、保険会社が独自に用意した基準を用いるため、弁護士が算定する場合と比べて大幅に低額になる可能性があるので注意しましょう。
過去の判例に即した適切な金額をもらいたい場合は、弁護士に相談して弁護士の算定基準で請求していくことをおすすめします。
| 自賠責基準について 休業損害の金額は上記の通り、「休業日数×1日あたりの基礎収入」をベースに計算すべきです。しかしながら、別の基準として「自賠責基準」という低い算定基準が存在します。 自賠責基準というのは、国が定めた最低限の基準で「休業日数×日額6,100円」で休業損害を計算します。 (1日の休業損害が6,100円を超えると証明できる場合は日額19,000円を上限に増額できる場合あり) 自賠責基準で算定された休業損害はあまりに低いため、もしも自賠責基準での示談を求められたら、実際の基礎収入をもって反論することをおすすめします。 |
なお、基礎収入は、事故に遭う前3カ月の給与などを基に計算するため、人によってかなり金額に差が生まれるので注意しましょう。
4.【職業別】休業損害の計算例(詳しい事例あり)

ここからは、職業別に、休業損害の基礎収入の出し方を解説していきます。
休業損害を受け取る方の職業によって算定方法がかなり異なるため、ご自分が該当する箇所の解説を読むようにしてください。
| 【職業別】休業損害の計算例 (1)給与所得者(会社員・アルバイトなど)の場合 (2)自営業者・個人事業主の場合 (3)家事従事者(主婦・主夫など)の場合 (4)無職・失業者の場合 (5)学生の場合 (6)会社役員の場合 |
それでは、職業別に詳しく解説していきます。
4-1. 給与所得者(会社員・アルバイトなど)の場合
いわゆるサラリーマンなどの給与所得者やアルバイト・パートタイマーなど、勤務先から給与を支給されている人の場合、休業損害の金額は「事故前3カ月の給与」をベースに計算します。
<給与所得者(会社員・アルバイトなど)の休業損害の計算式>
この場合の給与合計額には、基本給はもちろん各種手当や賞与も含めて計算します。また、税金や社会保険料などは差し引く前の総支給額が合計額となります。
※なお、任意保険会社が計算する場合に、1日あたりの基礎収入を「稼働日数」ではなく「暦日数(90日)で計算してくることがあります。歴日数で割ると実際よりも基礎収入が少なくなるため、休業損害の金額も低くなるので注意しましょう。
| 給与所得者(会社員・アルバイトなど)の休業損害の計算例 事故前3カ月の給与合計額が90万円、稼働日数が80日だった場合 1日あたりの基礎収入は、90万円÷80日=11,250円となります。 事故に遭ったことが原因のケガで治療・通院などをして会社を欠勤した日が20日なら 休業損害=20日×11,250円=225,000円となります。 |
ただし、給与額の変動が大きいケースなどでは、事故前1年間の給与額をもとに平均日額を計算して、それをもとに休業損害を算定する場合もあります。
「一時的に給与が減っていた」「昇給や賞与が遅れていた」など特殊な事情がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談して、因果関係を証明して相手方と交渉することをおすすめします。
4-2. 自営業者・個人事業主の場合
自営業者・個人事業主の休業損害を計算する場合は、事故に遭う前年の確定申告の所得金額をベースに計算するのが一般的です。
<自営業者・個人事業主の休業損害の計算式>
| 休業損害=休業日数×【事故前年に申告した所得金額÷365日】 |
収入ではなく所得なので、事業の収入から必要経費を除いた金額となります。確定申告の書類の「所得金額等」欄を確認しましょう。
※なお、完全に店を休業している場合には、無駄になった固定経費も追加で請求できます。この点については、任意保険会社は、低く計算してくることが多いので注意しましょう。
休業日数について任意保険会社と意見が食い違う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
| 自営業者・個人事業主の休業損害の計算例 事故前年の確定申告書に記載した所得金額が730万円だった場合 1日あたりの基礎収入は、730万円÷365日=20,000円となります。 事故に遭ったことが原因のケガで治療・通院などをして働けなかった日が20日なら 休業損害=20日×20,000円=400,000円となります。 |
もしも、前年の確定申告をしていない場合や過少申告をしていた場合は、例外的に、確定申告以外に収入や経費を立証できる資料を用意して基礎収入を証明できる場合があります。
4-3. 家事従事者(主婦・主夫など)の場合
専業主婦や専業主夫などは、家事に対する対価を実際に得ている訳ではないため、一見「休業損害はもらえないのではないか」と思われがちです。
しかしながら、他人の生活を支えるために家事をこなしている場合には、その家事について経済的な評価が可能と考えられるため、家事従事者についても休業損害が認められます。
※逆に言えば、一人暮らしで、自分が生きていくために必要な家事をこなしている場合には、休業損害は認められません。
「主婦でも休業損害が請求できるか?」については、以下のYouTube動画もぜひご覧ください。
具体的に請求できる休業損害の金額を計算する場合、基礎収入について、裁判所は女性の平均賃金を基礎として考えています。そのため、以下のような計算式で金額を算定します。
<家事従事者(主婦・主夫など)の休業損害の計算式>
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年発表している平均賃金の統計データのことです。例えば、令和5年の女性の全年齢平均賃金(年収)は399万6,500円となっています。
※家事従事者が男性の場合も、女性の全年齢平均賃金を用いて計算します。
※パートタイム収入がある兼業の場合は、実際の収入と賃金センサスを比べて、高額である方を基礎収入として使います。両方請求することはできません 。
なお、パートのお仕事に支障がないケースでは、パートのお仕事ができていたという事情から、家事の支障も少なかったと判断されることもあります。
| 家事従事者(主婦・主夫など)の休業損害の計算例 令和5年の全年齢平均賃金(年収)399万6,500円をもとに計算する場合 1日あたりの基礎収入は、399万6,500円÷365日=約10,949円となります。 事故が原因のケガで全く家事ができない状態が20日だった場合 休業損害=20日×10,949円=218,980円となります。 |
なお、家事従事者の休業日数については休業の証明ができないため、休業日数を何日とするかが争点になることがあります。自賠責基準では通院した日のみが休業日となりますが、弁護士基準で請求する場合には、ケガの程度などを考慮して休業日数を決定するのが妥当です。
事故直後はケガで家事が全くできなかったとしても、回復するにしたがって家事が徐々にできるようになっていくと判断されるためです。
最近の裁判所の判断としては、実際の被害者の症状や家事に支障が生じている程度に応じて1日あたりの金額を徐々に減らした認定をすることが多くなっています。これを一般的に「逓減(ていげん)方式」といいます。
例えば、1日あたりの基礎収入が1万円の場合、交通事故の直後で全く家事ができない日(1日~20日)までは100%、21日から40日までは75%、41日から60日までは50%、61日から80日までは25%などと計算をします。
主婦などの家事従事者の休業損害については、休業日数やケガの程度などで加害者側と意見がまとまらないことがあるため、迷うようならば弁護士に相談すると良いでしょう。
4-4. 無職・失業者の場合
無職・失業者の場合、休業損害を請求できるケースは一部に限られます。なぜならば、休業損害は、事故に遭ったことが原因で働けなくなり、収入が無くなったり下がったりした場合に請求できるという性質のものだからです。
具体的には、無職・失業者で休業損害を請求できるのは以下のようなケースに限定されます。
| 無職・失業者で休業損害を請求できるケース (1)事故の前に内定を受けていたケース (2)内定は受けていないものの求職活動中で、労働能力や意欲があり、事故がなければ仕事を得られていた可能性が高いケース |
上記のような状況である場合には、以下のように休業損害の金額を算出して請求することができます。
<内定が出ていた場合>
| 休業損害=休業日数×【内定先の年収推定額÷365日】 |
<内定が出ていないが就労の可能性が高い場合>
| 休業損害=休業日数×【将来就職する可能性が高い就職先の平均的な年収÷365日】 |
内定が出ていた場合は休業損害を認めてもらいやすい一方、内定が出ていない場合には加害者側が認めてもらえない可能性があります。
「事故に遭っていなければ就労していた可能性(蓋然性)」を表わす証拠を集めて提示する必要があるため、弁護士に相談することをおすすめします。
4-5. 学生の場合
学生の場合の休業損害は、「(1)アルバイト収入がある場合」か「(2)就職予定だった場合」に請求できます。
(1)アルバイト収入があった場合は、「4-1. 給与所得者(会社員・アルバイトなど)の場合」で示した通り、以下の計算式で算出できます。
<アルバイトをしている学生の休業損害の計算式>
| 休業損害=休業日数×【事故前3カ月の給与合計額÷稼働日数(出勤日数)】 |
(2)就職予定だった場合は、交通事故に遭ったことが原因で留年したり治療が長期化したりしたことが原因で就職の時期が遅れた場合に、以下のように休業損害を算出できます。
<内定が出ていた場合>
| 休業損害=休業日数×【内定先の年収推定額÷365日 】 |
<内定が出ていないが就労の可能性が高い場合>
| 休業損害=休業日数×【賃金センサスの平均賃金(年収)÷365日 】 |
4-6. 会社役員の場合
会社役員の場合は、報酬に労働対価以外の「利益配当分」が含まれているため、これを除いた「労働対価分」を1日あたりで計算した後、休業日数をかけて休業損害の金額を計算します 。役員報酬の減額がないケースにおいては、原則として休業損害は認められません。
<会社役員の休業損害の計算式>
| 休業損害=休業日数×【役員報酬年収-利益配当分)÷365日 】 |
ただし、役員報酬に対する「労働対価分」と「利益配当分」をいくらずつに分配するのかは、明確に決まっていないのが通常です。
そのため、個別の状況に応じて、会社の規模や、会社での役割、年齢、他の従業員との報酬差などを総合的に鑑みて判断されることになります。社外取締役や顧問などで労務提供の割合が低いと判断された場合には、休業損害が認められにくい傾向があるので注意しましょう。
会社役員は適切な休業損害の金額を判断するのが難しいため、交通事故に詳しい弁護士に相談して、因果関係を証明して相手方と交渉するのがベストでしょう。
5. 休業損害の日数の考え方

休業損害の日数は、初診日から完治または症状固定日(※)までの間に、交通事故によるケガが理由で実際に仕事を休んだ日をカウントします。有給休暇を使った場合にも、治療で仕事を休んでいればカウントして問題ありません。
| ※症状固定日とは、治療をこれ以上続けても改善の見込みがない状態であると医師が診断した日です。 |
具体的には、この期間中に、以下のような理由で仕事を休んだ日が休業日となります。
| 休業損害の日数にカウントできる日 ・ケガの治療のために、入院していた ・ケガの治療のために、医療機関に通院した ・ケガのリハビリのために医療機関に通院した ・ケガの痛みで、仕事ができなかった ・ケガの痛みで、通勤ができなかった |
ただし、休業日数として認められるか否かは、ケガの状態や職種、治療経過などから総合的に判断されます。そのため、交通事故が原因で休んだ日が全て対象になる訳ではない点に注意が必要です。原則として、医師の休業の指示が必要です。
また、休業日数は、勤務先に書いてもらった休業損害証明書の内容がベースになります。書いてもらった休業損害証明書の日数が正しいかを自分でも必ずチェックするようにしましょう。
6. 交通事故の休業損害を受け取る流れ3ステップ

ここからは、交通事故の休業損害を受け取る流れについて解説していきます。
| 交通事故の休業損害を受け取る流れ3ステップ (1)勤務先に休業損害証明書を記入してもらう (2)休業損害証明書を提出する前に内容をしっかり確認する【重要】 (3)加害者側の任意保険会社に提出して支払いを受ける |
特に2番目のステップが重要なので、しっかりと確認してみてください。
6-1. 勤務先に休業損害証明書を記入してもらう
加害者側に休業損害を請求する場合には、まず、休業したことや収入が減ったことなどの証明などを示すために、勤務先に「休業損害証明書」を記入してもらいます。
「休業損害証明書」の記入用紙は、加害者側の任意保険会社から送られてくるのが一般的です。また、保険会社の公式ホームページからダウンロードできる場合もあるので、それを勤務先に渡しましょう。
※自営業者の場合は「休業損害証明書」ではなく、資料に基づいて自分自身で休業損害の事実を証明する必要があります。交通事故の影響で仕事ができなかったことや収入が減少したことを明らかにする書類を用意しましょう。
| 補足:休業損害がもらえるタイミングについて 交通事故における休業損害は、原則としては、治療終了後または症状固定後に請求額が確定してから請求できることになっています。 ただし、交通事故が原因で休業が必要であることが明らかであり、加害者側の任意保険会社が認める場合には、示談が成立する前に「休業損害の内払い」として支払いを受けることが可能です。 |
なお、加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険(強制保険)に請求することになります。
ただし、自賠責保険の場合には、休業損害だけを事前に内払いしてもらうのではなく、他の現在までの治療期間に対応する慰謝料なども含めて請求する流れとなります。
6-2. 休業損害証明書を提出する前に内容をしっかり確認する(重要)
勤務先に記入を依頼した「休業損害証明書」を受け取ったら、必ず被害者自身の目で内容に誤りがないかしっかり確認しましょう。
なぜならば、この証明書をベースに休業損害の金額が算出されるからです。万が一、証明書の記載に誤りがあると、適切な休業損害を受け取れない可能性があります。
下記の項目を中心に、記載されている内容に誤りがないかをしっかりと確認しましょう。
| 休業損害証明書のチェックポイント ・休業日数に誤りがないか(有給休暇を取得した場合も請求対象になるので注意) ・給与の支給状況や金額に誤りがないか ・労災保険など他の保険からの給付の有無が合っているか |
もし誤りを見つけた場合は、勤務先の担当者にお願いして、正しい内容に修正してもらいましょう。
6-3. 加害者側の任意保険会社に提出して支払いを受ける
勤務先で作成してもらった休業損害証明書の内容を確認した上で、加害者側の任意保険会社に提出します。
任意保険会社が請求に応じる場合は、休業損害証明書を提出してから1〜2週間後には振込による支払いを受けることができるでしょう。
一方で、任意保険会社の判断で支払いを拒否される可能性もあります。拒否の理由としては以下のようなものが想定されます。
| ・休業の必要性がないと判断されたケース ・主婦・主夫は減収がないため、内払いは拒否されるケース ・有給休暇のみの休業損害請求の場合に、内払いは拒否されるケース ・自営業者などで、休業損害が発生していると判断できないケース |
休業損害を拒否される場合には、治療終了または症状固定後に改めて他の損害補償金と一緒に、改めて休業損害を請求していくことになります。
7. 休業損害の金額を保険会社任せにすると損する可能性がある

よくある誤解で、任意保険会社が算出した休業損害の金額について「争う余地がない」と思い込んでいる方が多いのですが、実際には争える余地は大いにあります。
特に、会社員などの給与所得者の場合、勤務先に書いてもらった「休業損害証明書」の内容にしたがって振込がされるため、争う余地がないと考える被害者も多いかもしれません。
【任意保険会社が算出した金額について争える可能性がある項目】
| 1日あたりの基礎収入 | 1日あたりの基礎収入は「暦日数」ではなく「稼働日数」で計算すべきですが、「暦日数」で計算されていた場合、休業損害も低くなるので注意が必要です。 |
| 休業日数 | 休業日数として認める日数を減らされている可能性がありますので、しっかり確認しましょう。 |
知らないまま任意保険会社が算出した休業損害をすんなり受け入れてしまうと、後悔する羽目になりかねません。損をしないためにも、しっかり押さえておきましょう。
8. 休業損害で迷ったら弁護士に無料相談するのがおすすめ

ここまで休業損害についてのさまざまな情報をお伝えしましたが、何か迷うことがあればぜひ弁護士に無料相談することをおすすめします。
相談だけならば無料で受け付けている弁護士が多いので、活用しない手はありません。また、自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合には、費用負担なしで依頼できることが多いのでぜひ活用しましょう。
休業損害については金額の算出方法がややこしいですし、解釈の違いによって金額が異なってくるケースもあります。そして、任意保険会社はできるだけ自社に有利な算定方法で計算しようとするので、注意が必要です。
休業損害に限らず、慰謝料などのほかの項目についても同様ですが、任意保険会社からは低額な示談金を提案されることが多いことを知っておきましょう。早い段階でご相談いただければ、依頼人(交通事故被害者)の利益が最も大きくなる方法についてアドバイスすることができます。
ただし、弁護士に依頼する場合には誰でも良い訳ではありません。交通事故の示談交渉は特殊性や専門性が高いものなので、できるだけ交通事故に強い弁護士を探して依頼することが大切です。
もしもどの弁護士に依頼するか迷う場合には、解決実績2万件以上、相談料・着手金の負担なく依頼できるサリュにぜひご相談ください。
以下に、休業損害の金額について争って増額させた事例をまとめているので、ぜひこちらも参考になさってください。
| 休業損害について低い提示金額をアップさせた事例 ・事例15:役員報酬全額を基礎に休業補償と逸失利益を獲得! ・事例368:主婦の休業損害を、すべての治療期間で認められた件 ・事例355:本業の休業がなくても、副業を全休し収入が減少。訴訟手続きにより、副業の休業損害の多くを判決で勝ち得た事例 |
弁護士が交渉に入ることで、正当な「弁護士基準」の金額にアップさせられる可能性が高くなります。相談は無料なので、ぜひお気軽にご連絡ください。
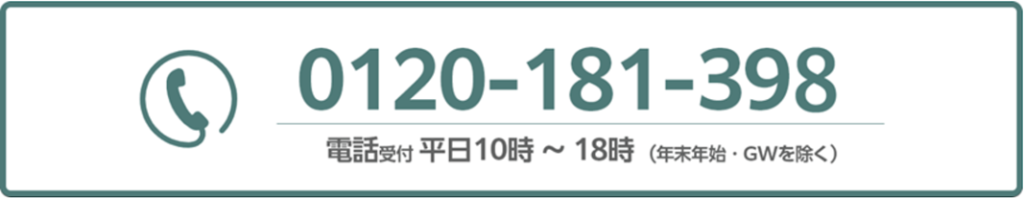
まとめ
本記事では「交通事故 休業損害」について解説してきました。
最後に、要点を簡単にまとめておきます。
▼交通事故の被害者が受け取れる「休業損害」とは
| ・交通事故によるケガが原因で休業するなどして収入が減った場合に、その損害を補償するもの ・多くの場合は、加害者が加入している保険会社から支払われる |
▼休業損害を請求できる人
| ・事故に遭う前に仕事で収入を得ていた人 ・事故前に働いていなかった無職の方は、基本的には対象外 ・ただし、専業主婦(主夫)などの家事従事者は休業損害の請求が可能 |
4章では、職業や立場別に、休業損害の金額の出し方について詳しく解説しました。
| (1)給与所得者(会社員・アルバイトなど)の場合 (2)自営業者・個人事業主の場合 (3)家事従事者(主婦・主夫など)の場合 (4)無職・失業者の場合 (5)学生の場合 (6)会社役員の場合 |
▼交通事故の休業損害を受け取る流れ3ステップ
| (1)勤務先に休業損害証明書を記入してもらう (2)休業損害証明書を提出する前に内容をしっかり確認する【重要】 (3)加害者側の任意保険会社に提出して支払いを受ける |
休業損害については、保険会社が算定した金額をそのまま受け入れてしまうと、損してしまう可能性があるので注意しましょう。
「適切な金額を受け取れているかわからない」という場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。初回相談は無料のケースが多いため、相談だけでもしてみることをおすすめします。


![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
