交通事故で脱臼|後遺障害や納得できる賠償金を得るポイントを説明
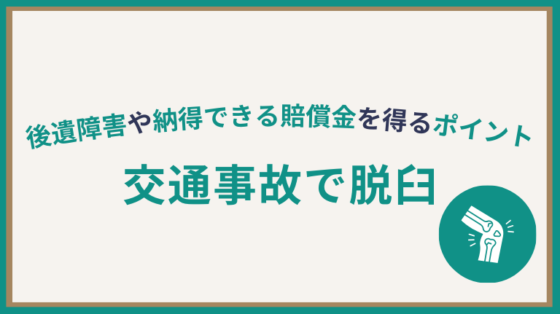
「交通事故にあって脱臼してしまった。元に戻るのだろうか…」
「肩も上がらなくなって、今までやっていた仕事はできなさそうだけど、慰謝料とかしっかりもらえるかな?」
交通事故による脱臼で、痛みやいつ治るか分からない不安が募り、これから先のことを考えるととても心配だと思います。仕事や私生活に影響が出ている分、慰謝料をしっかりと払ってもらいたいですよね。
しかし、相手の保険会社から提示される示談金は、もらえる権利のある賠償金の最低額であるケースが多いです。そうと知らずに、最低金額の賠償金しかもらえず損している方が多くいるのです。
交通事故による脱臼で正当な賠償金を得るには、以下の2つのポイントを押さえてください。
| 交通事故による脱臼で適切な賠償金を得る2つのポイント |
| ・治療は途中でやめたりせずに継続する ・交通事故の解決事例が多い弁護士に早い段階で相談する |
実際に、下記事例のように、弊所に相談をしたことで、賠償金が増額したケースは多々あります。
上記事例では、相手の保険会社からの提示金は380万円だったものの、交渉をして1471万円に増額しました。弁護士に相談することで、1091万円も賠償金がアップしたのです。
相手の保険会社の提示する示談金に対して、増額の交渉を自分で行うのは至難の業。そのため、交通事故に詳しい弁護士の力を借りることをおすすめします。
被害に見合った賠償を受けられるよう、この記事では以下のことを解説します。
| この記事で分かること |
| ・交通事故で脱臼した時に、まずあなたがすべき3つのこと ・交通事故で脱臼した時の後遺障害等級と慰謝料の目安 ・交通事故による脱臼で適切な賠償金を得る2つのポイント ・交通事故で脱臼して弁護士に相談した結果、賠償金がアップした事例 |
この記事を読むことで、納得のいく賠償を受けられ、最低限の賠償金しかもらえず後悔することがなくなります。
交通事故で脱臼して困っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の監修者
弁護士 平岡 将人
弁護士法人サリュ銀座事務所
第一東京弁護士会
交通事故解決件数 1,000件以上
(2024年1月時点)
【著書・論文】
虚像のトライアングル(幻冬舎MC・2015)
交通事故被害者を救う賠償交渉ノウハウ(株式会社レガシー・2017)
交通事故の賠償は不十分 被害者本意の仕組み作りを(週刊エコノミスト・2017.3)
後遺障害等級14級9号マスター(株式会社レガシー・2019)
交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等
【セミナー・講演】
人身傷害分野に取り組む弁護士のための医学研修(船井総研・2018)
後遺障害12級以上の世界(共同出演:株式会社レガシー・2019)
交通事故と各種保険 全3回(弁護士ドットコム・2020)等
【獲得した画期的判決】
東京高裁平成28年1月20日判決(一審:さいたま地裁平成27年3月20日判決)
「障がい者の事故被害救済」 日本経済新聞夕刊 掲載日2015年4月8日(許諾番号30040811)
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1.交通事故で脱臼したときにあなたがすべきこと
交通事故にあって脱臼になってしまった場合、これからどうすればよいか分からなくなってしまいますよね。
痛みもあるし、無事に治るのか・仕事や生活はどうなるのかなど不安がたくさん募っていると思います。
しかし、冒頭でも述べたように事故にあった後の行動次第で、脱臼の治り具合や慰謝料の額は大きく変わります。
この章では、交通事故で脱臼になってしまった場合に、まずあなたが何をすればよいかを解説しますので、一緒に確認していきましょう。
交通事故で脱臼したときに、まずあなたがすべきことは以下の3つです。
| 交通事故で脱臼したときに、あなたがすべき3つのこと |
| ・後遺障害認定を受けるために治療開始直後に適切な検査を受ける ・患部を固定した状態で3~6週間、治療で3~6ヶ月ほど病院に通う(手術の場合は約6ヶ月) ・治療完了もしくは症状固定になったら加害者に損害賠償金を請求する |
それぞれ解説していきますね。
1-1.後遺障害認定を受けるために治療開始直後に適切な検査を受ける
事故に遭って脱臼した場合、すぐに病院を診察し、治療開始直後に適切な検査(レントゲン・MRI・CTなど)を受けましょう。
検査を受けていないと、適切な後遺障害の等級を認められなかったり、すぐに病院に行かないと交通事故による脱臼だと認められなかったりするケースもあるからです。
また、検査をうけていると、相手の保険会社から提示された賠償金に納得がいかず交渉する際に、証拠として重要になります。
例えば以下の事例では、適切な検査を受けていたことで、賠償金が増額しました。
| 【適切な検査を受けていたことで、賠償金が増額した事例】 Aさんは、交通事故にあい左足大腿骨頚部骨折、右肩鎖関節亜脱臼等の重傷を負いました。 相手側の任意保険会社を通じて申請した後遺障害認定の結果は、納得のいく等級ではなく、異議申し立てをすることにしました。 医師に診断書を書いてもらい、検査結果などと一緒に異議申し立てを行うと、後遺障害等級が変更され、賠償金もアップしました。 |
このように、検査を受けていると、後遺障害の認定や等級の変更、賠償金の増額などを求めていく際の重要な証拠となります。治療を受けつつ、早めに適切な検査を受けられるように医師と話し合いましょう。
医師によっては「検査は必要ない」と判断する方もいますが、必ず検査を受けてください。
特に、肩の脱臼の場合、医師によって整復してもらい、見た目上は良くなったとしても、靭帯や関節唇を損傷している場合があります。これはレントゲンだけではわからず、MRIの撮影をすることで明らかになります。
そのため、早期にMRIの撮影をするようにしましょう。
また、後遺障害認定などを受ける際には、正常な肩との比較が有効ですので、検査を受ける際は可能な限り左右両方とも撮るようにしましょう。
1-2.患部を固定した状態で3~6週間、治療で1〜6ヶ月ほど病院に通う。手術の場合は6ヶ月ほど
では、交通事故で脱臼してしまった場合、治療はどれくらい続くのでしょうか。
脱臼の治療は、保存的治療(装具やギプス固定による治療)または手術療法のどちらかの方法で治療していきます。症状の重さなどによって総合的に判断されます。
治療方法・治療期間のおおよその目安は以下になります。
【脱臼の主な治療方法と治療期間】
| 主に行われる治療方法 | 治療期間 |
| 保存的治療 整復(手で骨を元の場所に戻す)→患部の固定→リハビリ | ・整復→患部の固定(約3~6週間) ・リハビリ(約3~6ヶ月) |
| 手術療法 手術→患部の固定→リハビリ | ・手術→患部の固定(約3週間) ・リハビリ(約6ヶ月〜) |
ただし、こちらはあくまで目安であり、損傷の状態によって治療内容や治療期間は変わります。医師と相談しながら治療を進めてくださいね。
また、「3-1.治療は途中で辞めたりせずに継続する」にて詳しく解説しますが、治療を途中で辞めてしまうと、正当な賠償金が受けとれなくなる可能性があります。
医師から「完治」または「症状固定(これ以上の回復は見込めない)」と判断されるまで、勝手に治療を辞めずに、頑張って治療を続けてくださいね。
| 症状固定の時期は慎重に! |
| これ以上治療を続けても症状が回復しないことを「症状固定」といいます。症状固定と判断されたあとに、まだ残っている症状について一定の要件を果たすと「後遺障害」に認定されます。 後遺障害に認定されるかどうかによって、損害賠償金の額も大きく変わる重要なポイントです。 この「症状固定」の時期は慎重に決定しましょう。症状固定が早すぎると回復できる損傷も回復されず、後遺障害が認定されない可能性があります。 適切な後遺障害認定を受けたい場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談しましょう。 |
1-3.治療完了もしくは症状固定(後遺症が残った)になったら加害者に損害賠償金を請求する
治療を続け、治療完了もしくは症状固定(これ以上治療を続けても改善は見込めない状態)になったら、加害者に損害賠償金を請求します。
損害賠償金には、以下のようにさまざまなものが含まれます。
| 【損害賠償金に含まれるもの】 ・慰謝料(入院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料) ・積極損害(治療費、器具装具費、通院交通費など) ・消極損害(休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益) ・物的損害(車両の修理費、車両の買い替え費用、評価損、代車費用、休車損害など) |
ただし、怪我に関して、相手側の保険会社が提示する賠償金は、自賠責保険基準と変わらず、安い場合が多いので注意しましょう。
弁護士に相談することで、賠償金がアップする可能性があります。
2.交通事故で脱臼したときの後遺障害等級と慰謝料の目安
前章で、交通事故に遭った際にまず何をすればよいのか分かったのではないでしょうか。
「1-3.治療完了もしくは症状固定(後遺症が残った)になったら加害者に損害賠償金を請求する」にて少し述べましたが、賠償金の中には、後遺障害に認定された場合の慰謝料や、逸失利益も含まれます。
後遺障害に認定されるかどうかで賠償金の額も変わってくるので、「自分のケガは後遺障害と認定されるのか」「自分は後遺障害の等級は何になるのか」気になりますよね。
この章では、交通事故で脱臼した際の後遺障害等級の目安について解説します。
脱臼した場合の後遺障害には、下記の3つがあります。
【脱臼による後遺障害】
| ・機能障害:関節が動かしにくい ・変形障害:骨が変形した ・神経障害:痛みなどの神経症状が残った |
それぞれ解説していきます。
2-1.機能障害:関節が動かしにくい場合
機能障害とは、肩が全く動かない・負傷していない肩に比べて動かなくなる状態のことです。
後遺障害の等級と慰謝料の目安は以下になります。負傷していない肩と比べてどれくらい動かないかによって、等級が変わります。
【脱臼の機能障害の後遺障害等級と慰謝料目安】
| 後遺障害等級 | 慰謝料目安 | 症状・状態 |
| 8級6号 | 830万円 | ・肩がまったく動かない ・負傷していない肩と比べて、可動域が10%以下しか動かない |
| 10級10号 | 550万円 | ・負傷していない肩と比べて、2分の1以下しか動かない |
| 12級6号 | 290万円 | ・負傷していない肩と比べて、4分の3以下しか動かない |
2-2.変形障害:骨が変形した場合
変形障害とは、正常な場合と比べて、骨が変形してしまった状態のことです。
後遺障害の等級と慰謝料の目安は以下になります。レントゲンではなく、目で見て変形していると分かる場合に、認定されます。
【脱臼の変形障害の後遺障害等級と慰謝料目安】
| 後遺障害等級 | 慰謝料目安 | 症状・状態 |
| 12級5号 | 290万円 | ・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨に変形を残すもの ※レントゲン上ではなく、裸体になった時の外見で変形がわかるもの |
2-3.神経障害:痛みなどの神経症状が残った場合
神経障害とは、ケガをした部位に痛みやしびれなどが残った状態のことです。
痛みやしびれは、見た目では分からないため、他人が認知するのは難しいですが、検査結果などの証拠を踏まえて判断されます。
後遺障害の等級と慰謝料の目安は以下になります。
【脱臼の神経障害の後遺障害等級と慰謝料目安】
| 後遺障害等級 | 慰謝料目安 | 症状・状態 |
| 12級13号 | 290万円 | ・レントゲンなどの画像検査で異常が確認でき、痛みとの因果関係が医学的に証明できる場合に認定される |
| 14級9号 | 110万円 | ・画像検査で異常は見られないが、事故の状態や症状などを踏まえて医学的に説明・推定ができる場合に認定される ※患者さん本人が自覚されていない場合があり、見逃されやすいので注意 |
2-4. 補足:後遺障害が等級に該当しない場合はどうするの?
後遺障害等級の表に該当しない症状でも、その等級と同水準の障害の場合は、「相当等級」として認められるケースがあります。
主に、労災保険で準用として扱っている症状などが「相当等級」に該当します。
【後遺障害等級の症状に該当しなくても相当等級と認められる症状】
| 障害 | 相当等級 |
| 上肢の動揺関節 (靱帯損傷などにより関節の安定性がなくなり、関節が正常時より大きく可働したり、異常な方向に動くようになったもの) | 10級相当・12級相当 |
| 上肢の習慣性脱臼 (一度脱臼をしてしまい、その後脱臼を繰り返してしまうこと) | 12級相当 |
| 下肢の動揺関節 (靱帯損傷などにより関節の安定性がなくなり、関節が正常時より大きく可働したり、異常な方向に動くようになったもの) | 8級相当・10級相当・12級相当 |
| 下肢の習慣性脱臼 (一度脱臼をしてしまい、その後脱臼を繰り返してしまうこと) | 12級相当 |
上記の様な相当等級に認定された場合、その等級と同水準の賠償請求ができるので、ご安心ください。
| 交通事故の損害賠償金について詳しく知りたい方は |
| こちらで紹介したのは、交通事故による脱臼の後遺障害等級とその等級による後遺障害慰謝料の目安のみです。 損害賠償金は、後遺障害慰謝料のほかにも、入院慰謝料や通院慰謝料、逸失利益などさまざまな要素が含まれています。 |
また、適切な後遺障害に認定されるためにすべきことは以下の記事にて解説していますので、併せてチェックしてみてください。

3.交通事故による脱臼で適切な賠償金を得るポイント
ここまでで、自分はおおよそどれくらいの等級にあたるのか、賠償金のおおよその目安が分かったのではないでしょうか。
前述しましたが、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準により、もらえる賠償金の額は大きく変わります。
この章では、交通事故による脱臼で適切な賠償金を得るポイントについて解説していきます。もらえる権利のある賠償金をしっかり獲得できるように、確認していきましょう。
適切な賠償金を得るポイントは、以下のとおりです。
| 交通事故による脱臼で適切な賠償金を得るポイント |
| ・治療は途中で辞めたりせずに継続する ・交通事故の解決事例が多い弁護士に早い段階で相談する |
それぞれ見ていきましょう。
3-1.治療は途中で辞めたりせずに継続する
まずは、症状が完治または症状固定するまで、治療を続けましょう。
治療を途中で辞めてしまったり、適切な頻度で治療を受けていないと、後遺障害に認定されない場合もあるからです。
例えば、以下のケースでは、適切な治療を受けていないために、後遺障害と認定されませんでした。
【適切な治療を受けておらず、後遺障害に認定されなかった事例】
| Aさんは交通事故で脱臼になりました。事故後の診察は病院で受けましたが、途中から病院に行かず、自分の判断で近くの整骨院にいってケアしてもらっていました。 これ以上ケアしてもらってもよくならなそうなので、後遺障害の認定を受けるために、病院に行って、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しました。 しかし、医師は、Aさんの整骨院でのケアは適切な治療であるとはいえないため、後遺障害診断書の作成を断わりました。 病院での適切な治療を受けていなかったAさんは、脱臼は治っていませんが、後遺障害と認定されませんでした。 |
このように、医師の言うとおりに治療を続けなかったり、途中で治療を辞めてしまうと、後遺障害と認定されません。
被害に見合った賠償金を得られるよう、治療を途中でやめたりせず、頑張って継続してくださいね。
また、相手の保険会社から治療費の打ち切りや症状固定の時期を指定される場合もありますが、それは気にしないようにしましょう。交通事故での治療が終わるのは、医師から「完治」または「症状固定」と診断されるタイミングです。
医師から「完治」か「症状固定」と判断されるまでは、必ず治療を続けてください。

3-2.交通事故の解決事例が多い弁護士に早い段階で相談する
交通事故の解決事例が多い弁護士に、早い段階で相談することも重要です。
| 交通事故の解決事例が多い弁護士に相談した方がいい理由 |
| 【理由①】加害者側の保険会社が提示する示談金は最低金額のことが多いため 【理由②】後遺障害の評価に関する専門知識を有していない医師もいるため |
それぞれ解説していきますね。
3-2-1.【理由①】加害者側の保険会社が提示する示談金は最低金額のことが多いため
冒頭でも述べたように、相手の保険会社から提示される示談金は、最低金額であることが多いです。
保険金は、自賠責保険基準→任意保険基準→弁護士基準の順に高くなっていきます。相手の保険会社は少しでも補償金額を抑えられたほうがいいため、一番補償額の低い自賠責保険基準の額であるケースが多いのです。
弊所に相談に来た以下の事例でも、相手の保険会社が提示した自賠責基準から、弁護士基準で交渉したことで賠償金が大きくアップしました。
【自賠責基準と弁護士基準の差】
相手から納得のいかない金額を提示された場合、専門知識がなかったら、その金額から覆すのは難しいですよね。
交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、専門知識と経験から交渉を行ってくれるため、賠償金も高くなるケースが多いのです。
3-2-2.【理由②】後遺障害の評価に関する専門知識を有していない医師もいるため
2つ目に、後遺障害の評価に関する専門知識を有していない医師もいるためです。
医師は医療のプロですが、後遺障害認定のプロではありません。そのため、後遺障害の認定を受けるための適切な診察・検査でなかったり、後遺障害診断書に抜け漏れがあったりするケースがあるのです。
例えば、以下の事例では、医師に書いてもらう後遺障害認定書に記載漏れがありました。
| 【事故とケガの状況】 ・Bさんはバイクで走行中、交差点から飛び出してきた乗用車と接触し、転倒・左足首の脱臼開放性粉砕骨折と左腓骨の開放性粉砕骨折の重傷を負った ・約6ヶ月間にわたり、治療を続けたが、左足首には可動域制限が残った |
| 【弁護士に依頼した結果】 主治医が当初書いた後遺障害診断書には、怪我を負った際に生じた傷痕に関しては、記載していませんでした。しかし、傷痕も大きさによっては、後遺障害として評価を受けられます。そこでサリュでは、主治医と面談をし、後遺障害診断書に傷痕の記載もしてもらいました。 その結果、左足首の可動域制限で10級、怪我を負った際の傷痕が醜状障害として12級と評価され、併合9級が認定されました。 サリュは、認定された後遺障害等級を基に、相手の保険会社と示談交渉に入り、休業損害や、慰謝料、逸失利益など約2600万円で示談をまとめることができました。 |
弁護士法人サリュ「事例150」
このように、医師に書いてもらう後遺障害診断書に書いてある内容が、後遺障害認定のための100%正しい診断書であるとは限りません。
交通事故に詳しい弁護士に相談すると、ふさわしい治療や検査のアドバイスをもらえ、診断書の確認や医師への面談も行ってくれます。
適切な後遺障害認定を受けて、納得のいく賠償金を得るには、交通事故の解決事例の多い弁護士に相談することをおすすめします。
4.【ケース別】交通事故で脱臼して弁護士に相談した結果、慰謝料が増額した事例
ここまでで、交通事故にあった際に適切な行動をすることで、賠償金の額は大きく変わることをお分かりいただけたでしょうか。
この章では、交通事故で脱臼した際に、弁護士に依頼した場合の慰謝料はどれくらい変わるのか、実際の事例を紹介します。
| 【事例1】後遺障害等級に異議申し立てを行い等級変更。賠償金も増額したケース 【事例2】相手は自転車で自賠責保険や任意保険がない!しかし100%の賠償金を取得したケース 【事例3】等級は変わらないが、逸失利益の主張で賠償金が増額したケース |
それぞれ見ていきましょう。
4-1.【事例1】後遺障害等級に異議申し立てを行い等級変更。賠償金も増額したケース
| 賠償金 | 約3300万円 |
| 後遺症の有無 | あり:併合9級 |
| 治療期間 | 2年間のリハビリ |
| ケガの状態 | 左足大腿骨頚部骨折、右肩鎖関節亜脱臼等の重傷 |
| 異議申立により等級を変更できた事例 |
| Iさん(40代男性)は、バイクを運転中に黄色信号で交差点内に直進で進入したところ、対向車線から右折してきた車と衝突し、左足大腿骨頚部骨折、右肩鎖関節亜脱臼等の重傷を負いました。Iさんは、約2年間懸命にリハビリを行いましたが、左足の股関節を人工関節に取り替え、股関節や肩関節の可動域制限等の複数の後遺症が残りました。 相手の自賠責保険会社では、股関節の可動域について10級11号が認められたものの、肩関節については14級9号の神経症状としての評価でしかなく、サリュが予測していた結果からはかけ離れたものでした。 そこでサリュは主治医と面談し、主治医からの意見書をもらい、異議申立を行いました。その結果、肩関節の可動域制限について12級6号、鎖骨の変形について12級5号が認められ、最終的に併合9級が認定されました。 最終的には裁判基準とほぼ同額である約3300万円(自賠責保険金含む)を回収しました。 |
この事例についての詳細は「事例219」をご覧ください。
4-2.【事例2】相手は自転車で自賠責保険や任意保険がない!しかし100%の賠償金を取得したケース
| 賠償金 | 約2700万円 |
| 後遺症の有無 | あり:併合10級 |
| 治療期間 | 約2年弱 |
| ケガの状態 | 左距骨開放性脱臼骨折、胸椎圧迫骨折 |
| 事例 |
| Lさん(男性・会社員)は、出勤のためバイクで国道を走っていました。ちょうど交差点に差し掛かり、青信号で発進したところ、突如、国道を横断しようとした信号無視の自転車が目の前を横切り、Lさんは避ける間もなく自転車後輪に接触し、コントロールを失ったバイクもろとも路上に転倒しました。 搬送先の病院では、左距骨開放性脱臼骨折、胸椎圧迫骨折の診断を受けました。 Lさんは、約2年弱の間、治療を続けましたが、左足には、依然として痛みが残り、曲げることもままならない状態でした。相手方は、自動車ではなく自転車だったため、自賠責保険や任意保険がなく、また、過失割合等にも争いがあったことから、Lさんは適正な賠償を受けられるか不安に思い、サリュの無料相談に来られました。 まずは、Lさんに残ってしまった症状を後遺障害として適正に評価してもらうため、Lさんが加入の保険会社に後遺障害の等級認定をしてもらいました。認定に当たっては、Lさんの症状が後遺障害としてしっかり評価を受けられるよう適切な後遺障害診断書を主治医に作成してもらいました。その結果、Lさんに残った症状は、後遺障害として併合10級が認定されました。 休業損害や、慰謝料、逸失利益などサリュの請求がほぼ認められ、最終的に約2200万円の請求が通りました。そして、その後、Lさん加入の保険会社からも、Lさんの過失分につきしっかり補償を受けられるよう案内し、約500万円の保険金の支払いを受けることができました。相手方からの賠償金と併せると、裁判をすることなく約2700万の補償を受けました。 |
この事例についての詳細は「事例212」をご覧ください。
4-3.【事例3】等級は変わらないが、逸失利益の主張で賠償金が増額したケース
| 賠償金 | 約2200万円 |
| 後遺症の有無 | あり:12級13号 |
| 治療期間 | ー |
| ケガの状態 | 左肩関節脱臼骨折 |
| 事例 |
| Aさん(49歳男性)は、自転車で走行中に、追い越しをしてきた乗用車に幅寄せをされ、パーキングメーターに衝突し、左肩関節脱臼骨折の怪我を負いました。Aさんは、サリュにいらっしゃった際に、痛みの等級である12級13号の後遺障害認定を受けていましたが、可動域制限も残っていたため、異議申立をしたいと考え、サリュに相談に来られました。 左肩の可動域制限値が認定基準には及ばず、等級は変わりませんでしたが、Aさんに残る左肩の痛みや動きづらさは相当なものでしたので、それに見合う賠償金の獲得を目指して示談交渉を開始しました。 痛みの後遺障害の逸失利益の喪失期間は、12級13号の場合は、喪失期間は10年で計算されることが多くあります。しかし、Aさんには、等級の認定は受けられなかったものの、可動域制限が残っているので、定年の67歳までの18年の喪失期間を請求していきました。 保険会社は、10年を超える喪失期間を認めない姿勢を崩しませんでしたが、粘り強く交渉した結果、16年の喪失期間で示談が成立。自賠責保険金も含めると2200万円を超える賠償金を獲得することが出来ました。 |
この事例についての詳細は「事例166」をご覧ください。
5.交通事故による脱臼は顧問ドクターのサポートが有効
ここまでで、交通事故で脱臼してしまったら何をすればよいのか、正当な賠償金を得るにはどうすればよいのかなどについて解説してきました。
医療や保険などさまざまな専門知識を持っていないと、正当な賠償金を受けとるのはなかなか難しいものです。
医師は医療のプロですが、後遺障害や交通事故の補償のプロではありません。そのため、前章の事例のように、あとで後遺障害の等級が変更されたり、賠償金が増額することもあるのです。
正当な賠償金を受けとるには、顧問ドクターがサポートしてくれる交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
交通事故に詳しい弁護士に相談すると、ふさわしい治療や検査のアドバイスをもらえ、診断書の確認なども行ってくれます。
交通事故にあって靱帯損傷をしてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人サリュにご相談ください!
「交通事故被害者の味方でありたい」という気持ちで、交通事故被害者のみの弁護を行うサリュが、あなたをフルサポートいたします!
| 弁護士法人サリュの強み |
| ・交通事故の解決実績20,000件以上 ・医療の専門知識を持つ顧問ドクターのサポートで後遺障害等級の獲得可能性アップ ・事故直後から訴訟対応までトータルサポート ・全国対応可能 |
私たちサリュは、交通事故のプロの先駆けとして業界トップクラスの実績があります。
これまでの解決実績20,000件以上、年間相談件数3000件以上の経験を元に、あなたを最後までサポートします。
脱臼してしまい、これからの生活を考えると不安でいっぱいのことと思います。正当な賠償金を受けとり、安心して生活できるように、最大限お手伝いさせていただきます。
\交通事故2万件の解決実績/
6.まとめ
いかがでしたか?
交通事故で脱臼した際に、まず何をすればいいのか、正当な賠償金を得るにはどう動けばよいのか分かったのではないでしょうか。
最後にこの記事をまとめますと
◎交通事故で脱臼した時にあなたがすべきことは
| 交通事故で脱臼したときに、あなたがすべき3つのこと |
| ・後遺障害認定を受けるために治療開始直後に適切な検査を受ける ・患部を固定した状態で3~6週間、治療で3~6ヶ月ほど病院に通う(手術の場合は約6ヶ月) ・完治もしくは症状固定になったら加害者に損害賠償金を請求する |
◎交通事故の脱臼で、正当な賠償金を得るためのポイントは
| 交通事故による脱臼で適切な賠償金を得るポイント |
| ・治療は途中で辞めたりせずに継続する ・交通事故の解説事例が多い弁護士に早い段階で相談する |
この記事を元に、適切な治療・検査をうけられ、納得のいく賠償金を得られることを願っています。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
