後遺障害2級とは?認定される症状や請求できる賠償金について解説
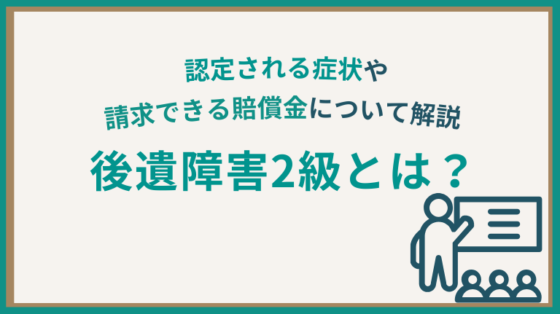
「家族に介護が必要な障害が残って後遺障害2級が認定されそう」
「後遺障害2級の認定を受けたらどうなるの?」
そのような疑問を持っていませんか?
後遺障害2級は、交通事故による怪我で以下のような症状が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級です。
【要介護】の場合
| 2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
【要介護でない】場合
| 2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
このように事故による重度の障害が残った場合に認定されるのが後遺障害2級という等級です。
しかし、このように重い障害が残り、将来の生活に大きな影響が出るにも関わらず、加害者側の保険会社に任せていると適正な金額の賠償金を受け取れない可能性があります。
なぜなら、相手は被害者やその家族に十分な知識がないことを逆手に取り、不当に低い金額で済ませようとしてくるからです。
そこでこの記事では、被害者が正当な補償を受けられるよう、後遺障害2級の認定を受けた被害者が請求できる項目やその相場に加えて、実際の獲得事例も詳しく解説します。
また、後遺障害2級に相当する障害が残った際に受けられる支援についても紹介するので、ぜひ最後までご覧いただき将来に備えた準備を行ってください。

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1.後遺障害2級が認定される症状
後遺障害2級は、介護が必要な場合とそうでない場合の2パターンに分かれます。
要介護である場合に2つの症状、要介護でない場合に4つの症状で認定される可能性のある等級です。
それぞれの症状について、詳しく解説します。
1-1.【要介護】の症状
後遺障害2級に認定される中で、介護が必要なものについては別表第1で以下の2つの症状が規定されています。
【自動車損害賠償保障法施行令別表第1】
| 2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
それぞれの症状について、詳しく見ていきましょう。
| ※同じく介護が必要な場合に認定される可能性がある1級とは、介護の必要な頻度によって異なります。 ・常に介護が必要な場合(自分で行動が一切できない)→1級 ・随時介護が必要な場合(食事や排泄などの一部の介護が必要となる)→2級 |
1-1-1.2級1号│神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
神経や脳に重篤な障害が残り、状況に応じて日常生活の動作に介護が必要な状態となった場合、介護が必要な2級1号に該当する可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・高次脳機能障害による精神障害 ・脳損傷による身体性機能障害 ・脊髄損傷による神経の機能障害などにより随時(状況によって)介護が必要になっているか |
| 認定のポイント | 上記のような症状により、食事や入浴、排泄などの生活動作が状況によって行えず、介護が必要なときがあるかどうか |
介護が必要な2級1号では、日常生活のすべてに常に介護が必要なわけではありませんが、生活の中で随時介護が必要になるため、家族や介護者によるサポートは必須となります。
1-1-2.2級2号│胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
臓器の中でも、主に呼吸器に重度の障害が残り、生活の中で状況に応じて介護が必要になった場合には介護が必要な2級2号に認定される可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・主に呼吸器に障害が残り、自力での食事や排泄、移動などが困難で、随時(状況によって)介護を必要とする |
| 認定のポイント | 血液検査や肺機能検査で以下のような条件に当てはまっている上で、状況に応じて介護が必要な場合 ・動脈血酸素分圧(PaO2)が50Torr以下 ・動脈血酸素分圧が50Torr超〜60Torr以下で、かつ動脈血炭酸ガス分圧(PaCO2)が37Torr未満または43Torr超 ・スパイロメトリー(肺機能検査)で高度な呼吸困難が見られる |
このような症状が残った場合、酸素ボンベなどを使った医療的なケアが必要になります。
1-2.【要介護でない】症状
後遺障害2級は、要介護ではない場合でも認定される可能性があります。
これらは、別表2で以下のように定められています。
【自動車損害賠償保障法施行令別表第2】
| 2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
それぞれの症状について、詳しく解説します。
1-2-1.2級1号│1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
片目の視力を失い、もう片方の視力も0.02以下に低下した場合、2級1号の認定を受けられる可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・片目を失明し、もう片方の視力※も0.02以下になった ※コンタクトや眼鏡で矯正した視力 |
| 認定のポイント | 失明は以下のようなケースで認められます ・眼球を摘出した・光の明暗が完全にわからない ・光の明暗が辛うじてわかる(暗室で光の点滅がわかる、目の前で動かした手の動きの方向がわかる) |
視力が0.02以下とはほとんど失明に近い状態で、視力に頼って生活することは非常に難しい状態です。
移動時には白杖や介助人によるサポートが必要となります。
1-2-2.2級2号│両眼の視力が0.02以下になったもの
両目の視力が0.02以下になった場合、2級1号の認定を受けられる可能性があります。
| 認定基準 | コンタクトや眼鏡で矯正した視力が両目とも0.02以下になる |
両目とも0.02以下というのは、WHO(世界保健機構)や眼科医の基準では「失明」とされることもあるほど視力が低下した状態です。
そのため、2級1号と同じく白杖や介助人によるサポートは必要となるでしょう。
1-2-3.2級3号│両上肢を手関節以上で失ったもの
両腕を手首より上で失った場合、2級3号の認定を受ける可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・ひじから手首の間で切断した・手首の橈骨、尺骨、手根骨が切り離された |
手首より先を失うことになるため、食事や筆記を自分で行うのは難しくなります。
また、着替えなどにもサポートが必要になるケースがほとんどでしょう。
義手を装着することで見た目や機能性を補うことができますが、動かすタイプの義手を使いこなすには操作の練習や慣れが必要です。
1-2-4.2級4号│両下肢を足関節以上で失ったもの
両足を足首より上で失った場合、2級4号の認定を受けられる可能性があります。
等級の認定は、以下のような基準で判断されることが多いです。
| 認定基準 | ・膝から足首の間で切断した・足首の脛骨・腓骨・距骨が切り離された |
足首より先を失ってしまうと、「立ち上がる」「歩く」などの日常動作ができなくなってしまいます。
そのため、義足や車椅子などの利用が必要になるでしょう。
| 上記に当てはまらなくても複数の症状で併合2級に認定されるケースもある |
| 後遺障害の認定では、複数の部位に障害が残った場合に「併合」という考え方が用いられます。 併合のルールは以下のとおりです。 (1)5級以上の後遺障害が2つ以上残存→重い方の等級を3つ繰り上げる (2)8級以上の後遺障害が2つ以上残存→重い方の等級を2つ繰り上げる (3)13級以上の後遺障害が2つ以上残存→重い方の等級を1つ繰り上げる このようなルールがあるため、以下のように等級が繰り上がる可能性があります。 【実際の事例】次の後遺障害の認定を受け、併合2級が認定されました ・神経、精神の障害(7級4号) ・右下肢の欠損(4級5号) ・右股関節の機能障害(10級11号) (横浜地判・平成23年5月27日) |
2.後遺障害2級に認定された被害者が受け取ることができる賠償金
前章では後遺障害2級が認定される症状を紹介してきましたが、どれも生活の介護や介助が必要になる非常に重い障害です。
このような症状が長く残り続けることを考えると、十分な賠償金を請求し、将来に備える必要があります。
交通事故の被害者が受け取ることができる賠償金は、以下のようなものになります。
この章では、後遺障害2級の認定を受けた被害者が受け取れる慰謝料と逸失利益、将来の介護費などについて詳しく解説します。
| 1.慰謝料│精神的苦痛に対する補償 2.逸失利益│将来の減収などに対する補償 3.将来の介護費 4.その他の賠償金 |
2-1.慰謝料│精神的苦痛に対する補償
慰謝料とは、交通事故による怪我によって生じた精神的苦痛を補償するものです。
後遺障害2級に認定された場合、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」を受け取ることができます。
それぞれの慰謝料について、算出の方法や相場を解説します。
| 慰謝料の計算基準の違い |
| 交通事故の慰謝料の計算基準には、以下の3種類があります。 このように、自賠責基準は最低限の算定基準です。 相手の保険会社は、この自賠責基準か、それより少し高い程度の任意保険基準で計算した慰謝料を提示するケースが多いでしょう。 しかし、被害者にとって正当だといえるのは、過去の裁判例などをもとに作られた弁護士基準で算出された金額です。 相手の保険会社から慰謝料などの提示があったときには、その金額を過信せず、必ず計算基準などの根拠を確認することが重要です。 |
2-1-1.入通院慰謝料│入院や通院による精神的苦痛への補償
入通院慰謝料は、交通事故によって入院や通院が必要になる怪我を負ってしまったことに対する補償です。
入院や通院を行った期間をもとに計算されます。
具体的な金額は、以下の表に当てはめて算出します。
※この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合、入通院期間1か月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。
(例:16か月入院した場合=340万円+(340万円-334万円)=346万円)
上記の表に当てはめると、以下のような金額が入通院慰謝料の相場となります。
| ・12か月入院した場合→321万円 ・9か月の入院後に6か月通院した場合→322万円 |
入通院慰謝料については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。
【怪我のケースで比較】交通事故の慰謝料の弁護士基準とその他の基準の差を徹底解説
2-1-2.後遺障害慰謝料│後遺障害による精神的苦痛への補償
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛への補償です。
認定された等級ごとに金額が異なり、2級の場合は以下の金額が相場となっています。
| 弁護士基準 | 自賠責基準 |
| 2370万円 |
介護を要する場合:1203万円 介護を要さない場合:998万円 |
この通り、弁護士基準と自賠責基準では倍近くの金額差が生じることになります。
保険会社は自賠責基準での後遺障害慰謝料の提示をしてくるかもしれませんが、本来はもっと高額に計算できる可能性があることを知っておいてください。
後遺障害慰謝料については以下の記事で詳しく解説しています。
後遺障害の慰謝料とは?等級ごとの相場や算定基準をわかりやすく解説
2-2.逸失利益│将来の減収などに対する補償
逸失利益とは、後遺障害の影響で仕事ができなくなったり仕事に支障が生じたりする場合に、本来であれば得られるはずだった収入を補償するものです。
後遺障害2級では、今後の働く能力が完全に失われている(労働能力喪失率100%)と判断されるのが一般的です。
逸失利益の計算は、以下の式に当てはめて行います。
| 1年あたりの基礎収入*×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数* *1年あたりの基礎収入…被害者が事故に遭う前の年収などから算出する *ライプニッツ係数…交通事故の損害などを計算するための係数。年齢で決まる。 |
たとえば、1年あたりの基礎収入400万円、30歳の男性が2級の認定を受けた場合の逸失利益は、以下のように計算されます。
| 400万円×労働能力喪失率100%×22.167=8866万8000円 |
※実際の計算式はケースによって異なります。
逸失利益は、正社員だけでなく、パートやアルバイト、自営業、家族の家事を行う主婦・主夫なども請求することが可能です。
年齢や性別ごとの後遺障害逸失利益の目安については、以下の表を参考にしてください。
各目安金額は、平均収入などをもとにした一例です。実際の金額は事例によって異なるため、詳しい金額は弁護士などにご相談ください。
【男性】
| 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 | 65歳 |
| 1億4002万 | 1億2025万 | 1億0897万 | 8180万 | 3550万 |
【女性】
| 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 | 65歳 |
| 9941万 | 8837万 | 7377万 | 5092万 | 2769万 |
| ※上記早見表では、以下を前提にしています。 【基礎収入】 25歳:男性5,908,100円・女性4,194,400円 35歳:男性5,897,800円・女性4,334,500円 45歳:男性6,837,700円・女性4,629,200円 55歳:男性7,242,100円・女性4,508,600円 65歳:男性4,162,800円・女性3,246,800円 (※令和6年の全学歴、年齢別、男女別の平均収入を前提) 【労働能力喪失率】100% 【ライプニッツ係数】労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数はこちら |
こちらの計算はあくまで例となります。
また、逸失利益についての詳しい内容は以下の記事で解説していますので、こちらも参考にしてください。
【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説
2-3.将来の介護費
後遺障害2級と認定された場合、将来的にかかると想定される介護費用も請求することが可能です。
具体的には、以下のような項目が請求の対象となります。
| ・訪問介護やデイサービスなどの介護サービス利用料 ・家族が介護する場合の日額(一般的に1日8000円) ・車椅子や義手、義足などの福祉器具の購入費用、買い替え費用 ・おむつなどの衛生用品の消耗品の購入費用 ・バリアフリー化(手すりの設置など)にかかった住宅改装費用 ・介護車両の購入や改装費用 |
また、過去の裁判例では以下のような項目が認められたケースもあります。
| 遷延性意識障害(1級3号)の母の介護を行うため、長女がホームヘルパー2級の資格を取ろうとして受講した研修費用7万8000円 | 札幌地判・平成13年8月23日 |
| 高次脳機能障害等の女性の父親が、被害者の通院のための運転免許の取得、自動車の購入を行った費用325万円のうち250万円 | 東京地判・平成15年8月28日 |
| 3級3号の男性(固定時24歳)について、被害者と付き添い家族の交通費として1人につき日額500円、平均余命54年分の122万円(2人分で合計245万円)を認めた | 名古屋地判・平成13年3月30日 |
| 右腕神経叢引き抜き損傷等(3級)の被害者が極めて専門性の高い手術を受ける必要性が認められ、豊富な症例のある山口県の病院で治療を受けた際のホテル代33万円、入院中に夫が付き添うために借りた住居の賃料35万円を認めた | 横浜地判・平成26年4月17日 |
このように、今後の生活への必要性が認められる項目については幅広く請求が可能なため、示談の前にしっかり確認しておきましょう。
2-4.その他の賠償金
ここまでに紹介した項目以外にも、賠償金として請求できる項目は多数あります。
実際に、以下のような項目は賠償の対象となります。
| 物損の損害賠償 | 車の修理費、代車やレンタカー費用、レッカー代、事故車の保管料など |
| 治療費 | 事故で負った怪我の治療に要する費用(診察料、手術費、入院費、投薬費など)。 必要かつ相当とみなされる範囲で請求可能。 |
| 通院交通費 | 治療のために通院する際に発生する交通費(公共交通機関や自家用車のガソリン代など)。 妥当な手段・理由があれば全額または相当分が請求対象。 |
| 装具・器具購入費 | 治療やリハビリに必要な装具や器具(松葉杖、コルセット、車椅子など)を購入する費用。 将来的に必要になると考えられるものも含まれる。 医師の指示や診断で必要性が認められるものが対象となる。 |
| 付添費用 | 入院・通院時に家族などが付き添うことで発生する人件費や交通費。 |
| 休業損害 | 治療や療養のために仕事を休み、得られなかった収入分に対する損害。 給与所得者は休業損害証明書、自営業者は確定申告などで証明し算定する。 詳細は以下の記事で解説 交通事故の休業損害|職業ごとの算出方法・受け取り方法など網羅解説 |
これらの費用は、これから安心して生活を続けるためにも、もれなく請求するようにしましょう。
また、このような補償について、保険会社は請求が可能であることを十分に説明しないことも考えられます。
被害者側が自ら気づいて申告しなければ支払われないこともあるため、注意してください。
3.後遺障害2級の認定を受けた場合の賠償金獲得事例
ここまで、後遺障害2級の症状や賠償金の金額の相場について説明してきました。
しかし、実際にどのくらいの賠償金が獲得できるのかイメージできないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、もっと具体的にイメージできるよう、これまで2万件以上の交通事故を解決に導いてきたサリュの解決事例の中で、後遺障害2級が認定されて納得の賠償金を獲得できた事例を3つ紹介します。
| 【ケース1】将来の介護費用を含め約1億4500万円を獲得した事例 【ケース2】保険会社や加害者の不誠実な対応に対抗し約2億円を獲得した事例 【ケース3】治療中からのサポートで将来の介護費用などを含めた金額で解決した事例 |
3-1.【ケース1】将来の介護費用を含め約1億4500万円を獲得した事例
| 事故・怪我の状況 | 原動機付自転車で走行中、側道から進入してきた自動車に衝突され、びまん性脳損傷の重症 |
| 認定を受けた症状 | 左片麻痺、高次脳機能障害の重い後遺障害が残る日常生活でも随時介護が必要な状態になったとして、後遺障害等級(要介護)2級1号が認定 |
| 獲得金額 | 約1億4500万円 |
この事故では、被害者はびまん性脳損傷の重傷を負いました。事故により左片麻痺と高次脳機能障害が残り、日常的に介護が必要な状態となったため、後遺障害等級(要介護)2級1号が認定されました。
交渉では、被害者本人の慰謝料や逸失利益に加えて、ご両親による入通院の付添や介護にかかる負担、将来的な在宅介護費、自宅改造費の損害がどこまで認められるかが争点となりました。
相手方にも弁護士が付き、特に将来の介護費用や逸失利益については大幅な減額を求められる厳しい交渉となりました。
サリュでは、後遺障害等級の認定前から被害者をサポートし、適切な準備とアドバイスにより適切な等級認定を実現。
さらに、成年後見制度の活用も提案・支援し、介護体制や費用の将来見通しも踏まえて主張を組み立て、訴訟を回避しながら最大限の補償を引き出すため粘り強く交渉を続けました。
その結果、被害者は自賠責保険金を含めて総額約1億4500万円の示談金を獲得。
長期にわたる支援により、ご本人とご家族にとって納得のいくかたちでの解決を実現できました。
3-2.【ケース2】保険会社や加害者の不誠実な対応に対抗し約2億円を獲得した事例
| 事故・怪我の状況 | 青信号に従いバイクを発進させたところ、進行道路と交差する道路から赤信号を無視した自動車が出てきて衝突。頭蓋骨骨折、びまん性軸索損傷、脊髄損傷、内蔵損傷等の重傷 |
| 認定を受けた症状 | 高次脳機能障害及び脊髄損傷後の各症状等で併合2級 |
| 獲得金額 | 約2億円 |
被害者(20代男性)は通勤中、青信号でバイクを発進した直後に、赤信号を無視して交差点に進入してきた自動車に衝突されました。
頭部や脊髄に重い損傷を負い、一時は意識不明の重体に。目を覚ました後も、高次脳機能障害や下半身の麻痺が残り、日常生活には全面的な介助が必要となりました。
事故後、当初は休業損害の支払いがありましたが、次第に保険会社からの対応が滞りはじめ、サリュへ相談に来られました。
訴訟では、加害者が被害者に過失があったと主張しており、刑事記録にも不利な内容が残されていたため、過失割合が大きな争点となりました。
サリュでは、刑事記録や目撃証言を丁寧に検証し、加害者の虚偽供述に反論しました。
また、裁判中には配偶者の思いを直接伝える場が設けられ、裁判官の心証にも影響を与えました。
その結果、被害者は自賠責保険金を含めて総額約2億円で和解。サリュは約4年半にわたり、被害者とそのご家族に寄り添い、厳しい状況の中でも希望を持てる解決を実現しました。
3-3.【ケース3】治療中からのサポートで将来の介護費用などを含めた金額で解決した事例
| 事故・怪我の状況 | 横断歩道を青信号で横断中、強引に交差点に進入してきたトラックに轢かれ、意識不明の重体 |
| 認定を受けた症状 | 左足大腿部の切断、脳挫傷による高次脳機能障害及び眼球運動障害(複視:物が二重に見える状態)などで併合2級 |
| 獲得金額 | 将来の介護費用や車椅子の費用を含めた金額 |
被害者(80代・主婦)は、青信号で横断歩道を渡っていた際、交差点に強引に進入してきたトラックに衝突され、意識不明の重体となりました。
一命はとりとめたものの、左足大腿部の切断、高次脳機能障害、複視などの重い後遺障害が残る見込みとなりました。
事故後、ご家族は住まいや介護の問題、保険会社への不信感、将来への不安を抱える中で、サリュに相談。
サリュは、入院中から転居費用等の先払い交渉を行い、生活環境の変化に対応。自宅での生活が困難となった被害者の介護施設入居に伴う支援も行いました。
治療終了後は、後遺障害申請に向けて診断書作成の助言や、ご家族とともに陳述書を作成するなど丁寧な準備を重ね、併合2級の認定を獲得しました。
また、判断能力の低下により成年後見制度の利用が必要となったため、家庭裁判所への申立てもサポートし、ご家族が後見人に就任されました。
その後の示談交渉では、慰謝料に加え、将来の介護費用や車椅子費用なども含めた内容で和解が成立。
ご家族からは「事故のストレスから解放され、少し元気を取り戻しました」とのお言葉とお礼のお手紙をいただきました。
4.後遺障害2級に該当する症状が残った場合に受けられるその他の支援
後遺障害2級に認定されるような重度の障害が残った場合には、加害者からの賠償だけでなく、公的な支援を受けられる可能性があります。
ここでは、主に利用できる可能性のある4つの制度について解説します。
| 1.障害者手帳の交付 2.障害年金 3.労災保険(業務中や通勤途中の事故の場合) 4.その他 |
4-1.障害者手帳の交付
後遺障害2級に該当する障害では、障害者手帳(身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳など)の交付対象となる可能性が高いでしょう。
障害者手帳には後遺障害の等級とは異なる等級の認定があります。
障害者手帳では、障害の症状や程度に応じて1~7級などの等級が決められ、中でも1級・2級になると重度の障害であることから、手厚い支援を受けられる傾向にあります。
具体的な等級は障害の内容や程度によって異なるため、詳しくはお住いの市町村の障害者福祉担当の窓口にお問い合わせください。
| 申請先 | お住まいの市町村の障害者福祉担当窓口 |
| 必要なもの | 医師の診断書・意見書、障害を証明するものなど |
| 受けられる支援 | ・所得税や住民税の控除 ・公共交通機関の運賃割引 ・医療費助成 ・福祉用具の給付や貸与 ・住宅改修費の助成 など |
4-2.障害年金
重い後遺障害が残った場合は、国民年金や厚生年金から「障害年金」を受け取ることができる可能性があります。
障害年金では、障害の程度に応じて1級・2級などの等級が決められ、それぞれに応じた金額が支払われます。
ただし、後遺障害の等級と障害年金の等級は基準が異なります。
「後遺障害2級だから障害年金も2級になる」というわけではないので、注意が必要です。
【障害基礎年金】
| 障害の程度1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない |
| 障害の程度2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない |
障害年金の年金額は、加入している年金が「国民年金」か「厚生年金」かによって異なります。
ここでは、国民年金の場合の金額の例を紹介します。
【障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)】
1級
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 1,039,625円 + 子の加算額※ |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,036,625円 + 子の加算額※ |
2級
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 831,700円 + 子の加算額※ |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 829,300円 + 子の加算額※ |
※子の加算額
| 2人まで | 1人につき239,300円 |
| 3人目以降 | 1人につき79,800円 |
子の有無によって異なりますが、月額約7万円〜10万円程度の支給となります。
厚生年金に加入していた場合は、上記に追加して報酬比例分(収入に応じた金額)が追加されるイメージです。
4-3.労災保険(業務中や通勤途中の事故の場合)
仕事中や通勤途中に発生した交通事故で怪我をして後遺障害が残った場合、労災保険の対象となります。
労災保険では、以下のような項目が請求可能です。
| 療養補償給付 | 勤務中・通勤中の負傷または疾病で、療養を必要とする場合にもらえる給付 |
| 休業補償給付 | 勤務中・通勤中の負傷または疾病が原因で、働けなくなり、賃金を得ることができなかった場合(または減額された場合)にもらえる給付 |
| 障害補償給付 | 勤務中・通勤中の負傷または疾病が治癒した後に、一定の障害が残った場合にもらえる給付 |
| 傷病補償等年金 | 勤務中・通勤中の疾病が1年6カ月を経過しても治癒せず、その程度が「傷病等級」に該当する場合に支給 |
| 介護補償給付 | 障害補償年金または傷病補償年金受給者のうち、特定の状態に該当し、介護を受けている場合に支給される給付 |
労災保険と任意保険(自賠責保険)は併用可能です。
労災保険については以下の記事で詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。
4-4.その他
その他、重度の障害が残ってしまった場合には、以下のような支援を受けられる可能性があります。
【各自治体の福祉サービス】
| 申請先 | お住まいの市町村の障害者福祉担当窓口など |
| 受けられる支援 | ・訪問介護や介護施設の利用料の給付 ・障害の重度に応じた手当 など |
※自治体によって受けられる支援の内容や金額は異なります
【ナスバによる介護料の支給】
| 申請先 | 独立行政法人自動車事故対策機構 ナスバ 各支部 |
ナスバとは独立行政法人自動車事故対策機構の略称で、自動車事故の防止や被害者の支援を行っている機関です。
ナスバでは、交通事故によって要介護になった場合、以下のような給付を受けられます。
| 最重度 特1種 | 月額85,310 円(下限額)~211,530 円(上限額) |
| 常時要介護 1種 | 月額72,990 円(下限額)~166,950 円(上限額) |
| 随時要介護 2種 | 月額36,500 円(下限額)~83,480 円(上限額) |
※労災保険の介護給付等との併給は不可
これらの支援は自分で調べなければ対象であることに気が付かず、支給を受けられないこともあります。
障害に対するサポートについては、地域の福祉担当窓口などで相談してみてください。
5.後遺障害2級に認定されても将来の介護費や支出を軽視され、十分な補償を受けられない可能性がある
後遺障害2級は、日常生活に常時介助が必要なほど重い障害です。
それにもかかわらず、保険会社との交渉次第では十分な補償を受けられないおそれがあります。
なぜなら、保険会社は自社が支払う賠償金を最低限に抑えるため、以下のような手法で賠償金を低く計算しようとするからです。
| ・将来の介護やケアに必要な金額を低く計算する ・健康保険適用前提で提示してくる(本来は自由診療ベースであるべき) ・請求できるはずの項目について提示しない ・逸失利益などを低く計算する |
実際に、先ほど紹介した3-1.【ケース1】将来の介護費用を含め約1億4500万円を獲得した事例でも、保険会社は弁護士を付けた上で、「将来の介護費用や逸失利益についての大幅な減額」を求めてきました。
こちらの事例ではサリュの粘り強い交渉で納得できる金額になったものの、相手の言いなりになっていたら大幅に削られていた可能性もあります。
このように、後遺障害2級という重い障害が残ったにも関わらず、適正な金額の賠償金を得られないリスクがあることを知っておいてください。
6.後遺障害2級の適正な賠償金を獲得するために弁護士が力になれる
「手足を失ってしまった」「介護がないと食事や着替えもままならない」
そんな重い障害が残ってしまった被害者に対する適正な賠償金を獲得するためには、弁護士への相談が重要です。
なぜなら、前章でも述べた通り、相手方の保険会社は被害者に最大限の補償をすることよりも、自社の支払額を抑えることを優先する傾向があるからです。
専門知識がない状態で提示された金額が適切かどうかを見極めるのは非常に難しく、結果として大幅に低い金額で妥協してしまう可能性があります。
弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けることができます。
| ・保険会社の提示金額が適正かどうかを過去の似た事例などと比較して判断してくれる ・将来の介護費用などが漏れなく算定されているか確認してくれる ・相手の主張に矛盾や問題がないか確認してくれる |
また、正式に依頼をすれば、相手の保険会社との交渉も弁護士が代わりに進めてくれるため、相手に有利な条件で一方的に進められるようなことを防げます。
本当に相手の出した条件が適正なのかを確認するためにも、弁護士に相談しておきましょう。
7.後遺障害2級の賠償金が本当に適正か悩んだらサリュにご相談ください
「相手の保険会社が提示してきた条件をそのまま受け入れていいのかわからない」
そんな不安が少しでもある方は、まずはサリュにご相談ください。
サリュは、これまで2万件以上の交通事故案件を、被害者に寄り添って解決してきた法律事務所です。
被害者の方やそのご家族が納得して事故解決を迎え、安心して将来に歩み出せるよう、さまざまなサポートを行っています。
後遺障害2級の賠償金に悩んだ方に相談していただきたい理由は、以下の3点にあります。
| 1.相手が提示する金額が適正かどうか判断できるから 2.ノウハウ豊富な弁護士が対応できるから 3.事故解決まで被害者とご家族をフルサポートするから |
7-1.相手が提示する金額が適正かどうか判断できるから
1つ目の理由は、相手が提示する金額が適正かどうか再計算できるからです。
5.後遺障害2級に認定されても将来の介護や支出を軽視され、十分な補償を受けられない可能性があるでも説明したとおり、後遺障害2級という重い障害が残っても、相手の保険会社は適正な金額を提示するとは限りません。
むしろ、極力支払い金額を減らすため、不当に低くなるような計算を行っているケースも多いのです。
サリュでは、ご相談いただいた段階で相手が提示する金額が適正なものかどうかを再計算し、項目の漏れや計算が低くなっているところをお伝えします。
また、ご依頼いただければサリュが行った再計算した金額をもとに、相手との交渉を行います。
このように、適正な金額であるかを改めて確認できるのがサリュにご相談いただきたい1つ目の理由です。
7-2.ノウハウ豊富な弁護士が対応できるから
ノウハウ豊富な弁護士が相手との対応を行えることも、サリュにご依頼いただきたい理由です。
交通事故対応では、弁護士のノウハウや交渉力によって結果が変わってしまうケースが数多くあります。
なぜなら、交通事故は個別のケースによって必要な対応が異なるため、対応力が問われ、十分な知識や経験がないと思うような結果が出せないからです。
サリュには、これまでの交通事故解決実績1000件以上のベテラン弁護士が多数在籍しています。
また、充実した教育体制も整えているので、スキルの高い弁護士が揃っているのです。
このようなノウハウ豊富な弁護士が対応できるのが、サリュの大きな強みとなります。
7-3.事故解決まで被害者とご家族をフルサポートするから
最後の理由は、事故解決まで被害者とご家族をフルサポートできるからです。
交通事故後は、加害者側との交渉が必要になりますが、治療やリハビリを続けながら証拠を収集し、相手と対等に交渉する準備を整えるのは非常に大変です。
そこで、サリュでは相手との交渉や証拠の収集だけでなく、後遺障害の認定や訴訟になった際の対応など、被害者とそのご家族をフルサポートしています。
安心して治療を続け、将来のための賠償金を獲得するためにも、ぜひサリュにご相談ください。
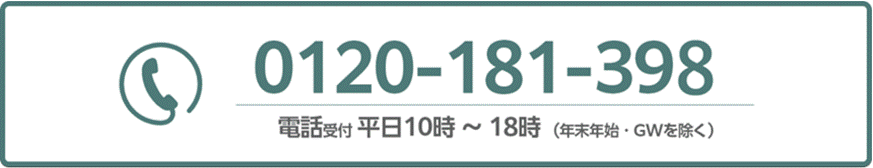
メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。
8.まとめ
この記事では、後遺障害2級について解説しました。
内容のまとめは以下のとおりです。
▼後遺障害2級は、交通事故による怪我で以下のような症状が残った場合に認定される可能性がある
【要介護】の場合
| 2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
【要介護でない】場合
| 2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
▼後遺障害2級に認定された場合に受け取れる賠償金は以下のとおり
▼後遺障害2級の認定を受ける後遺障害が残った場合、加害者からの賠償のほか、障害者手帳の交付や障害年金、労災保険などの給付を受けられる可能性がある
▼適正な賠償を獲得するためには、弁護士への相談・依頼が重要
これらの内容を参考にして、症状に応じた適正な後遺障害の認定と賠償金獲得に向けて行動してください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
