聴覚障害の等級を症状別に解説|適正な等級認定に向けやるべきこと
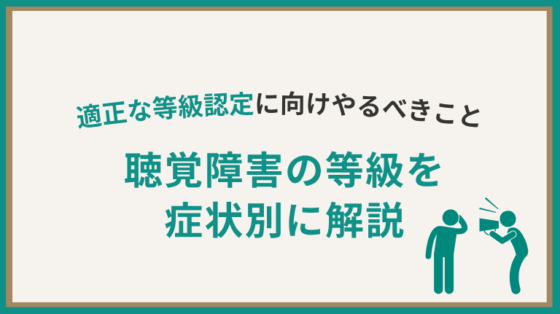
「聴覚障害になってしまった。自分の症状だと後遺障害等級何級になる?」
このように、事故による怪我が原因で聴覚障害が残ってしまい、後遺障害等級が何級になるのか気になっていませんか?
後遺障害等級とは、後遺障害の重さのことで、一番重い第1級から第14級まであります。
聴覚障害が該当するのは、4~14級です。
聴覚障害が残ってしまったあなたにとって大事なのは、あなたの症状に見合う正当な等級を認めてもらうことです。
どのような症状が現れているのかによって、認められる可能性がある等級が変わります。
| 状況 | 認定される可能性がある後遺障害等級 |
| 両耳に聴覚障害がある | 4級、6級、7級、9級、10級、11級 |
| 片耳のみに聴覚障害がある | 9級、10級、11級、14級 |
| 聴覚障害に伴って耳鳴りがある | 12級、14級 |
しかし、聴覚障害が残ったにもかかわらず、後遺障害非該当となったり不当に低い等級が認定されたりするケースがあることを、ご存じでしょうか。
例えば、AさんとBさんで同じ聴覚障害の症状があるのに、Aさんは10級、Bさんは11級が認定されるケースもあるということです。
等級が一つ変われば、慰謝料を含む賠償金は大きく変わります。
もし不当な等級が認定されれば、本来受け取れるお金を受け取れなくなったり、補償を受けられなくなったりする可能性もあるのです。
そこでこの記事では、聴覚障害になってしまった方が認定される可能性がある後遺障害等級や、適正な等級を認めてもらうためにやるべきことなどを解説します。
最後まで読めば、自分が何級の認定を受けられる可能性があるのかが分かり、適正な等級を認めてもらうためにすべきことを理解できます。
後遺障害等級の認定結果が出た際、その等級が正当かどうか判断するためにも、症状別の等級について学んでいきましょう。

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1. 聴覚障害の後遺障害等級は4~14級
聴覚障害が残ってしまった方が認定される可能性がある後遺障害等級は、4~14級です。
記事冒頭でもお伝えしましたが、症状によって認定される等級が異なります。
| ・両耳に聴覚障害がある場合:4級〜11級 ・片耳のみに聴覚障害がある場合:9級〜14級 ・聴覚障害に伴って耳鳴りがある場合:12級・14級 |
ここでは、どのような症状で何級が認められる可能性があるのか、詳しく見ていきましょう。
| 「〇級〇号」の「号」について |
| 「号」は症状の程度や部位によってさらに細かくわけるためのものです。号の数字は症状を分類するためのものなので、2号より3号が重い、というようなルールはありません。 |
1-1. 両耳に聴覚障害がある場合:4級〜11級
両耳に聴覚障害が残ってしまった場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、4~11級です。
| 等級 | 症状 |
| 4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの 【等級が認定される基準】 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 【等級が認定される基準】 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
| 6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 【等級が認定される基準】 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの |
| 7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 【等級が認定される基準】 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
| 7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 【等級が認定される基準】 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの |
| 9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 【等級が認定される基準】 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
| 9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 【等級が認定される基準】 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの |
| 10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 【等級が認定される基準】 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
| 11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 【等級が認定される基準】 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの |
引用:国土交通省 自賠責保険・共催ポータルサイト 限度額と補償内容
※平均純音聴力レベル:どのくらい小さな音が聞こえるか
※最高明瞭度:言葉をどの程度明確に聞き取れるか
実際に、両耳の聴覚障害で等級が認められた事例があります。
| ・会社員男性、難聴・耳鳴りで9級(名古屋地判平31.2.22 自保ジ2047・12) |
1-2. 片耳のみに聴覚障害がある場合:9級〜14級
片耳に聴覚障害が残ってしまった場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、9~14級です。
| 等級 | 症状 |
| 9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの 【等級が認定される基準】 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの |
| 10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 【等級が認定される基準】 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの |
| 11級6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 【等級が認定される基準】 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
| 14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 【等級が認定される基準】 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの |
参照:国土交通省 自賠責保険・共催ポータルサイト 限度額と補償内容
※平均純音聴力レベル:どのくらい小さな音が聞こえるか
※最高明瞭度:言葉をどの程度明確に聞き取れるか
実際に、片耳の聴覚障害で等級が認められた事例があります。
| ・航空機の燃料補給業の男性、1耳の聴力障害で11級6号(岡山地判平21.5.28 交民42・3・692) ・タクシー運転手男性、左耳難聴と左耳鳴症で10級(大阪地判平12.3.14 自保ジ1405・7) |
参考:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(基準編)2024年版
1-3. 聴覚障害に伴って耳鳴りがある場合:12級・14級
耳鳴りの症状が残ってしまった場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、12・14級です。
| 等級 | 症状 |
| 12級 | 耳鳴が常時あると評価できるもの |
| 14級 | 医学的に合理的に耳鳴りの存在を説明できるもの |
実際に、耳鳴りを伴う聴覚障害で等級が認められた事例があります。
| ・事務職会社員男性、右耳小骨離断に伴う難聴、耳鳴りで14級(東京地判平25.1.16 交民46・1・49) ・ホテルフロント勤務男性、難聴・耳鳴りで12級(京都地判平29.4.21 交民50・2・459) |
参考:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(基準編)2024年版
2. 同じ聴覚障害でも後遺障害等級非該当となったり不当に低い等級を認定されるケースがある
1章では、聴覚障害の症状ごとに、認定される可能性がある後遺障害等級を紹介しました。
ここで、注意していただきたいことがあります。
それは、同じ聴覚障害でも、後遺障害非該当となったり、不当に低い等級を認定されたりするケースがあるということです。
なぜこうしたことが起きるのかというと、後遺障害等級は、申請時に提出する診断書や検査結果などの証拠によって決まるからです。
どれだけ重い難聴や耳鳴りといった症状が残っていても、それが書類上で医学的に正しく証明されていなければ、正当な等級が認定されません。
その結果、本来受け取れるはずだった後遺障害慰謝料等の賠償金を受け取れないリスクが生じてしまう可能性があるのです。
このような事態を避けるためには、残った症状を医学的に証明することが何より重要です。
そのための準備については「4.聴覚障害で適正な等級の認定を受けるためにやるべきこと」で解説するので、このまま読み進めてください。
3. 実際に非該当から適切な後遺障害の認定を受けた事例
2章では、同じ聴覚障害でも、認定される等級が異なるケースがあることをお伝えしました。
当弁護士法人サリュでも、等級が認定されるほどの聴覚障害なのに、当初は非該当とされてしまった方よりご相談いただいた事例があります。
| 【非該当→14級】歩行中に自転車で衝突された方の事例 【非該当→12級】乗用車で停車中に後方から追突された方の事例 |
今回の事例では、弁護士の介入により後遺障害14級が認められましたが、聴力障害が残ったにもかかわらず、非該当のまま泣き寝入りする被害者がいるのも実情です。
どのような流れで聴覚障害の等級認定を受けることができたのか、参考にしてください。
3-1.【非該当→14級】歩行中に自転車で衝突された方の事例
| 賠償金額 | 380万円 |
| 事故の状況 | 歩行中に自転車で衝突される |
| 後遺障害等級 | 非該当→14級 |
Mさんは、歩行中に自転車で衝突され、聴力障害が残ってしまいました。Mさんは後遺障害の申請をしましたが、事故前から聴力障害があることを理由に、等級が認められませんでした。
しかしサリュの弁護士が、医療記録をもとにMさんの聴力障害について調べたところ、聴力障害は改善されており、事故後に悪化したことが判明したのです。
その後、相手の自賠責保険会社へ異議申立てをしたところ、後遺障害第14級3号が認定されました。
最終的に、Mさんは380万円を超える賠償金を受け取ることができました。
事例353:聴力障害の既往症を理由に後遺障害非該当でも、医療記録を調査し異議申し立て。後遺障害14級3号の認定を受けた事例
3-2.【非該当→12級】乗用車で停車中に後方から追突された方の事例
| 賠償金額 | 1,200万円 |
| 事故の状況 | 乗用車で停車中、後方から追突される |
| 後遺障害等級 | 非該当→12級 |
40代のDさんは、赤信号停車中に後続車両に追突され頚椎捻挫の傷害を負いました。耳鳴りに悩んでいたDさんは、怪我の治療中にサリュに相談しに来てくださいました。
サリュの弁護士は、Dさんに「難聴はありませんか?」と聞きましたが、Dさんはないと回答します。
しかし、サリュの弁護士は、耳鳴りに悩んでいる人が難聴を認識していないケースがあることを知っていたため、すぐにDさんの純音聴力検査結果を検討しました。
その結果、Dさんに後遺障害等級が認定されるレベルの難聴があることが判明し、自賠責保険金と合わせて約1,200万円の賠償金を獲得することができました。
今回Dさんは後遺障害12級が認められましたが、サリュに来られる前は、12級相当の後遺障害があることに気づいておられませんでした。
ご相談いただいていなければ、Dさんは後遺障害非該当となっていた可能性があるでしょう。
4. 聴覚障害で適正な等級の認定を受けるためにやるべき4つのこと
2章、3章で、聴覚障害が残っても後遺障害非該当になったり、不当に低い等級が認定される可能性をお伝えしました。
4章では、適正な等級の認定を受けるために、今からやっておくべき事前準備を紹介します。
| 1.後遺障害認定に必要な聴力検査を行う 2.気になる症状はすべて主治医に伝える 3.適切なタイミングで症状固定の診断を受ける 4.交通事故に強い弁護士のアドバイスを受ける |
事前準備次第で適正な等級を認めてもらえるかどうかが変わるため、必ずチェックして実施するようにしてください。
4-1. 後遺障害認定に必要な聴力検査を行う
適正な後遺障害等級の認定を受けるには、認定基準に対応した聴力検査を受けておくことが重要です。
なぜなら、聴覚障害の有無やその程度は、検査結果をもとに判断されるからです。
検査を受けていない、あるいは必要な検査が不足している場合、実際の症状よりも低い等級しか認められない可能性があります。
聴覚障害の有無を証明するために必要な検査は、下記のとおりです。
| 症状 | 聴覚障害を証明するために必要な検査 | |
| 両耳、片耳の聴覚障害 | 標準純音聴力検査 | どれだけ小さい音まで聞こえるかを調べる検査(聞こえの程度は正常か、どの程度の聞こえの悪さかを判断する) |
| 語音聴力検査 | 言葉をどの程度明確に聞き取れるかを確かめる検査 | |
| 耳鳴りを伴う聴覚障害 | ピッチ・マッチ検査 | 機械を使って音を流し、耳鳴りの周波数を調べる検査 |
| ラウドネス・バランス検査 | 耳鳴りがどのくらいの音量なのかを調べる検査 | |
| 耳鳴マスキング検査 | 耳鳴りと似た音を出して、耳鳴りの聞こえ方を確かめる検査 | |
これらの検査を受けないと、後遺障害等級を判断する際の基準(例:平均純音聴力レベル90dB以上)に必要なデータを取得できず、症状に見合う後遺障害等級を認めてもらえません。
もし、まだこれらの検査を受けていないなら、主治医に「後遺障害認定に必要な検査を受けたい」と伝えてみてください。
4-2. 気になる症状はすべて主治医に伝える
後遺障害の等級認定を正しく受けるためには、どんなに小さな症状でも主治医にすべて伝えておくことが大切です。
等級の判断に使われる後遺障害診断書は、医師が把握している情報をもとに作成されるからです。
診断書には、「いつからどの程度の症状がでているのか」といった自覚症状の経過も記載され、等級の判定に影響します。
もし、
「耳鳴りがする気がするけど、気のせいかもしれない」
「今日は普通に聞こえるし、前の症状は一時的だったのかも」
と自分で判断して主治医に伝えなかった場合、聴覚障害が残っても「大したことがない」「自覚症状がなかったのだから問題ない」などと扱われてしまう恐れがあるのです。
自覚症状は、医師にとっても重要な判断材料です。
「伝えるほどでもないかも」と思う症状でも、遠慮せず必ず主治医に話してください。
4-3. 適切なタイミングで症状固定の診断を受ける
適切なタイミングで症状固定の診断を受けることも、聴覚障害で適正な等級の認定を受けるために必要です。
症状固定とは、交通事故において治療終了を意味するものです。これ以上治療やリハビリを続けても症状が良くならない状態になると、症状固定と診断されます。
症状固定のタイミングで後遺障害の有無や等級が判断されるため、早すぎる症状固定は認定に不利に働くことがあります。
例えば、事故から6ヶ月未満で症状固定と診断されると、
「治療が十分に行われなかったから難聴や耳鳴りの症状が出た」
と判断され等級を下げられたり、そもそも後遺障害と認められなかったりする場合があります。
主治医が交通事故に詳しくないケースもあるので、症状固定の診断を受ける際は医師に任せきりにせず、「今が適切なタイミングなのか」を自分でも確認しましょう。
| 後遺障害認定の申請は、症状固定の診断を受けてから |
| 後遺障害認定は、症状固定の診断を受けてから申請します。 申請手順については、以下の記事をご覧ください。 |

4-4. 交通事故に強い弁護士のアドバイスを受ける
聴覚障害で適正な等級を認定してもらうには、できるだけ早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することが大切です。
交通事故に強い弁護士がいれば、聴覚障害の等級認定に必要な証拠を漏れなく集められるからです。
そもそも、聴覚障害は見た目ではわからないため、必要な検査や書類が少しでも欠けていると正当な等級が認められません。
交通事故に詳しい弁護士に相談すれば、過去の事例をもとに、
「あなたの症状なら〇級が認められる可能性がある」
「等級の認定に必要な検査が足りていないので、主治医にお願いしましょう」
など、等級認定に必要な具体的なアドバイスを早い段階から受けられます。
また弁護士は、治療の途中段階からでも後遺障害等級の認定に向けてサポートすることが可能です。
少しでも不安を感じているなら一人で抱え込まず、交通事故に強い弁護士に早めに相談することをおすすめします。
5. まとめ
本記事では、聴覚障害になってしまった方の後遺障害等級について、解説しました。
最後に、大事なポイントをまとめます。
〇聴覚障害の後遺障害等級は4~14級
| 状況 | 認定される可能性がある後遺障害等級 |
| 両耳に聴覚障害がある | 4級、6級、7級、9級、10級、11級 |
| 片耳のみに聴覚障害がある | 9級、10級、11級、14級 |
| 聴覚障害に伴って耳鳴りがある | 12級、14級 |
〇同じ聴覚障害でも後遺障害非該当となったり不当に低い等級を認定されるケースがある
〇聴覚障害で適正な等級の認定を受けるためにやるべき4つのこと
| 1.後遺障害認定に必要な聴力検査を行う 2.気になる症状はすべて主治医に伝える 3.適切なタイミングで症状固定の診断を受ける 4.交通事故に強い弁護士のアドバイスを受ける |
自分の症状で何級になるのか、正確に判断するのは難しいです。
正当な等級を認めてもらうためにも、本記事でお伝えしたことを実践してみてください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
