弁護士のセカンドオピニオン|交通事故で後悔しないための相談手順
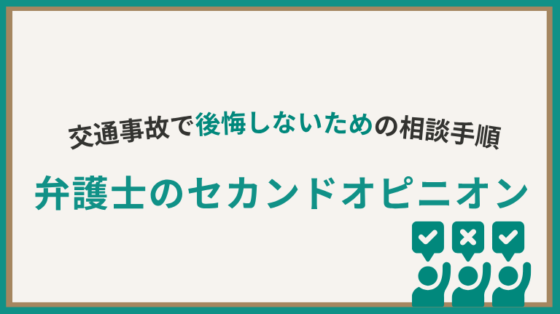
「交通事故でとりあえず弁護士に依頼したけど、対応が悪くて不安がある…」
「セカンドオピニオンで他の弁護士に相談したいが、どうしたら良いだろう?」
交通事故で依頼した弁護士に不安があり、このような悩みを抱えている方はいないでしょうか?
そのような方にお勧めするセカンドオピニオンの手順は以下のとおりです。
| 1.セカンドオピニオンで相談する内容をまとめる 2.事故状況や治療状況を説明できる書類を準備する 3.セカンドオピニオン先の弁護士を探す 4.相談前にセカンドオピニオンであることを伝える 5.どのような点が納得できないのか相談する 6.【弁護士を変更したいと思ったら】変更の手続きを行う |
このように、弁護士の変更を前提としていなくても、まずは相談してみてください。
ただし、現状の不安や不満の内容を明確にせず、やみくもにセカンドオピニオンを受けたり弁護士を変更したりしても、納得できない状況が続いてしまう可能性があります。
「セカンドオピニオンを受けても時間の無駄だった」
「弁護士を変更したのに結局同じ状況が続いている」
そのような後悔を防ぐためにも、この記事ではセカンドオピニオンのやり方だけではなく、信頼できる弁護士の選び方まで解説します。
現状の不安な気持ちを解決するためにも、まずはセカンドオピニオンについての理解を深め、納得できる事故解決に向けて行動を始めてください。

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した
目次
1.交通事故で弁護士のセカンドオピニオンを受ける手順
弁護士のセカンドオピニオンを検討していても、実際どのような手順で進めればいいのかわからないという方も多いはずです。
そこで、この章では弁護士のセカンドオピニオンを受けるための具体的な手順を解説します。
弁護士のセカンドオピニオンを受ける手順は、以下の通りです。
それぞれの項目で何をすればいいのか、どんな注意点があるのか、詳しく説明していきます。
| 1.セカンドオピニオンで相談する内容をまとめる 2.事故状況や治療状況を説明できる書類を準備する 3.セカンドオピニオン先の弁護士を探す 4.相談前にセカンドオピニオンであることを伝える 5.どのような点が納得できないのか相談する 6.【弁護士を変更したいと思ったら】変更の手続きを行う |
1-1.セカンドオピニオンで相談する内容をまとめる
まずは、セカンドオピニオンで相談する内容をメモなどにまとめておきましょう。
これが、この後の弁護士探しの基準や相談時の時間の短縮につながります。
| ・今の弁護士に「まだ交渉は進められない」と言われたけど本当なの? ・ネットで見た慰謝料の相場より低い気がするけど、交渉できないの? ・後遺障害の認定を受けたいけど、サポートが消極的で不安 |
このように、箇条書きやざっくりとしたメモでも問題ないので、相談したい内容を事前にまとめておきましょう。
単に「今の弁護士が信用できない」だけでは不満や不安が具体的に伝わらず、的確な助言をもらえない可能性があります。
セカンドオピニオンを有意義に進めるためにも、まずは相談内容を事前にまとめることからスタートしましょう。
1-2.事故状況や治療状況を説明できる書類を準備する
次に、交通事故や治療の状態を説明できる書類の準備を行います。
セカンドオピニオンで具体的なアドバイスを受けるためには客観的な資料の提供が不可欠です。
提供できる資料が不足していると、相談先の弁護士も具体的な判断ができず、一般的なアドバイスしかできない可能性が高まります。
相談時には、できる限り以下のような証拠を集めて提出できるようにしておいてください。
| 医療関係の証拠 | 診断書・診療報酬明細・検査画像など |
| 事故関係の証拠 | 交通事故証明書・実況見分調書など |
| 損害関係の証拠 | 修理見積書・休業損害証明書など |
原本を依頼中の弁護士に預けている場合には、コピーや書類を写真に撮ったもの(スクリーンショットなど)でも大丈夫です。
相談先の弁護士に、事故の客観的な様子が伝わる証拠を揃えておきましょう。
1-3.セカンドオピニオン先の弁護士を探す
事前の準備が整ったら、セカンドオピニオン先の弁護士を探していきます。
具体的な弁護士選びのポイントについては、4.信頼して交通事故の対応を任せられる弁護士選びのポイントで詳しく解説しますので、こちらを参考にしてください。
弁護士事務所には、「初回相談料が無料」のところと「初回から料金が発生するところ」があります。
相談料が負担になる可能性があるため、複数の弁護士へのセカンドオピニオンを検討している場合は注意してください。
| 弁護士費用特約を使う場合は事前に保険会社へ相談する |
| 相談料を弁護士費用特約などで補償してもらう場合、事前に加入している保険会社への相談が必要になります。 保険会社によっては、セカンドオピニオンは補償の対象外となる可能性もあるので、事前に確認しておきましょう。 |
1-4.相談前にセカンドオピニオンであることを伝える
相談したい弁護士が決まったら、相談前の予約の段階で「セカンドオピニオンである」ということを伝えておきましょう。
弁護士側も、初めての依頼なのかセカンドオピニオンなのかで対応が変わる部分があるため、事前に共有しておいたほうがスムーズに進みます。
また、現在準備している書類や相談したい内容についても、簡単に伝えておくと不足がないか事前に確認してもらえるでしょう。
事務所によってはセカンドオピニオンを行っていない、積極的ではないことも考えられるため、この段階で伝えて確認しておいてください。
1-5.どのような点が納得できないのか相談する
面談当日は、準備した資料とまとめておいた相談内容をもとに、納得できない点について相談してください。
弁護士とのコミュニケーションにすれ違いがあっただけで、客観的な意見をもらうと納得できるということもあるかもしれません。
ただし、弁護士には以下のルールがあるため、現在の弁護士の方針については具体的な指摘を受けられない可能性があります。
| 弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない(弁護士職務基本規程 第72条) |
「今の方針の問題点を教えてもらう」というよりは、「別の弁護士に相談した場合の見解を聞く」という側面が大きいことを知っておいてください。
セカンドオピニオンを受けたからと言って必ず弁護士を変更しなければいけないわけではありません。あなたが納得・安心できることが重要なので、ここで納得できればその内容を参考に既に依頼している弁護士との関係を継続してください。
1-6.【弁護士を変更したいと思ったら】変更の手続きを行う
セカンドオピニオンを受けた結果、弁護士を変更したいと思ったらそのための手続きを進めていく必要があります。
以前の弁護士との間に委任契約がある状態で新たな契約を結ぶことはできませんので、まずは現在依頼している弁護士に連絡をして契約を解除し、その後新しい契約を結びましょう。
既に依頼している弁護士への契約の解除の連絡は、まずは電話や手紙で解約意向を伝え、その後は当該法律事務所ないし弁護士の指示に従ってください。。
解除にあたっては、以下のような手続きが必要になります。
| 業務資料の返還請求 | 証拠・提出書類の原本やデータなど、前任弁護士に預けている書類を返還してもらう |
| 未払費用の精算 | 弁護士が既に稼働していた場合、その分の弁護士費用や実費の支払いを行う |
基本的には、弁護士同士で引継ぎを行うのが一般的なため、依頼者は契約を解除したい旨と後任の弁護士を伝えれば問題ありません。
また、自分の保険会社にはこのタイミングで連絡をする必要がありますが、相手の保険会社へは一般的に弁護士から連絡をするため、依頼者が行う必要はありません。
弁護士の変更方法については「【実践的】交通事故の弁護士は変更できる!後悔しない方法・注意点」で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
| 依頼中の弁護士にセカンドオピニオンが知られることは基本的にない |
| 「セカンドオピニオンをしたら今の弁護士にバレて気まずくなりそうで心配」 そう考えて相談をためらうかもしれませんが、相談先の弁護士から依頼中の弁護士にセカンドオピニオンの情報が漏れることは基本的にありません。 なぜなら、弁護士には守秘義務があるので、弁護士同士とはいえ依頼の内容を漏らすことは守秘義務違反になるからです。 とはいえ「相談時に必要な書類を取り寄せる」「急に連絡頻度が変わる」などの行動から依頼中の弁護士に推察されてしまう可能性はあります。 |
2.弁護士のセカンドオピニオンを行う際の注意点
セカンドオピニオン自体は「別の弁護士に相談するだけ」でリスクの低い手段ですが、ケースによっては依頼者に負担が生じる可能性があります。
本章では、思わぬ負担に驚くようなことがないよう、セカンドオピニオン時に押さえておきたいポイントを解説します。
| 1.相談費用の自己負担が発生する可能性がある 2.弁護士を変更すると金銭的な負担が発生する可能性がある 3.弁護士を変更すれば事態が好転するとは限らない |
2-1.相談費用の自己負担が発生する可能性がある
まず、セカンドオピニオンだけの場合でも起こりうるリスクとして、相談費用の自己負担が発生する可能性があります。
弁護士事務所の中には無料相談を行っているところもありますが、相談費用の支払いが必要になるケースもあるからです。
相談費用の相場は、1時間5000円~1万円程度となります。
このように、相談だけでも費用が発生する可能性があるので注意してください。
2-2.弁護士を変更すると金銭的な負担が発生する可能性がある
弁護士を変更した場合、さらに金銭的な負担が発生する可能性があります。
まず、着手金やすでに稼働した分の実費などについては、基本的に返金はありません。
そのため、「以前の弁護士」と「新しく依頼する弁護士」に二重に着手金を払うことになるので注意が必要です。
また、弁護士費用特約を使っている場合であっても、以下のようなケースでは自己負担が発生するかもしれません。
| ・弁護士費用特約の規約で2人目以降の弁護士への支払いに制限がある ・特約の限度額(一般的に300万円)をオーバーする |
このように、費用面で負担がある可能性を知ったうえで、それでも弁護士を変更するべきかを慎重に検討してください。
2-3.弁護士を変更しても事態が好転するとは限らない
最後に知っておいていただきたいのが、弁護士を変更しても事態が好転するとは限らないということです。
セカンドオピニオンで別の弁護士に相談すると、その人のほうが優秀に感じて弁護士の変更を急いでしまうかもしれませんが、優秀に感じるのには理由があります。
| ・最初の弁護士に相談したときより証拠が揃っているため、適切な回答がスムーズに出やすい ・不満点を含めて相談しているため、対応が自分に合ったものになりやすい ・異なる見解の意見が出たとき、不満が前提にあるため「今までの弁護士が間違っていたのかも」と感じやすい |
このように、相談時には別の弁護士のほうが優秀に感じることがあるかもしれませんが、変更したからといって必ずしも事態が好転するわけではありません。
リスクを説明せずに弁護士の変更を勧めるような法律事務所には特に注意が必要です。
ここまでに説明したとおり、金銭的な負担が発生する可能性があることも踏まえたうえで、冷静な判断を行ってください。
3.「弁護士を変えても状況が変わらない…」後悔を防ぐには納得できる弁護士選びが重要
交通事故の弁護士を変更するときには、納得できる弁護士選びが非常に重要です。
そうでないと結局同じ後悔を繰り返すことになってしまうからです。
まずは、1-1.セカンドオピニオンで相談する内容をまとめるでもお伝えしたとおり、現状のどの部分に不満や不安を抱えているのかを明確にしましょう。
| ・レスポンスが遅い ・後遺障害の認定に向けて行動してくれない ・慰謝料をもっと増額できないのか知りたい(できない場合、理由を説明してほしい) |
このように状況を整理し、どんな解決を求めているのか、実現が可能なのかをよく検討し、相談したうえで弁護士を決定しましょう。
これらの対応を怠ってしまうと、金銭的な負担や手続きの手間をかけて弁護士の変更を行ったにもかかわらず、結局変更後も対応に不満を抱く結果になりかねません。
そういった事態を避けるため、今ご自身が不満に思っていることや相談したいことを明確にしたうえで、同じような不満が生まれない弁護士をしっかり選んでいきましょう。
4.信頼して交通事故の対応を任せられる弁護士選びのポイント3つ
前章でお伝えしたとおり、セカンドオピニオンで交通事故の弁護士を変更したいと思ったときには、弁護士選びが非常に重要です。
ここでは、交通事故被害者が安心して任せられる弁護士を見極める3つのポイントを解説します。
| 1.交通事故の被害者に特化した解決実績が豊富である 2.相談時に納得できるよう話をしてくれる 3.客観的な意見を伝えてくれる |
4-1.交通事故の被害者に特化した解決実績が豊富である
交通事故の被害者側に特化していることと解決実績が豊富であることは最も重要な指標となります。
なぜなら、交通事故の対応では被害者と加害者のどちらにつくかで必要な法知識・経験などが異なるからです。
| 被害者側の弁護士に必要な知識 | 適正な賠償金額の算定、後遺障害等級の認定手続きなど |
| 加害者側の弁護士に必要な知識 | 賠償金の減額、過失割合の交渉など |
このように必要な知識が異なるため、交通事故被害者が適正な結果を得るためには「被害者に特化して多数の解決実績がある」弁護士を選ぶことが重要なのです。
また、解決実績が豊富な弁護士事務所では、特殊な事例なども数多く担当している可能性が高く、幅広い案件への対応が可能です。
経験や知識が豊富な弁護士を探す基準として、「被害者特化である」「解決実績が1万件以上ある」という指標を基準にしてください。
4-2.相談時に納得できるよう話をしてくれる
次に大切なのが、相談時に納得できるよう話をしてくれることです。弁護士への依頼では、単に法的な知識や実績だけでなく、依頼者との相性も大きなポイントとなります。
なぜなら、相談時に不安な点やわからないことを遠慮なく話せる環境が整っていない場合、適切なサポートを受けられない可能性があるからです。
例えば、依頼者が「このままで示談しても良いのか」「後遺障害の申請を進めた方が良いのか」といった疑問を抱えたまま話を進めてしまうと、後々後悔することにもつながりかねません。
不安な点を話しやすく、明瞭に説明してくれる弁護士かどうかというのも弁護士選びの基準として重要です。
4-3.客観的な意見を伝えてくれる
最後に、利益を重視せずに被害者に客観的な意見を伝えてくれる弁護士であることも重要です。
セカンドオピニオンでは、弁護士が「依頼を受けるために無責任な言葉で弁護士の変更を勧めてくる」という可能性もゼロではありません。
そのような勧誘に乗って新たな後悔をしないためにも、相談内容が客観的で信頼できるものかどうかを判断してください。
例えば、信頼性の高い発言かどうかを確認するためのポイントとしては以下のようなものがあります。
| ・被害者のケースに対して、過去の判例や法律などの根拠がある数字を提示する →「同じような怪我で通院が6か月の場合は●円が相場です」 ・メリットだけではなくデメリットも提示する →「弁護士を変更した場合、このような手続きと費用がかかります」 ・弁護士変更以外の選択肢も提示する →「このケースでは、今の弁護士にこの内容を伝えれば改善されるかもしれません」 |
逆に、根拠の薄い以下のような発言は注意が必要です。
| ・客観的な根拠のない数字を提示する →「うちに依頼していただければ絶対に増額しますよ」 ・具体的な理由を説明せず、依頼を過剰に焦らせる →「今すぐ弁護士を変更しないと、取り返しがつかなくなりますよ」 |
このように、弁護士の発言から「本当に信頼できるのか」を判断してください。
また、後悔しない弁護士選びのポイントについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。
「後悔しない」交通事故の弁護士の選び方・見極め方のポイント徹底解説
5.交通事故の対応に不安を感じたらサリュにご相談ください
「弁護士の変更までは考えていないけど、まずはセカンドオピニオンで相談してみたい」
そのようなお悩みを抱えている方は、ぜひサリュにご相談ください。
サリュは、これまで交通事故の被害者に特化して2万件以上の事故解決を行ってきた法律事務所です。
これまでにも、依頼中の弁護士に不安を抱えた方のセカンドオピニオンとして、数々の相談に対応してきた実績があります。
| セカンドオピニオンから依頼を受け、納得の結果を獲得したサリュの解決事例 |
| 相手の提示金額→82万5308円(休業損害は認められない) 最終的な賠償金→約270万円 ※相手の保険会社から支払われた金額を除く |
| この事例では、相手の保険会社の不誠実な対応に疲弊した被害者が他事務所に依頼したものの、不安があり、セカンドオピニオンとしてサリュにご相談をいただきました。 相談後に依頼していただき、相手の保険会社との交渉を行いました。 主な争点は、主夫である被害者の休業損害についてです。 相手方は、「休業損害も認められないし、後遺障害もない。ましてや事故態様においても過失が10%はある」と主張し、82万5308円の賠償金を提示してきました。 しかし、サリュは ・事故当時の状況 ・事故による生活状況の変化 などを主張し、結果的に270万円の賠償額で和解しました。 交通事故の見識が薄い場合、主夫の休業損害として十分な補償を受けられない可能性があります。 サリュなら証拠を精査し、納得できる解決を目指します。 事例の詳細を見る |
このように、実際にセカンドオピニオンからご依頼をいただき、依頼者の方が納得できる賠償金を獲得できた実績もございます。
初回は費用のご負担なくご相談いただけますので、
「とりあえず話だけでも聞いてみたい」
「自分の不安が解消できそうなのか知りたい」
という方、今は弁護士の変更までは考えていない方も、お気軽にお問い合わせください。
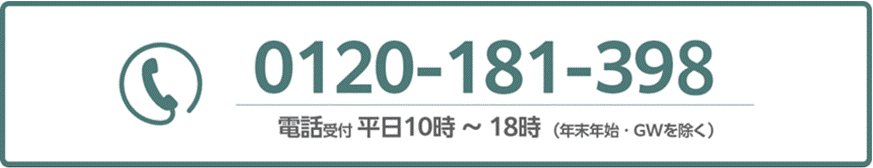
メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。
6.まとめ
交通事故の示談・訴訟で「今の弁護士に不安を抱えたまま進める」ことにならないよう、弁護士のセカンドオピニオンのやり方や注意点について解説してきました。
内容のまとめは以下のとおりです。
▼弁護士のセカンドオピニオンの手順
| 1.セカンドオピニオンで相談する内容をまとめる 2.事故状況や治療状況を説明できる書類を準備する 3.セカンドオピニオン先の弁護士を探す 4.相談前にセカンドオピニオンであることを伝える 5.どのような点が納得できないのか相談する 6.【弁護士を変更したいと思ったら】変更の手続きを行う |
▼弁護士のセカンドオピニオンをする際の注意点
| 1.相談費用の自己負担が発生する可能性がある 2.弁護士を変更すると金銭的な負担が発生する可能性がある 3.弁護士を変更しても事態が好転するとは限らない |
▼セカンドオピニオンや弁護士の変更で後悔しないための弁護士選びのポイントは3つ
| 1.交通事故の被害者に特化した解決実績が豊富である 2.相談時に納得できるよう話をしてくれる 3.客観的な意見を伝えてくれる |
弁護士の対応に不安がある方は、まずはセカンドオピニオンを検討してください。
この記事が、あなたが納得できる弁護士を選び、適正な賠償を受け取るための第一歩となれば幸いです。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
