【交通事故】示談交渉を自分でするのは避けるべき|後悔する理由とは
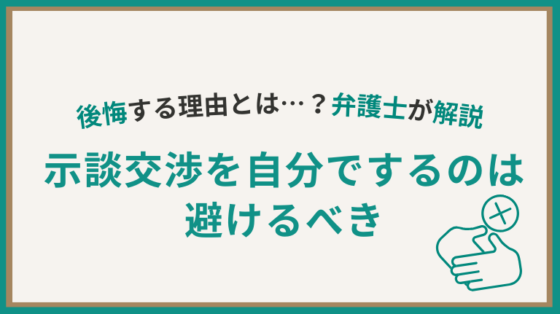
「交通事故の示談交渉って自分でできる?」
「弁護士とかに相談するのは面倒だし、余計なお金もかかりそう」
弁護士費用の心配や、弁護士に依頼する手間を考えて、交通事故の示談交渉を自分で行おうとする方は少なくありません。
「自分で調べて知識をつければ、交通事故の示談交渉くらいならできるんじゃないかな」
と考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、交通事故の示談交渉を自分で行うことはおすすめしません。
なぜなら、示談交渉で自分の意見を通すためには、専門的な知識や経験が必須となるからです。
示談交渉を自分で行った場合、基本的には相手の保険会社の言い分が通りやすく、被害者側の意見はほとんど通らないと思ったほうがいいでしょう。
それどころか、最初は丁寧に説明してくれていた保険会社の担当者の態度が途中で変わり、高圧的に保険会社の主張を受け入れるように言われるようなケースもあるのです。
そのような中で自分で示談交渉をすると、以下のような後悔をすることになるかもしれません。
| 1.相手に都合のいい条件で押し切られる 2.保険会社に治療を打ち切られる 3.示談後に請求できる項目の漏れに気が付く |
それでは、被害者が意見を通すためにはどうすればいいのかというと、弁護士への依頼が重要になります。
弁護士に依頼し、保険会社との示談交渉を代行してもらうことで、被害者の意見が相手に通りやすくなるからです。
また、弁護士に依頼することで、相手との交渉を任せられるため、ストレスや負担を軽減することができます。
とはいえ、どんな弁護士でも依頼すればいいというわけではありません。
保険会社の手口を知り尽くし、被害者のために戦ってくれる弁護士を選ぶ必要があります。
この記事では、示談交渉を自分で行いたいと考えている方に向けて、自分で示談交渉を行うことはおすすめしない理由と、それでもやりたい場合の手順、示談交渉を弁護士に任せたほうがいい理由をお伝えします。
お伝えした内容を参考に、示談交渉に対応してください。

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1.交通事故の示談交渉を自分で行うことはできるがおすすめしない
交通事故の示談交渉を、被害者本人が自分ですることは可能です。
以下のように、示談書にサインをして送り返すだけで、示談自体は簡単に成立させられます。
| 相手が送ってきた示談書にサインをする ↓ 送り返す ↓ 示談金が振り込まれる |
しかし、この方法は基本的にはおすすめしていません。
なぜなら、弁護士などを介入させずに被害者が自分で交渉を行った場合、ほとんど交渉の余地はなく、被害者の意見を通すことは難しいからです。
相手の保険会社は、極力補償を少なくするため、最低限の基準の示談金しか提示してこない傾向にあります。
また、保険会社は、被害者が専門的知識を有しておらず、法律や判例などに基づいた反論ができないことを利用して、被害者が交渉しようとしても、
「こちらの事故のケースでは、提示している金額が限界です」
「今回のような場合、示談金の増額はできません」
このようにごまかされ、相手の意見を聞かざるを得ない状況になることもあるでしょう。
示談交渉自体は自分で行うことも可能ですが、被害者にとって正当な条件での解決を望む場合には、おすすめしない方法となります。
2.自分で示談交渉した結果よくある後悔3つ
示談交渉を自分で行うことは可能ですが、最初にお伝えした通り、あまりおすすめしていません。
保険会社とのやり取りを十分理解し、対処できればよいのですが、実際には専門知識や経験不足で被害者が大きな損をしてしまう事例が少なくないからです。
実際に、自分で示談交渉することでどのようなリスクがあるのか、起こりやすい後悔を3つ解説します。
| 1.相手に都合のいい条件で押し切られる 2.保険会社に治療を打ち切られる 3.示談後に請求できる項目の漏れに気が付く |
2-1.相手に都合のいい条件で押し切られる
最初に紹介する自分で示談交渉して後悔する点は、相手に都合のいい条件で押し切られ、納得できない結果に終わることです。
相手の保険会社の担当者は交渉のプロであり、法律や損害賠償の知識を熟知しています。
一方、被害者側は専門知識がないまま対応しがちで、相手の言い分にうまく反論できません。
| ・被害者がわからない専門用語を多用する ・金額が不当だと訴えても「弊社の基準ではこれが限界です」などとはぐらかす ・交渉が長引くと裁判などをちらつかせ、早く合意させようとする |
相手はこのような手を使い、なんとか加害者有利な形で決着をつけようとしてくるでしょう。
例えば、実際には被害者に過失割合がないケースにも関わらず過失があると言われたり、治療費や検査費など、請求の対象になる費用があるにも関わらず、伏せられていたりします。
プロである相手の保険会社に十分反論できなかった結果、交渉の場で圧倒的に不利になり、納得できない条件のまま解決してしまう可能性があるでしょう。
2-2.保険会社に治療費を打ち切られる
次に考えられるリスクは、まだ治療中にも関わらず、保険会社の判断で治療費を打ち切られることです。
治療を開始してから3~6か月程度が経過した段階で、保険会社の担当者から
「もう症状固定の時期なので、治療費の支払いは終了します」
などと言われることがあります。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても効果が期待できない」という状態のことで、これは、基本的に担当医が判断するものです。
しかし、相手の保険会社はそれを知らせず、保険会社の決めたタイミングで症状固定を決めるべきかのように言ってくることがあります。
治療費を打ち切られると、以下のようなリスクが考えられます。
| ・怪我に対して十分な治療を続けられない ・入通院慰謝料が本来受け取れる額より小さくなる ・後遺障害等級(事故で後遺症が残ったこと)の認定を受けるのが難しくなる |
いつまで治療を続けるべきなのかは、保険会社ではなく、担当している医師が判断することです。
そのことを知らないと、不当な時期に治療を終了することになるかもしれないでしょう。
このように、保険会社の一方的な判断で治療費を打ち切られるリスクがあることを知っておいてください。
2-3.示談後に請求できる項目の漏れに気が付く
最後に起こりえるリスクは、示談が終わってから、「実はもっと請求できる損害賠償項目があった」と気付いてしまうことです。
交通事故の被害者は、治療費や慰謝料はもちろん、事故による怪我で仕事を休んでしまった分の休業損害や、通院にかかった交通費など、幅広い項目を請求することができます。
【交通事故の被害者が請求できる項目(主な項目の抜粋)】
| ・治療費 ・通院交通費 ・装具 ・器具購入費(コルセットやサポーターなどの購入費用) ・付添費用(家族の付添いが必要な場合にかかった費用) ・将来介護費(後遺障害が残り、将来介護が必要になった場合) ・入院雑費 ・休業損害 ・入通院慰謝料 ・逸失利益(後遺障害が残り、労働能力の低下が認められた場合) ・後遺障害慰謝料(後遺障害が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合) |
示談交渉の際、被害者側が把握しきれていない項目を見落とすと、その分の補償を受け取れないまま解決してしまうこともあるでしょう。
請求できる項目を十分に調べて示談前に確認しておかないと、このような後悔につながります。
3.どうしても自分で示談交渉をする際の流れ(手順)
前章では示談交渉を自分で行うのはおすすめしないとお伝えしましたが、とはいえ、どのように進めればいいのか知りたいという方も多いでしょう。
ここでは、示談交渉に向けて、被害者本人が交渉する際の流れを解説します。
| 1.すべての損害が確定したら示談交渉を開始する 2.相手の保険会社から示談金の提示がある 3.示談金に納得がいかなければ同意せず反論する 4.お互いが納得する金額になったら示談書にサイン又は署名する 5.示談書の返送後、約2週間で示談金が振り込まれる |
3-1.すべての損害が確定したら示談交渉を開始する
交通事故の示談交渉は、事故によるすべての損害が確定した段階でスタートします。
事故で負った損害ごとに、以下のようなタイミングで交渉を開始します。
また、それぞれのケースで交渉にかかる期間の目安も記載しているので、こちらも参考にしてください。
| 事故のケース | タイミング | 示談交渉までの期間の目安 |
| 事故で怪我をした | 治療終了後(完治後) | 完治後からおよそ3〜6か月 |
| 後遺障害が残った | 後遺障害等級認定後 | 症状固定からおよそ3か月〜1年 |
| 被害者が死亡した | 葬儀後 (四十九日終了後が一般的) | 交渉開始からおよそ3か月〜1年 |
| 車などが壊れた | 修理費などの見積もり後 | 交渉開始からおよそ1〜2か月 |
まずは損害の全容が確定してから示談交渉へ進むのが基本です。
怪我や後遺障害がある場合は、治療や認定の手続きをしっかり行いましょう。
3-2.相手の保険会社から示談金の掲示がある
示談交渉が始まると、まず相手の保険会社から示談金が提案されます。
ただし、この提示額が必ずしも妥当とは限りません。
相手の保険会社は会社が負う負担を少しでも小さくするため、最低限の基準で計算した示談金を提示してくることが多いからです。
ここで不当な条件で同意してしまうことを避けるためにも、正当な示談金の相場を知っておきましょう。
交通事故の慰謝料には、以下の3つの計算基準があります。
被害者には弁護士基準の慰謝料を請求する権利がありますが、相手はそれよりも低い計算基準で計算した示談金を提示してきます。
例えば、同じむちうちの怪我であっても、以下のように入通院慰謝料の相場が異なってしまうのです。
【事故によりむちうちになり3か月通院した場合】
| 自賠責基準※ | 206,400円 |
| 弁護士基準 | 530,000円 |
※3か月(90日)の間に週2回、計24回通院した場合
このように、相手が提示してきた金額は、被害者にとって妥当なものではない可能性が高いため、同意する前によく確認をしておきましょう。
通院日数が少なかった場合の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。

3-3.示談金に納得がいかなければ同意せず反論する
相手保険会社から提示された金額に納得できなければ、同意せず反論しましょう。
一度合意してしまうと、あとから取り消すことは原則できないため、慎重に対応してください。
示談については、電話や対面で持ち掛けられた場合、その場で合意しないことが重要です。
内容を精査するためにも、必ず一旦持ち帰って検討するようにしましょう。
また、反論する際には自分の意見を伝えるだけではなく、意見の裏付けとなる証拠を準備しておく必要があります。
| 相手の過失の証拠 | ・実況見分調書 ・ドライブレコーダーの記録 ・目撃情報や事故当時の写真 |
| 怪我の症状を示す証拠 | ・診断書 ・病院の検査結果 ・通院記録 |
| 怪我による損失の証拠 | ・治療費や検査費などの領収書 ・休業損害証明書(会社などを休んだ日数の記録) |
これらの証拠を準備した上で、交渉を行ってください。
| 交渉するときは過去の裁判例を参考にする |
| 相手の提示した条件に反論するときには、過去の裁判例を参考にしてください。 感情的に「この怪我に対してこの金額は納得できない」と言っても受け入れてもらえません。 しかし、「過去の裁判例では、同じ通院期間で同じ症状の人が●円の慰謝料を受け取っている」というように、実際の判例をもとに交渉すれば、受け入れてもらえる可能性が高まります。 交渉の際には、自分の意見を補強するような過去の裁判例を探し、それを根拠に戦うことが重要です。 |
3-4.お互いが納得する金額になったら示談書にサイン又は署名する
最終的に、お互いに納得できる金額になったら、その条件で示談書を作成し、署名捺印します。
示談書は、これまでの交渉結果を反映した最終的な合意書です。
いったん署名捺印してしまうと条件を変更することはできないので、十分に吟味してから手続きしましょう。
3-5.示談書の返送後、約2週間で示談金が振り込まれる
示談書のやり取りが完了すると、通常は1〜2週間程度で指定した口座に示談金が振り込まれます。
入金が確認できるまでは、示談書の内容や連絡事項をきちんと保管し、振込額の誤りなどがないかチェックしましょう。
これで、示談交渉の一通りの流れは完了となります。
4.正当な金額を受け取るなら自分で示談交渉せず弁護士を頼ろう
前章でお伝えした通り、自力で示談交渉をした場合、相手の保険会社に有利に交渉が進んで後悔する結果になる可能性があります。
そのような事態を防いで納得する結果を得るためには、弁護士への依頼を検討してください。
弁護士は、交通事故に対する専門知識を持ち合わせ、被害者の味方になってくれる存在です。
実際に弁護士に依頼することでどのようなメリットがあるのか、代表的なものを3つ紹介します。
| 1.相手保険会社との交渉を一手に担ってくれる 2.被害者にとって適正な金額の示談金を請求してくれる 3.後遺障害認定などの手続きもサポートしてくれる |
4-1.相手保険会社との交渉を一手に担ってくれる
1つ目のメリットは、相手保険会社との交渉を一手に担ってくれることです。
保険会社との示談交渉では、事故や保険の知識を熟知した相手と直接やり取りしなければならず、疲弊してしまう方も少なくありません。
ここまででもお伝えしてきたとおり、相手は加害者側に有利になるように交渉を進めてくるため、反論することに疲れてしまう方も多いでしょう。
そこで頼りになるのが、弁護士です。
弁護士に依頼すれば、その後の保険会社とのやり取りはその後、基本的にすべて弁護士を介して行うことになります。
また、弁護士が介入することで、相手の対応も変わるケースが多いのが特徴です。
被害者相手であれば押し切れると考えていても、弁護士がついている場合、保険会社は通用しないと考え、被害者本人が交渉するときよりも譲歩しやすい傾向にあります。
このように、交渉の負担を軽減してくれるのが弁護士に依頼する1つ目のメリットです。
4-2.被害者にとって適正な金額の示談金を請求してくれる
弁護士に依頼する2つ目のメリットは、被害者にとって適正な金額の示談金を請求してくれることです。
3-2.相手の保険会社から示談金の掲示があるでも解説した通り、慰謝料の相場は弁護士に依頼するかどうかで、大きく異なります。
弁護士が交渉することで、被害者が納得できる慰謝料を受け取れる可能性が高まるでしょう。
また、2-3.示談後に請求できる項目の漏れに気が付くで紹介したような、被害者が請求できる項目についても、知識の豊富な弁護士であればもれなく確認してくれます。
これらの理由により、被害者にとって適正な金額の示談金を請求できることが、弁護士に依頼する2つ目のメリットです。
4-3.後遺障害認定などの手続きもサポートしてくれる
弁護士に依頼する最後のメリットは、後遺障害認定などのサポートを受けられることです。
後遺障害の申請は難しく、誰がやっても簡単に認定されるものではありません。
実際に、申請後の認定される確率は5%前後とも言われています。
認定を受けるには、後遺障害の症状や生活への影響などを客観的な証拠で証明する必要があり、被害者本人が進めるのは難しいものです。
そこで重要なのが、専門的な知識とサポート経験が豊富な弁護士の力を借りることです。
弁護士に依頼することで、以下のような部分でサポートを受けられます。
| ・必要な検査を受けているかの確認 ・医療証拠(診断書、検査結果、カルテなど)の収集 ・担当医師へ書面などで働きかけ、追加で必要な意見書などの作成依頼 |
認定における弁護士の重要性については以下の記事で詳しく解説しているので、後遺障害が残りそうな方は、こちらも参考にしてください。

| 費用面は依頼前に相談できる! |
| 弁護士に依頼する際にネックとなるのが、弁護士費用ではないでしょうか。 「わざわざ依頼をしたのに、結局弁護士費用がかさむだけでプラスにならなかった」というようなことが不安で、依頼を避けている方もいるかもしれません。 多くの弁護士事務所では、弁護士費用でマイナスが生じる「費用倒れ」が発生しないかどうかを、依頼前に相談することが可能です。 示談交渉の後で後悔することを防ぐためにも、交渉前に一度相談に行ってください。 |
5.元損保の経験がある弁護士なら保険会社の手口を知り尽くしている
ここまで、示談交渉を進める際の弁護士の必要性について説明してきました。
そこで気になるのが、「どんな弁護士に依頼すればいいのか」というところかと思いますが、示談交渉を有利に進めるためには、「損害保険会社の手口を知り尽くしている弁護士」をおすすめします。
損害保険会社は、さまざまな事故対応を行う中で、加害者側に有利に交渉を進めるためのノウハウを蓄えています。
それに十分に抗い、被害者にとって適正な示談金を獲得するためには、その手口を知り尽くした上で対抗できる弁護士が必要なのです。
保険会社の手口を知り尽くしているかどうかを判断する大きな材料として、損保会社での経験の有無があります。
内部で働いた経験から、以下のような知見があるからです。
| ・保険会社が提示する示談金の根拠がわかる ・過失割合の交渉方法などを把握している ・どのタイミングでどんな交渉をしてくるか予測できる |
示談交渉を任せる弁護士を選ぶ際には、法律の知識や過去の解決実績だけではなく、損保会社への知見の深さも判断材料にしてください。
6.自分で示談交渉ができないと思ったらサリュが力になります
交通事故の示談交渉でお悩みなら、サリュにお任せください。
サリュは、これまで2万件以上の交通事故解決実績のある、被害者救済に特化した弁護士事務所です。
交通事故被害者の方が、示談の内容で後悔するようなことがないよう、あなたの立場に寄り添ったサポートを行います。
また、前章で解説した通り、保険会社と戦うにはその手口を知り尽くした、元損保弁護士が強力な味方となります。
サリュの創設者は元損保弁護士であり、その手口やノウハウをサリュ全体で共有し、相手の言いなりにならない体制を作っています。
「納得できない条件を覆したい」
「自分の意見を相手に通したい」
そんな気持ちを抱えながらも、示談交渉にお悩みがある方は、まずはお気軽にお電話などでお問い合わせください。
メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。
7.まとめ
この記事では、示談交渉を自分で行う方法と、おすすめしない理由を解説しました。
内容のまとめは、以下の通りです。
▼示談交渉は自分で行うことも可能だが、被害者が適正な補償を獲得するためにもおすすめしない
▼自分で示談交渉した際によくある後悔は以下の3つ
| 1.相手に都合のいい条件で押し切られる 2.保険会社に治療を打ち切られる 3.示談後に請求できる項目の漏れに気が付く |
▼自分で示談交渉を行う流れ5ステップ
| 1.すべての損害が確定したら示談交渉を開始する 2.相手の保険会社から示談金の提示がある 3.示談金に納得がいかなければ同意せず反論する 4.お互いが納得する金額になったら示談書にサイン又は署名する 5.示談書の返送後、約2週間で示談金が振り込まれる |
▼正当な補償の獲得のために弁護士に依頼したほうがいい理由は以下の3つ
| 1.相手保険会社との交渉を一手に担ってくれる 2.被害者にとって適正な金額の示談金を請求してくれる 3.後遺障害認定などの手続きもサポートしてくれる |
この記事の内容を参考に、納得のいく形で示談交渉の決着をつけられるよう行動してください。
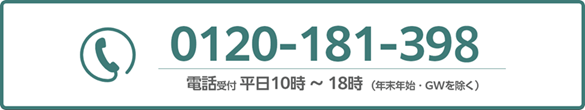

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)
